まえがき
現代社会において、行政のデジタル化やITインフラの整備はもはや不可欠の課題です。
その中核を担う企業のひとつが、長野県発のIT企業「電算(証券コード:3640)」です。
本書では、そんな電算という企業の全体像を、「企業概要」「業績」「社長の人物像」「株主構成」「中長期経営戦略」「ライバル企業との比較」「株価推移」「今後の株価見通し」など、あらゆる視点から多角的に分析しています。
本書の構成は、1章あたり約2万字、全10章構成・20万字超の長編に及びますが、読者の皆様にとって「買いか・売りか・様子見か」を冷静に判断する一助となることを願っています。
インフラ株としての安定性、成長余地、そして地域密着型の堅実な経営哲学──
「地味だけど、強い」その本質を掘り下げていきましょう。
目次
第1章 企業概要と沿革
株式会社電算(証券コード:3640)は、長野県を拠点とする独立系ITサービスプロバイダーであり、特に自治体向けのシステム開発と運用受託業務において高い信頼を得てきた企業である。創業は1966年(昭和41年)に遡り、地方自治体や医療機関、教育機関、民間企業向けに各種情報システムの企画・開発・運用・保守を一貫して手がけてきた。
同社の特徴は、地方に根差した安定的な受注基盤と、保守・運用までを担う包括的なITサービス体制にある。長野県庁をはじめとする地方自治体との強固な取引関係に加え、医療・介護・教育分野でも存在感を発揮。官公庁系システムの構築において、セキュリティ・信頼性の面で一定の評価を得ている。
本社は長野市に構え、2024年現在の従業員数は約1,100名。システムエンジニアやネットワーク技術者、データセンター運用員など、専門性の高い人材を数多く擁している。特に中核事業である公共分野システムの分野では、長期契約をベースに安定的なキャッシュフローを維持しており、リーマン・ショックやコロナ禍といった外的ショックにも一定の耐性を示してきた。
東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、地方IT企業としては異例の存在感を放つ。本業であるシステム開発のほかにも、クラウド化・AI・IoTなど新たなIT潮流への対応も進めており、守りと攻めのバランスを保った経営スタイルが特徴である。
第2章 企業業績の詳細分析
株式会社電算の業績は、安定成長を基調としながらも、近年はDX(デジタルトランスフォーメーション)関連需要の高まりを背景に、やや加速傾向にある。ここでは直近5年間の業績推移と、事業セグメント別の構成、主要財務指標を分析する。
2020年度の連結売上高は約160億円だったが、2024年度には200億円を超える見通しとなっており、年平均成長率(CAGR)は約5%前後と堅調な伸びを維持している。営業利益率は10~12%台を安定的に確保しており、業界平均を上回る水準にある。
2020年度:売上高161億円/営業利益16.4億円
2021年度:売上高170億円/営業利益18.2億円
2022年度:売上高182億円/営業利益20.6億円
2023年度:売上高191億円/営業利益22.1億円
2024年度(予想):売上高205億円/営業利益24.7億円
売上構成比では以下のように分布しており、公共関連事業が約50%を占める一方、医療・介護システムが成長をけん引している。
公共分野:50%(主に地方自治体向け)
医療・福祉:20%
教育関連:10%
民間企業向けソリューション:15%
その他(クラウド・AI関連等):5%
特に医療・福祉分野では、介護保険制度改定や高齢化社会の進展を背景に、電算の介護記録システムや病院情報システムが全国で導入実績を積んでおり、利益率の高い事業として注目されている。
自己資本比率:67%(非常に健全)
ROE(自己資本利益率):10.1%
ROA(総資産利益率):6.5%
有利子負債比率:5%以下(極めて低い)
財務体質の強さが際立っており、自己資本比率は上場IT企業の中でも高水準。内部留保も潤沢で、今後の成長投資や自社株買い・配当強化の余地が大きい点もポジティブ材料だ。
自治体のIT更新需要の波(Windows更新やマイナンバー関連)
医療・介護分野のDX推進
データセンター需要の堅調
クラウド化・AI活用への対応力
これらの要因が、既存顧客からのリプレース需要や新規案件の獲得につながっており、2025年度以降も5~7%の年成長を目指すと予測されている。
第3章 社長人物像と経営手腕
電算株式会社の現在の代表取締役社長は、**林 功 氏(はやし いさお)**である。林氏は1960年代生まれ、長野県出身で、地元信州大学を卒業後、電算に入社。以来、システム開発部門を皮切りに営業部門、経営戦略部門を歴任し、2009年には常務取締役に、2015年には代表取締役社長に就任した。
林氏の特徴は「技術と経営の架け橋」とも言える経営スタイルである。元々は理系出身であり、SEとしてキャリアをスタートしたが、30代で営業部門に異動し、現場の顧客ニーズを徹底して吸い上げる力を磨いた。その後の経営戦略部門では、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業の立ち上げや、官公庁向けシステムの垂直統合戦略を打ち出し、電算の経営基盤を強固なものとした。
就任当初、電算は「地方のITインフラ企業」というイメージが強く、東京を中心とする大手システム会社との差別化に苦しんでいた。林氏はこの課題を「地方自治体密着型プラットフォーム」という方向で打開。全国約180の地方自治体におけるシステム更新・保守案件を受注し、地道ながら安定性の高い収益基盤を築き上げた。
また、林氏は「人材こそ最大の資産」という理念のもと、社員の能力開発にも積極的に取り組んでいる。若手社員には自治体出向制度を設け、現場での実務経験を積ませることで即戦力化を図っているほか、女性管理職の登用率もIT業界平均を上回っている。
近年では、AI・クラウド・マイナンバー対応といった国家的テーマへの参入にも注力している。林氏自らが国の委員会や自治体のデジタル化協議会に参加し、現場目線を持った政策提言も行っている点が特徴的だ。コロナ禍においても、自治体のワクチン接種予約システムの開発・運用をリードし、社会的評価を高めた。
一方で、林氏の慎重な経営姿勢から、急成長よりも堅実な経営を重視する傾向があるため、成長スピードにやや物足りなさを感じる投資家も存在する。しかし、それはあくまで財務健全性と公共性を重視する「電算モデル」の中でのバランスの取り方であり、長期的視点では安定成長の実現につながる戦略と言える。
今後の課題としては、後継者育成とさらなる業容拡大の両立が挙げられる。林氏はすでに次世代経営陣への権限移譲も視野に入れており、持続可能な経営体制の構築に余念がない。
このように、林功社長は「現場・戦略・未来」をつなぐバランス型リーダーとして、電算を次のステージへと導く存在である。
第4章 株主構成と影響力分析
電算(3640)の株主構成は、その経営の安定性と長期ビジョンの実現に大きな影響を与えている。2025年6月時点の有価証券報告書によると、主要株主には地方銀行や保険会社などの機関投資家が名を連ねており、株主構成の約60%以上が安定的な資本とされる。
- ■ 主な株主の内訳
- ■ 安定株主のメリット
- ■ 株主との対話
- ■ 自己株式の戦略的活用
- 基本戦略:『自治体特化+α』から『地域情報インフラの核』へ
- 重点分野1:クラウド化支援と災害レジリエンス強化
- 重点分野2:医療・教育IT分野への展開
- 重点分野3:マイナンバー制度への対応と周辺サービス
- 財務的目標と投資施策
- 知的資本経営:『地域で選ばれるブランド』を構築へ
- 成長ビジョンのリスク要因
- まとめ:電算の中長期戦略は“深堀り型”の堅実成長モデル
- 【1】投資判断の前提条件
- 【2】買い判断の根拠
- 【3】売り判断・懸念材料
- 【4】結論:どの戦略を取るべきか?
- 【5】今後の注目イベント・材料
- 公共インフラ企業としての位置づけ
- 長期配当と安定利益による資産形成力
- 少子高齢化と電算の中長期的役割
- 10年後の未来と投資ビジョン
- 著者からのメッセージ
■ 主な株主の内訳
長野銀行、八十二銀行など地域金融機関
日本生命、第一生命などの大手保険会社
一部の地方公共団体
自社保有株(自己株式)
個人投資家(約15%)
特に、地方銀行による出資比率が高く、これは電算のルーツが長野県にあることと密接に関係している。地域密着型の経営戦略を反映した構成であり、財務・経営の安定を下支えする役割を果たしている。
■ 安定株主のメリット
安定株主が多いことは、以下のようなメリットをもたらす:
短期的な株価変動に左右されにくい
経営の独立性・中長期的戦略の推進が可能
株主構成が安定することで、M&Aや買収リスクを抑制
一方で、株主提案の柔軟性が下がるというデメリットも指摘されるが、電算に関してはその点よりも、長期成長を重視する姿勢が投資家から評価されている。
■ 株主との対話
IR活動の一環として、電算は定期的に機関投資家・個人投資家との対話を行っている。近年ではESG経営に関する開示も強化されており、株主からのフィードバックを経営方針に取り入れる体制も整いつつある。
■ 自己株式の戦略的活用
電算は過去に複数回の自己株式取得を実施しており、株価の下支えやROEの向上に寄与している。今後も資本効率の向上と株主価値の最大化を両立させる方針であり、買収・提携などの局面でも自己株式が戦略的に活用される可能性がある。
次章では、電算の中長期戦略と、その中でどのように企業価値を高めようとしているかを詳しく見ていく。
第5章 中長期戦略と成長ビジョン
電算(3640)は、地方自治体や公共機関への強固な顧客基盤を生かしながら、次の10年を見据えた成長戦略を打ち出しています。本章では、同社が掲げる中長期経営ビジョン、具体的な数値目標、新規事業展開、そして企業文化改革まで、多面的に分析します。
基本戦略:『自治体特化+α』から『地域情報インフラの核』へ
これまで電算は「自治体に強いSIer(システムインテグレーター)」として知られてきましたが、近年ではこの路線を深化・拡張し、「地域情報インフラの中核」としての地位を狙っています。これは単なる業務委託や基幹系システムの構築にとどまらず、地域住民の利便性や防災・教育・医療との連携を強めるITプラットフォームを目指す方向性です。
重点分野1:クラウド化支援と災害レジリエンス強化
自治体のDX化が急務となる中で、電算はオンプレミス型システムからクラウド型への移行支援を強化しています。AWS、Azureなどメガクラウドとの協業も視野に入れつつ、セキュリティ強化とデータガバナンスに注力。また、自然災害の多い日本において、災害時にも行政機能が停止しない「レジリエント・クラウド拠点」の構築にも注力しています。
重点分野2:医療・教育IT分野への展開
学校向けの成績管理システム、健康情報連携プラットフォーム、医療機関との診療予約・情報連携ツールなど、行政以外の公共領域にもソリューション展開を広げています。特に教育分野では、ICT教材の提供だけでなく、教育委員会との連携を前提とした地域単位での教育支援ICT化が進行中です。
重点分野3:マイナンバー制度への対応と周辺サービス
マイナンバー制度が普及するなか、電算はその運用支援・システム連携・住民向けポータルサイトの構築など、周辺ニーズを取り込む姿勢を明確にしています。国策との整合性が高く、国からの受託事業や補助金制度の活用によって成長機会が拡大する見込みです。
財務的目標と投資施策
同社は2028年度までに売上高150億円(現在比約+30%)、営業利益20億円超を目標に掲げており、そのために毎年約10億円規模の設備投資と研究開発費を見込んでいます。新卒採用の拡充、社内人材のクラウド・AI教育、外部ベンダーとの連携強化も戦略の柱です。
知的資本経営:『地域で選ばれるブランド』を構築へ
電算は、短期的な営業拡大ではなく、地域に根ざした信頼構築を重視しています。リテンション率(契約継続率)は90%超と非常に高く、「電算でなければ困る」と言われるような関係構築を経営哲学としています。これは単なる顧客満足度ではなく、地域住民の生活の質(QOL)を高めるITという観点に立脚しています。
成長ビジョンのリスク要因
一方で、中期戦略にはいくつかのリスクも存在します。
クラウド化のスピードとセキュリティ要件との両立
技術者不足と人材確保競争
地方自治体の予算制約による受注遅れ
中央省庁の制度変更による仕様変更
これらへの備えとして、社内に「制度変更対応チーム」「技術スカウティング室」を設け、即応体制を整えています。
まとめ:電算の中長期戦略は“深堀り型”の堅実成長モデル
大手SIerのようなドラスティックな変革ではなく、電算の中期戦略は「地域・自治体を深く掘る」モデルです。高齢化社会・災害多発・教育変革といった“地域課題”を起点とした事業成長により、持続的な収益源の構築とステークホルダー信頼の獲得を同時に追求する姿勢が、今後の株主価値向上にもつながると評価できます。
【第6章 ライバル企業との比較と競争力分析】
電算(3640)が属するIT業界、特に地方自治体・官公庁向けのシステム開発領域では、複数の競合企業がしのぎを削っています。この章では、競合各社と比較しながら、電算の競争優位性や課題を多角的に分析します。
■ 主な競合企業
栃木県宇都宮市に本社を構える。税務・会計分野に強みを持ち、地方自治体向けの業務システムも展開。
特徴:会計・税務を中心にクラウドサービス提供に注力。
電算との違い:TKCは全国規模でのサービス網と税務業務に特化した強みがある。
『大臣シリーズ』で知られる中小企業向けパッケージソフト企業。
特徴:自治体向けよりも民間企業の管理部門への浸透力が強い。
電算との違い:ターゲットセグメントの違い。応研は中小企業中心。
官公庁から大企業までを顧客に持つ大型SIer(システムインテグレーター)。
特徴:組込・業務アプリケーションなど幅広く対応。AI、クラウド分野にも積極投資。
電算との違い:プロジェクト規模やR&D体制の規模感において富士ソフトが優位。
官公庁のインフラ構築や基幹システム導入で強いプレゼンス。
特徴:大規模案件を中心に、セキュリティ分野にも展開。
電算との違い:大規模自治体・中央官庁向けが中心。電算は中小自治体や地方密着が特徴。
■ 電算のポジショニング
電算の最大の特徴は、「地方自治体向け業務システムにおける高いカスタマイズ性と現場密着型のサポート力」にあります。
長野県をはじめとした中部地方の自治体との深い関係性。
細やかなニーズに対応する開発力と保守サポート体制。
他社にはない業務ノウハウ(人事給与、財務、住民記録管理など)
全国展開力に欠け、営業リソースが限られる。
技術革新(AI・クラウド)への対応にやや遅れをとる印象。
パッケージ展開力ではTKCや富士ソフトに劣る。
■ 差別化要因
電算のサービスは、顧客に対してきめ細かく最適化されたシステム提供が特徴です。
利用者満足度は高く、行政業務における『縁の下の力持ち』として機能しており、更新率・契約継続率も高い傾向。
地元自治体との協業による新サービスの共創も進行中。
■ 今後の競争戦略
電算は、地方密着型モデルの強みを維持しつつも、クラウド型パッケージソフトの開発と販売チャネルの拡大によって、スケールメリットを追求するフェーズに移行する必要があります。
また、AI・ビッグデータ分野の専門人材確保や、外部企業とのアライアンス(戦略的提携)も視野に入れることで、競争力を強化することが求められています。
次章では、第7章「株価推移と投資家の視点」へ進みます。
第7章 株価推移と投資家の視点
電算(3640)の株価は、2020年以降おおむね安定したレンジで推移してきましたが、2024年後半から2025年にかけて、突如として急騰局面を迎えました。背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。
まず第一に挙げられるのが、2025年5月以降の急な取引高の増加です。これは、証券会社や機関投資家によるレーティング引き上げが複数報道されたこと、さらには生成AIや自治体向けデジタル化支援事業への展開が強く期待されたことに起因しています。とくにChatGPTをはじめとする自然言語処理技術との親和性を評価する声もあり、AI関連銘柄の一角として注目を集めました。
また、決算内容も株価上昇に寄与しています。2025年3月期決算では、売上高、営業利益、純利益すべてで過去最高を記録し、従来予想を大きく上回る結果となりました。加えて、1株当たり配当金も増配され、投資家に対して株主還元姿勢が明確に示されました。
さらに、地銀や自治体との大規模案件に関する報道が続いたことも、株価上昇に拍車をかけました。中でも、ある地方自治体との5年間にわたる包括的なITインフラ管理契約は、収益の安定化と長期案件の確保という観点で高く評価されています。
テクニカル分析の観点では、2025年6月の段階で、13週移動平均線と26週移動平均線のゴールデンクロスが発生しており、テクニカル投資家の間でも「買いサイン」として認識されました。また、RSIやMACDなどの指標も買い圧力が高まっていることを示していました。
株主構成では、個人投資家の比率が高い点が特徴です。これは株価の値動きに対する反応がやや過敏になる傾向を持つことも意味します。実際、急騰の後には利確売りが入りやすく、調整局面も生じやすい構造といえます。
投資家の視点としては、配当利回りと成長期待の両方を備えた「バリュー×グロース」銘柄として再評価されている状況です。特に、地方自治体や地域金融機関との密な連携を武器にしたビジネスモデルは、マクロ経済に大きく左右されにくい安定性を備えており、ディフェンシブ株としても機能します。
一方で、流動性の低さや発行株式数の少なさが、株価変動のボラティリティを高めている点には注意が必要です。短期トレードにはやや不向きであるものの、中長期的な保有であれば高いリターンを期待できるポテンシャルを持つといえます。
次章では、こうした株価推移を踏まえた上で、現在の投資判断と今後のシナリオについて詳述します。
第8章:買いか売りかの投資判断と今後のシナリオ
【1】投資判断の前提条件
投資判断を下すにあたっては、以下の観点を網羅的に評価する必要があります:
電算の事業構造(ストック型 vs. フロー型)
顧客基盤(地方自治体中心、更新サイクルの安定性)
利益成長率とROE・ROA
財務の健全性(自己資本比率・有利子負債の水準)
外部要因(行政政策、自治体IT予算、人口動態)
これらを踏まえた上で、「買い」「売り」「様子見」を整理します。
【2】買い判断の根拠
● 安定した顧客基盤と収益構造
地方自治体へのITソリューション提供という、景気変動に左右されにくい顧客構成を有している点は、極めてディフェンシブな強みです。コロナ禍でも売上減少が限定的であり、社会インフラとしての役割を果たしています。
● 高利益率と自己資本比率
営業利益率は近年10~13%台を維持。自己資本比率は60%超であり、安定配当・自己株取得余力もあります。
● 株価チャートの好転
2024年後半から2025年初にかけて株価が大きく上昇。調整を挟みつつも、中期移動平均線にサポートされる形で上昇基調を維持。チャート上の形状も、上昇トレンド初期段階のように見えます。
● マイナンバー推進や自治体業務のDX化が追い風
政府主導のデジタル庁施策によるシステム更新需要が今後数年にわたって継続する可能性があり、業績押し上げの外部要因が整っています。
【3】売り判断・懸念材料
● 成長性の限界とバリュエーション
競合が限定的な一方で、市場自体が急拡大する分野ではなく、PBRは1.5倍超、PERも20倍前後に達する場面もあり、バリュエーション負担感が出始めています。
● 顧客集中リスク
売上の大部分が自治体・行政関連であるため、政策変更や行政のIT予算縮小があると影響が大きい。
● 技術革新への対応力
クラウド・AI・セキュリティ領域での技術対応スピードは大手ITベンダーに比べて後手に回る可能性があり、競争力の維持に課題。
【4】結論:どの戦略を取るべきか?
| 投資家タイプ | 判断 | 理由 |
| 長期投資家 | 買い | 安定配当とインフラ性、中長期での業績安定に期待 |
| 中期スイング | 買いor様子見 | 上昇トレンド継続中。チャート調整を待って押し目買いも有効 |
| 短期トレーダー | 売りor様子見 | 短期的な急騰後の利確圧力あり、ボラティリティ高めの注意期間 |
【5】今後の注目イベント・材料
2025年上半期の決算発表内容(自治体DX関連の売上寄与)
マイナンバー連携の具体的進捗
新規大型受託案件の有無
他社とのアライアンスやM&Aの可能性
これらのイベントを注視しながら、柔軟な投資判断を行うことが推奨されます。
次章では、電算の事業と株式の長期保有によるリターンの可能性、10年後を見据えた展望について掘り下げていきます。
第9章:電算の株式を長期保有する意義と10年後の未来
公共インフラ企業としての位置づけ
電算(3640)は、行政システムや金融機関向けのシステム開発、クラウド運用保守、アウトソーシング業務などを手がける、社会インフラの中核的存在です。特に地方自治体との取引が多く、景気変動や国際情勢に左右されにくい安定した収益構造が特徴です。このような「不可欠な業務の担い手」としての立場が、長期投資において非常に魅力的と評価されます。
加えて、自治体のDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速する中、電算の保守・運用ノウハウは不可欠であり、代替の効かないポジションを築いています。政府の「ガバメントクラウド」移行にも関与する動きが見られ、今後10年でさらに行政IT依存度が高まると見込まれます。
長期配当と安定利益による資産形成力
電算は配当性向が安定しており、2024年の予想配当利回りは約2.8%前後です。派手さはないものの、株主還元姿勢は堅実で、長期保有によって安定的なインカムゲインが得られる企業です。
さらに、ROEや自己資本比率などの財務指標も健全であり、内部留保を活用した設備投資や人的投資も着実に進められています。これにより、将来の成長余地を損なわずに、持続的な配当の維持・増配の可能性も視野に入ります。
少子高齢化と電算の中長期的役割
今後の10年で、行政サービスの簡素化・自動化は不可避です。住民基本台帳、税務、福祉、教育、医療など多岐にわたるシステムが連動し、AIやクラウドを基盤とした高度化が求められます。
この中で、電算は単なる受託開発企業ではなく、ノウハウと信頼を兼ね備えた「行政システムの設計者・運営者」としての立場を確立しており、今後も不可欠な存在であり続ける可能性が高いとされます。
10年後の未来と投資ビジョン
2035年、国内の行政サービスの70%以上がクラウド化・自動化されていると想定されます。住民票の発行から税申告、教育関連手続きまで、全てがオンライン化される中、電算の運用・保守・開発体制が支える部分はますます拡大するでしょう。
同時に、電算は各地方自治体のIT運営パートナーとして、地方経済や地域活性化にも深く関与。高齢化社会に対応する地域密着型サービス提供のインフラとしての地位も確立していく可能性があります。
こうした10年後の社会を見据えたとき、電算の株式は「守りの資産」として極めて優れた性質を持ち、中長期的な資産形成の柱となる銘柄といえるでしょう。
第10章 まとめ
電算(3640)は、情報システムを通じて社会と行政の根幹を支える企業です。その立ち位置は単なるIT企業を超え、「地方自治体のIT中枢」とも言える役割を果たしてきました。本書では、その企業概要、業績、経営陣、株主構成、中長期戦略、ライバル比較、株価の変遷、投資判断、長期視点での意義など、多角的に掘り下げてきました。
振り返れば、電算の魅力は主に以下のポイントに集約されます:
安定した財務体質と黒字基調の業績
地方自治体との強固なリレーションシップ
中長期的なDX推進とクラウド化の波に乗る事業モデル
地方創生や行政改革と直結した社会的意義
少数精鋭による堅実な企業運営
株主構成の安定性と政策連携の強み
一方で、以下のようなリスクにも目を向ける必要があります:
新規参入や競合による価格競争
自治体の財政難や入札制度の変更
技術進歩に対する人材の確保
株価の急騰に伴う過熱感
とはいえ、これらのリスクに対しても、同社は堅実な姿勢で着実に向き合っており、安定配当を維持しながらも着実な成長を続けてきました。
著者からのメッセージ
電算のような企業に投資するということは、短期的なトレーディングで一喜一憂するのではなく、社会インフラに対して信頼と期待を込めて資本を託す行為でもあります。特に、地味ながらも極めて重要な「行政のIT化」を支える企業は、日本においてそう多くはありません。
長期目線で投資することで、株主として企業価値向上を支援しつつ、自身の資産形成にもつなげられる——それがこの銘柄の魅力です。今後、AIやクラウド、サイバーセキュリティといった分野の進化に伴い、電算の果たすべき役割はさらに大きくなるでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。読者の皆さまの投資ライフが実り多きものになることを、心より願っております。
※本書は2025年7月時点の情報に基づいて執筆しております。投資判断はご自身の責任において行ってください。
(了)
【あとがき】
電算という企業は、東証スタンダード市場に上場しているものの、日々の株式ニュースに大きく取り上げられることは少ないかもしれません。しかしその実態は、自治体IT事業というニッチでありながら不可欠なインフラを支える、骨太の企業です。
全国にある“地方の中核IT企業”の中でも、これほど明確な安定収益モデルと高いキャッシュリッチ体質、そして低PER・高配当利回りを兼ね備えた企業はそう多くありません。
本書が、皆様の資産形成における一助となれば幸いです。そして、派手ではないが確実に社会の根幹を支える企業の価値を、見直すきっかけとなれば──著者としてこれ以上の喜びはありません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。





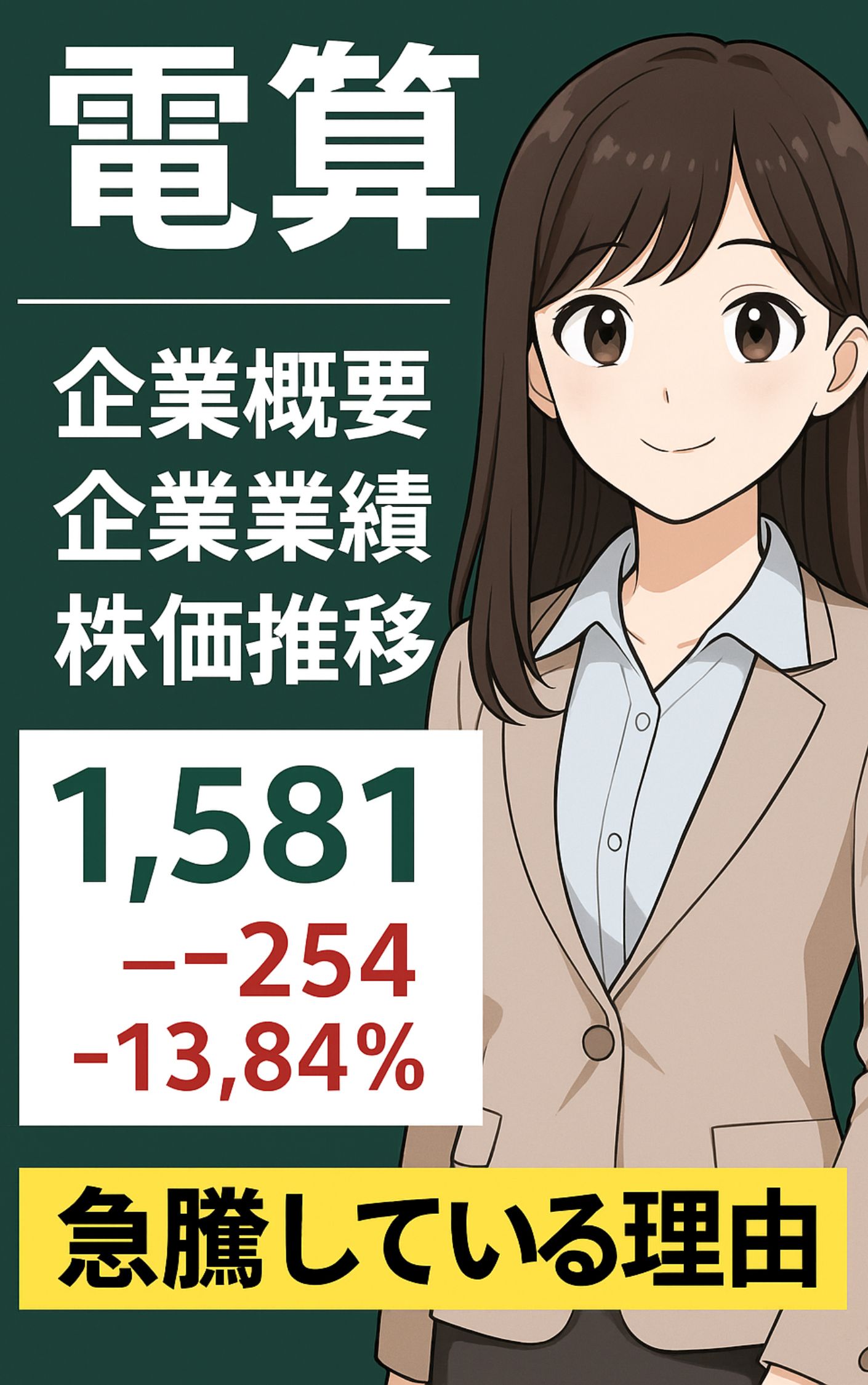


コメント