まえがき
現代は「投資の時代」です。
しかし、インターネットやSNSを通じて膨大な情報が溢れ、
何が「正しい投資」なのか分からず不安を感じている方も多いでしょう。
この本では、経済学という「普遍的な理論」に基づき、
地政学的リスク、インフレ、金融政策、心理的罠といった
あらゆる角度から「正しい投資とアブない投資」の違いを解説します。
特別な才能や複雑な手法ではなく、
正しい知識・正しい行動・正しいマインドセットこそが
個人投資家の最大の武器です。
本書があなたにとって「知識による資産防衛」の一助になることを願って。
さあ、投資の本質を学ぶ旅へ出かけましょう。
目次
第1章:投資と経済学の関係 ― 「なぜ経済学が投資に必要か」
第3章:投資しなければ資産は縮む ― インフレ時代の資産防衛
第4章:最低限知識としての投資戦略 ― インデックス投資 vs. 個別株投資
初心者にはインデックス投資から始め、安定した資産形成を目指す
投資に慣れてきたら個別株に挑戦し、さらに高いリターンを目指す
第5章:詐欺・ノイズを見抜く力 ― 投資情報リテラシーの重要性
第9章:実践者のケーススタディ ― 資産運用の成功例・失敗例
第1章:投資と経済学の関係 ― 「なぜ経済学が投資に必要か」
1-1. 投資と経済学の接点
「投資はセンスや勘で行うもの」と思われがちです。
しかし著者・上念司氏は、本書でこう指摘します。
「正しい投資をするには、まず経済学的なモノの見方が不可欠だ。」
なぜなら、株式市場も為替市場も、
根底では 経済法則が支配する「人間の行動の集積体」 だからです。
経済学を知らずに投資することは、
「地図を持たずに山を登る」ようなものです。
1-2. インフレと通貨供給の基本
著者は「現代投資家にとって必須の知識」として、
マクロ経済の基礎を挙げます。
特に重要なのは 「インフレのメカニズム」。
政府や中央銀行がお金を大量に発行すれば、
通貨の価値は下がり、物価が上がる。
これは「貨幣数量説」の基本的ロジックです。
投資家として 「物価がどの方向に動くか」を読む目線 が、
長期的資産形成に不可欠であると説きます。
1-3. GDPと成長期待
著者は「GDP成長率」の理解も必須と指摘。
国の経済成長は「将来の企業収益」に直結する。
GDP成長が期待される国・地域の資産は「買い」、
成長が鈍化・停滞する国の資産は「売り」対象。
たとえば、米国株が強いのは「成長期待」があるから。
経済成長率と市場リターンの関係は、
経済学的な基本事項です。
1-4. お金の流れを見る ― 「市場の本質」
著者が繰り返し主張するのは、
「マーケットにおけるお金の流れ(資金フロー)を理解せよ」ということ。
中央銀行の金融政策
政府の財政出動
民間部門の投資・貯蓄動向
これらは 経済学的ロジックで予測できる部分が多い。
「ニュースの見方」「数字の読み方」を
経済学ベースに変えるだけで投資の精度は大きく上がります。
1-5. 日本経済の特殊性
本書では、日本の経済構造への分析も重要な柱。
これらを踏まえると:
✅ 日本に偏った投資ポートフォリオは危険
✅ 成長余地のある海外市場への資産分散が必要
という現実的な結論に至ります。
1-6. 経済学を「投資に活かす」方法
著者は「学問としての経済学」ではなく、
「実践ツールとしての経済学」を強調します。
具体的には:
物価・金利の動向に基づく投資判断
金融緩和・引き締め局面を読む目線
市場の需給関係の把握
これらは 感覚や憶測ではなく、
“経済学的に正しい考え方”として習得できるもの です。
1-7. 投資初心者へのメッセージ
最後に著者は次のように結びます。
「初心者ほど経済学を学び、基本に立ち返れ。
そうすれば“アブない投資”を避け、“正しい投資”ができる。」
派手な儲け話に振り回されず、
経済の基礎を理解することが、
最も地味だが最強の防御策です。
第2章:地政学リスクの本質 ― サル山理論で読む国際経済
2-1. 投資における「地政学的視点」の重要性
著者・上念司氏は、投資における「地政学的リスク」の軽視が
個人投資家にとって重大な落とし穴になると指摘します。
「経済・投資はグローバル化している。
世界情勢を知らずして正しい投資判断はできない。」
米中対立、ロシア・ウクライナ戦争、中東情勢などは
マーケットに直接的な影響を与える要素です。
2-2. サル山理論 ― 習近平体制の中国を読む
著者が本書でユニークに紹介するのが
「サル山理論」。
これは、動物の世界で見られる「権力闘争」の原理を、
中国の政治構造に応用して読み解くフレームワークです。
✅ 習近平は一見盤石に見えるが、
内部には派閥闘争・利権構造・不満が渦巻いている。
✅ 権力の集中が行きすぎると、
経済の柔軟性・イノベーションが失われる。
こうした体制リスクは、
「中国経済の不透明さ」と「資本逃避圧力」を生み出し、
結果として「中国関連株の不安定性」に直結するのです。
2-3. 米国の覇権と米中経済摩擦
著者は、米国経済を取り巻く「覇権の維持」という視点も強調します。
米国の強み:
一方で、米中対立は今後も激化が予想され、
その影響が「半導体」「エネルギー」「金融市場」に現れる。
ここで重要なのは:
✅ 中国市場依存度の高い日本企業への注意
✅ 米国と中国どちらが「長期的に安定して成長するか」を見極める
2-4. 日米同盟と日本の位置づけ
著者は、日本経済の「安全保障と同盟関係」にも着目。
日本は米国と強固な同盟関係にある。
地政学的には「米国側」として資本主義経済圏に位置づけられる。
そのため、日本国内の投資環境は
米国の政策・金融戦略の影響を大きく受ける構造。
個人投資家が 「米国政治・経済動向を最優先でウォッチする必要がある」
と著者は説きます。
2-5. 有事の資産防衛 ― 地政学的ショックへの備え
著者は「戦争・災害・政変などの突発的リスク」を
「ブラックスワン」と呼び、
投資家として「想定内」として備えるべきだと述べています。
具体的な対応策:
✅ 資産分散(国内外・通貨・業種・市場)
✅ 流動性確保(現金・換金性の高い資産)
✅ 防衛産業・インフラ株への部分的投資
地政学リスクは「いつ起きるかわからない」からこそ、
最初から織り込んだポートフォリオ設計が必要。
2-6. 「一方向投資」の危うさ
特定の国・地域に偏った投資(例:中国・東南アジア集中)は
「地政学的ショックで一瞬にして毀損するリスク」があります。
著者のメッセージ:
「長期投資家こそ“地政学分散”を徹底せよ。」
これは単なる業種・銘柄の分散に留まらず、
国・地域リスクを横断的に管理する発想です。
2-7. 地政学リスクに対する「正しい投資家の態度」
最後に著者はこうまとめています。
✅ 地政学リスクは「見て見ぬふり」できない時代。
✅ 「分散」と「シンプルな守りのルール」で備えることができる。
✅ 世界情勢の基本構造(米中・米露・中東など)は必ず押さえる。
つまり、「経済学+地政学的教養」が
これからの「正しい投資家」に必要な素養だと説いています。
第3章:投資しなければ資産は縮む ― インフレ時代の資産防衛
3-1. 貯金だけでは資産が目減りする
著者は冒頭でこう警告します。
「インフレ下では現金だけを持っていること自体がリスク。」
経済学的に考えれば、物価上昇(インフレ)が続く限り、
現金の購買力は低下していく。
つまり、 銀行預金に置いておくだけでは実質的に“資産が目減り”していく のです。
3-2. インフレという「見えにくい敵」
物価上昇率が2%でも、
10年後には現金の価値は約82%に減る。
100万円の預金 → 実質的には82万円の価値に。
著者は「金利ゼロ環境下で貯金だけに頼ることは、
将来の生活を危険に晒すこと」だと強調します。
3-3. 投資は“資産を守る行動”である
著者が強調するのは、
「投資は資産を増やすためだけでなく、守るための手段」。
資産を実質的に保全するためには:
✅ 株式などインフレ連動資産を持つ
✅ 通貨分散(ドル建て資産など)を行う
✅ 長期的視野で資産形成を図る
インフレの時代だからこそ、
投資を「守りの戦略」として位置づける必要があります。
3-4. インフレ耐性のある投資先
著者は、インフレ時代に有効な資産クラスとして:
株式(特に高配当・優良企業)
→ 物価上昇とともに売上・利益も増える構造。
不動産
→ 賃料収入がインフレ連動。
インフレ連動債(TIPSなど)
これらを分散して保有することを勧めます。
3-5. 「過度なリスク回避」が最大のリスク
投資を避ける理由として多くの人が挙げるのは:
元本割れの不安
価格変動のストレス
しかし、著者はここに鋭く切り込みます。
「リスクを避けようとして貯金一辺倒になることが、
実は最大のリスク。」
経済学的に「現金の価値は物価に対して常に目減りする」という原則を
しっかり理解する必要があるのです。
3-6. 投資のタイミング論を超える
インフレ対策として重要なのは、
「一度に大金を投じること」ではなく、
「時間分散をして淡々と積立投資をすること」。
ドルコスト平均法
→ タイミングを読む必要がない。
→ 平均取得単価を平準化できる。
著者は「マーケットを読む必要はない。
淡々と積立を続けることこそが正解」だと述べます。
3-7. 長期戦略が鍵
投資で資産防衛するためには、
短期的な価格変動に耐える覚悟と計画が不可欠。
10年、20年単位で資産を成長・保全する視点。
目先の上下は「ノイズ」として処理する冷静さ。
これがインフレ時代に資産を守る唯一の方法です。
3-8. 「金利とインフレの関係」も押さえる
著者は「金利が低いからといって安心するのは危険」と警告します。
金利は一時的に低く抑えられていても、
インフレが加速すれば実質金利は低下。
この「インフレと金利の関係」を理解することが、
投資判断の基礎。
3-9. まとめ:「投資しないリスク」を理解せよ
著者はこの章を次のメッセージで締めくくります。
✅ インフレは静かに、そして確実に現金の価値を奪う。
✅ 投資は“増やすため”ではなく“守るため”のツールでもある。
✅ 正しい経済学的視点を持ち、淡々と積立投資を継続せよ。
「投資をしないことこそ最大のリスク」
―― これが著者の一貫した主張です。
第4章:最低限知識としての投資戦略 ― インデックス投資 vs. 個別株投資
4-1. インデックス投資の基本
投資初心者にとって「どのように資産を増やすか?」という最初の課題に対して、著者は インデックス投資 を強く勧めています。
インデックス投資とは、
「市場全体」を代表する株式や債券の指数(インデックス)に投資する方法で、
例えばS&P500 や TOPIX といった指数に連動するETFを購入することです。
インデックス投資の最大の利点:
この手法は、市場全体の成長を享受しつつ、
個別株に比べてリスクを大きく抑えることができます。
著者は、「投資初心者こそインデックス投資から始めるべきだ」と述べています。
4-2. 個別株投資の魅力とリスク
一方で、個別株投資はリスクを取ることになりますが、
それゆえに大きなリターンが期待できるというメリットもあります。
著者は、「個別株投資は経済学とファンダメンタル分析に基づく投資判断ができるならば、
非常に魅力的な選択肢」と述べています。
ただし、リスクも大きく、
適切な分散と企業分析がなければ、損失を被る可能性が高くなります。
4-3. 「投資初心者」にはまずインデックス
著者は、**「初心者がいきなり個別株に手を出すべきではない」**と警告しています。
その理由は以下の通りです:
そのため、まずはインデックス投資で市場全体の成長を享受し、
投資家としての基礎を固めることが重要です。
4-4. 投資信託とETFの選び方
インデックス投資を行う際に利用する金融商品として、
投資信託 と ETF(上場投資信託)があります。
投資信託
→ 購入方法が簡単で、自動積立が可能。
→ 手数料が少し高い場合がある。
ETF
→ 取引所で売買可能で、取引コストが低い。
→ 一部のETFは、手数料が非常に低い。
著者は「ETFを選べば、より低コストで長期運用が可能」とし、
特にコスト面での優位性を挙げています。
4-5. アクティブ運用 vs パッシブ運用
著者は、投資家にとって重要なのは、
アクティブ運用 と パッシブ運用 の違いを理解することだと述べています。
アクティブ運用
→ ファンドマネージャーが積極的に市場を分析し、個別銘柄を選んで運用。
→ 高リスク・高リターン。
パッシブ運用
→ 市場全体を反映したインデックスに連動する運用。
→ 低リスク・安定したリターン。
著者は「アクティブ運用が必ずしも有利ではない」とし、
実績のあるパッシブ運用を選ぶことを推奨しています。
4-6. 株式投資の長期的な視点
株式投資を行う上で重要なのは、「長期視点」です。
短期的な市場の動きに一喜一憂しないこと
10年、20年単位で資産を増やすことを目指す
著者は、特に株式市場の短期的な変動に反応するのではなく、
「経済全体の成長」に投資する姿勢がFIRE実現には不可欠だと述べています。
4-7. ポートフォリオの分散とバランス
投資をする際には「分散」が欠かせません。
著者は次のようにポートフォリオの分散を推奨します:
地域分散
→ 米国株中心でも、成長を見込める他国・地域に分散。
資産クラスの分散
→ 株式だけでなく、不動産・債券・金などの分散。
リスクのバランス
→ ハイリスク・ハイリターンの資産と、安定した資産を組み合わせる。
これにより、リスクを抑えつつ、リターンを最大化することができます。
4-8. まとめ:インデックス投資と個別株投資の使い分け
著者はこの章で、インデックス投資と個別株投資を使い分ける重要性を説いています。
初心者にはインデックス投資から始め、安定した資産形成を目指す
投資に慣れてきたら個別株に挑戦し、さらに高いリターンを目指す
インデックス投資と個別株投資を適切に組み合わせることで、
FIREを目指す投資家にとって理想的な資産形成が可能になります。
第5章:詐欺・ノイズを見抜く力 ― 投資情報リテラシーの重要性
5-1. 投資詐欺の巧妙さ
著者は「正しい投資」の大前提として
「詐欺から身を守る力」 を挙げています。
特に日本では高齢者を狙った金融詐欺が多発。
「元本保証」「必ず儲かる」といったセールストークに
簡単に引っかかる人が後を絶ちません。
著者はこう警告します。
「投資において“絶対に儲かる”は存在しない。
この一言を肝に銘じるだけでも被害は防げる。」
5-2. ノイズ情報に惑わされない
現代はSNSやネットメディアが発達し、
投資情報があふれています。
しかし著者は次のように述べます。
「日経新聞もテレビもSNSも“ノイズの温床”になり得る。」
「著名人が買った」「インフルエンサーが推奨」
こうした情報に流されること自体が
投資判断の質を落とします。
正しい投資家は 情報源を吟味し、
“本質的な情報”と“ノイズ”を見分ける目” を鍛える必要があります。
5-3. 経済学的視点で情報を見抜く
著者は投資判断をするとき、
「経済学的に正しい情報」かどうかを必ず確認すべきだと説きます。
例えば:
✅ “経済成長を無視した妙な理論”には注意
✅ “短期間で巨額利益を謳う商材”は無視
✅ 「インフレ」「金利」「通貨」の基本に基づいて評価
5-4. SNSとの付き合い方
SNSには有益な情報もありますが、
著者は「SNSの情報に直接従うのではなく、
“他者の意見を参考にしつつ自分で判断”すること」を推奨。
SNSは「学びの場」ではあっても「答えを得る場」ではない。
「答えは常に自分の中にある」
―― これが正しい投資家の姿勢です。
5-5. 投資詐欺の典型例
著者は投資詐欺の典型例として次を挙げます。
未公開株投資詐欺
ファンド購入の手数料詐欺
仮想通貨を装った高利回り詐欺
これらの共通点は:
✅ 説明が複雑でわかりにくい
✅ 高利回りを強調
✅ 「今しかない」「急げ」と煽る
「投資初心者は“わからない商品には手を出さない”という基本ルールを徹底せよ」
と著者は強く警告します。
5-6. 口コミの危うさ
口コミサイト・ネット掲示板・投資コミュニティ。
こうした場も「実は詐欺師にとっての営業ツール」になる危険性があると著者は指摘。
サクラ投稿
宣伝目的のやらせレビュー
“仕込みコメント”
口コミはあくまで「一意見」であり、
自分の資金を投じる判断基準にすべきではありません。
5-7. 投資判断に必要な「沈黙」
著者は「投資判断に一番重要なことは“沈黙”だ」と述べています。
✅ 投資判断をSNSで相談しない
✅ 他人の雑音を遮断する
✅ 自分で資料を読み、自分で考える
孤独を厭わない姿勢が「詐欺とノイズを見抜く」最大の防御策です。
5-8. まとめ:「投資家の自己防衛マインド」
この章の結論として、著者は次の3原則を提案しています。
1️⃣ “絶対に儲かる”は存在しないと理解する
2️⃣ 情報リテラシーを鍛え、ノイズを見抜く力をつける
3️⃣ “孤独な投資判断”を恐れない
「投資詐欺とノイズ情報に振り回されない自己防衛マインド」
これがFIREを目指す個人投資家にとっての重要な武器です。
第6章:行動経済学と投資心理 ― 心理的罠とその対策
6-1. 投資は心理との戦い
著者・上念司氏はこう述べます。
「正しい投資は“メンタルゲーム”である。」
経済合理性だけでは投資で成功できない。
なぜなら、投資家は「人間」であり、
感情や直感に流されやすい生き物だからです。
ここで重要なのが「行動経済学」という視点。
6-2. 行動経済学の基本概念
行動経済学は「人間の非合理な経済行動」を分析する学問。
著者は次のような心理的バイアスを紹介しています。
✅ 損失回避性
損したくないあまり、利確が早く、損切りが遅くなる。
✅ 確証バイアス
自分の信じたい情報だけを集め、反対意見を無視。
✅ フレーミング効果
同じ内容でも「儲かる話」と強調されると乗りやすい。
6-3. 群集心理の罠
著者は、投資における「群集心理」にも警鐘を鳴らします。
SNSやマスコミの煽り
周囲の成功者の話
こうした「みんなが買ってるから安心」という心理は、
バブルの温床であり、「アブない投資」そのもの。
✅ 投資判断は孤独であってよい。
✅ 「自分の基準」で行動することが重要。
6-4. プロスペクト理論に学ぶ
行動経済学の代表的理論「プロスペクト理論」によると、
人間は「利益より損失に2倍以上敏感」だと言われます。
この特性が投資における代表的失敗パターン:
小さな利益をすぐ確定
大きな損失を抱えてしまう
著者は「損失回避本能に打ち勝つには、
ルール化・自動化が有効」と述べます。
6-5. 感情的決断を回避する方法
著者の具体的提案:
✅ 投資ルールを事前に紙に書いて「見える化」
✅ ルール通りに実行できる仕組みを作る(例:自動積立)
✅ 投資判断に「感情」が入り込む余地をなくす
「感情の排除は不可能。
ならば仕組み化で感情を排除せよ。」
という合理的アプローチです。
6-6. マーケットの「一喜一憂」を捨てる
マーケットは毎日変動します。
価格の上下は自然現象のようなもの。
著者は「投資家は市場のノイズに反応する生き物だが、
これにいちいち反応していたら疲弊する」と述べます。
✅ 週1回の口座確認
✅ 目標未達なら放置
✅ 必要以上にニュースを見ない
こうした“距離感”が投資家心理を守ります。
6-7. 投資初心者こそ「心理管理」が重要
著者が強調するのは:
「初心者ほど心理面の罠にかかりやすい。」
SNSの成功談を真に受ける
短期的に利益を上げようと焦る
自分のルールを守れず衝動的に売買
これらの罠を防ぐには「行動経済学の理解」が役立ちます。
6-8. まとめ:自分をコントロールせよ
著者の最終メッセージ:
✅ 投資心理を理解することは「相場観」に勝る武器
✅ ルール化・自動化で心理的弱点を補う
✅ 短期変動に一喜一憂せず、長期目線を持つ
「行動経済学の知恵を武器に、
自分の心をコントロールできる投資家になれ。」
第7章:資産防衛としての投資 ― 経済常識・非常識の見極め
7-1. 投資は「攻め」ではなく「守り」
著者・上念司氏は強調します。
「正しい投資は“守り”のために行うもの。」
一攫千金を狙うのではなく、
インフレ・経済停滞・税負担増などのリスクから
自分の資産を守るための行動 こそ投資の本来の姿だという考え方です。
7-2. 経済常識 vs. 誤解
投資家として必要なのは
「経済常識」と「非常識」の見極め。
著者は次のように述べます。
✅ 「銀行預金は安全」は誤解。
インフレによって実質価値は下がる。
✅ 「国の借金=危険」も過剰なイメージ。
日本の借金は“自国通貨建て”だから即破綻はしない。
✅ 「株式投資は危ない」は過去の固定観念。
インフレ時代にはむしろ現金だけに依存する方が危険。
このように、現代経済に合った正しい常識を学ぶことが重要です。
7-3. 日本特有のリスク
著者は「日本人特有の資産形成の課題」にも言及。
高齢化による将来不安
低金利下の貯蓄志向
株式や投資に対する心理的抵抗
これらを克服するためには
「資産運用=資産防衛」という意識改革が必要 だと説きます。
7-4. 防衛型ポートフォリオの構築
資産防衛としての投資では
「リターンの最大化」ではなく「安定性・持続性」が主眼。
著者の考える基本戦略:
✅ 高配当株・ETFを中心に据える
✅ 一定割合の現金(生活防衛資金)を持つ
✅ インフレ耐性資産(不動産・金など)を組み込む
多様化・分散を徹底することで
「市場ショックにも耐える資産構造」を作ることができます。
7-5. 長期目線の重要性
資産防衛投資は「短期で結果を求めるものではない」。
市場変動に惑わされない
長期保有による複利効果を享受
著者は「10年、20年後を見据えた安定的資産形成」が
最大の資産防衛策だと力説しています。
7-6. リスク管理の基本
リスクをゼロにすることは不可能。
だからこそ著者はリスク管理のための基本原則を示します。
✅ 投資先の分散
✅ 通貨の分散
✅ 現金比率の適切な維持
これらは「守りの投資の三本柱」であり、
個人投資家が簡単に実践できる具体的行動です。
7-7. 「守る意識」が利益を生む
皮肉なことに、
「守る意識」で投資に臨む方が、
結果的に安定したリターンを得やすいと著者は言います。
短期売買に走らない
ハイリスク商品に手を出さない
資産を守る構造を維持する
守りこそが、長期的には最大の攻めになるという逆説です。
7-8. まとめ:「常識を見直し、自分を守る投資を」
著者の結論はシンプルです。
✅ 投資は「資産を守る戦略」だと理解する
✅ 古い常識(貯金一辺倒)から脱却する
✅ 経済リスクから自分の生活を防衛する行動を徹底する
「資産防衛としての投資を、今すぐ始める」――
これが著者の強いメッセージです。
第8章:相場観の養い方 ― マクロ・ミクロ視点の使い分け
8-1. 「相場観」が重要な理由
著者・上念司氏はこう述べます。
「投資で最も危険なのは“なんとなく投資する”こと。
自分の相場観を持つことが何より大切だ。」
相場観とは、「経済の全体像」と「個別の企業・市場」を
適切に見渡し、自分なりの見通しを持つことです。
これがなければ、SNSやニュースの情報に
右往左往することになり、
「アブない投資家」になってしまうのです。
8-2. マクロ経済視点の重要性
相場観の第一歩は 「マクロ経済の理解」。
著者は次の指標を常に確認することを勧めています。
✅ 金利(特に長短金利差)
✅ 物価動向(インフレ率)
✅ GDP成長率
✅ 雇用統計
✅ 各国中央銀行の金融政策
これらを俯瞰することで、
「市場全体の方向性(リスクオンかリスクオフか)」
を見極めることができます。
8-3. ミクロ経済視点の重要性
著者はさらに、「個別企業・業界の視点」も重視します。
決算情報
業界動向
競争優位性
特に「どの企業がマクロ経済の変化に強いのか」
を分析する目が必要。
マクロだけを見ていても個別銘柄は選べず、
ミクロだけを見ていても相場全体に流される。
この「バランス」が相場観を磨くカギです。
8-4. 日経新聞・SNSに依存しない情報収集
著者は、投資家の多くが「日経新聞の見出し」に
左右されすぎていることを問題視。
✅ 見出しだけでは本質を見誤る
✅ SNSの「話題株」は往々にして「売り抜けられる側」
情報収集の際には「自分で元データを当たる習慣」が重要だと強調します。
8-5. 長期と短期の視野を整理する
相場観を養うためには、
「長期と短期の整理」も必要。
短期的な材料(選挙・金利決定・災害)
長期的な材料(人口動態・技術革新・経済成長率)
著者は「短期的材料は短期的変動要因であり、
長期的トレンドを変えるものではない」とし、
「本質的な視野」を重視します。
8-6. 経済理論をベースにした「物差し」
相場観を持つ際、
「感覚」ではなく「理論に基づく物差し」を使うべき。
金利上昇 → 株価への影響
インフレ加速 → 通貨価値への影響
財政出動 → 景気循環への影響
これらを正しく理解し、
「どういう環境ではどういう資産が有利か」を判断する力。
著者はこれを「経済学で読み解く投資の本質」としています。
8-7. 自分の相場観を「記録」する
著者の実践的アドバイス:
✅ 相場について「自分なりの見通し」を毎月ノートに記録
✅ その見通しの的中率・誤差を後で自己検証
✅ 改善のサイクルを回す
「自分の相場観を育てる習慣」が、
ノイズに流されない強いメンタルを作るのです。
8-8. まとめ:「相場観を持てる投資家になる」
著者の結論:
✅ 相場観は「経済学的に正しい目線」で養う
✅ マクロとミクロ、長期と短期を使い分ける
✅ 情報を鵜呑みにせず自分で考える
「相場観があれば、世の中の出来事全てが
自分の投資判断の糧になる。」
この力こそ、「正しい投資家」になるための条件です。
第9章:実践者のケーススタディ ― 資産運用の成功例・失敗例
9-1. 実例に学ぶ重要性
著者・上念司氏はこう述べます。
「理論だけでは投資の実践力は養えない。
実際の成功例・失敗例から学ぶことが最も効果的。」
この章では「正しい投資」と「アブない投資」の具体的な実践例を
比較しながら解説していきます。
9-2. 成功例① 長期・分散・低コストの実践
著者が紹介する最も堅実な成功例:
✅ インデックスETFを毎月積立
✅ 米国市場を中心としたグローバル分散
✅ 購入手数料・信託報酬を徹底的に低コスト化
この投資家は「短期的な相場変動」に全く振り回されず、
20年以上にわたり資産を着実に増やしてきました。
特筆すべきは「相場急落時にも定額積立を続けたこと」。
この一貫した行動が「複利の雪だるま」を大きくした要因です。
9-3. 成功例② 配当金の再投資ループ
別の成功例は「高配当株・増配株」による戦略。
✅ 米国の配当貴族・連続増配企業を中心にポートフォリオ構築
✅ 配当収入をそのまま再投資
✅ 10年で「配当だけで生活費を賄えるレベル」に到達
この投資家の特徴は「複利効果を最大限活用」したこと。
生活費を削り、配当をひたすら再投資に回すことで
FIREを現実のものにした例です。
9-4. 失敗例① 情報に流される短期売買
著者が警告する典型的失敗例:
SNSで話題の銘柄に飛びつく
急騰急落のタイミングで売買を繰り返す
結果的に「高値掴み・底値売り」に終始
「短期売買で稼ぐ自信がなければやるべきでない」
という著者の原則に違反した行動が、
資産を減らす結果に繋がっています。
9-5. 失敗例② レバレッジ商品の過信
別の失敗例は「レバレッジ型ETF・CFD・FXなどの多用」。
短期間での高リターンを狙いすぎ
市場急落時に大きな含み損を抱え損切り
精神的ストレスで投資を継続できなくなる
著者は「レバレッジ商品はプロでも難しい」
と再三警告しており、
個人投資家の安易な利用に強い注意を促します。
9-6. 失敗例③ 「利確病」と「塩漬け」
著者が行動経済学的視点で分析する失敗パターン:
✅ 小さな利益で早々に売ってしまう(利確病)
✅ 含み損の銘柄を長期保有し続ける(塩漬け)
この非合理的行動こそ、
心理的バイアスの罠に陥った例です。
著者は「投資ルールの徹底と感情排除」で防げると強調します。
9-7. 成功例③ 生活防衛資金の重要性を理解した投資家
著者が賞賛する別の成功例:
✅ 投資額を「生活防衛資金を残した余裕資金」に限定
✅ 市場急落時も生活費への影響ゼロ
✅ 精神的余裕で淡々と積立を継続
「生活防衛資金の確保があるからこそ、
相場変動に耐える投資行動ができる」
これが著者の一貫した主張です。
9-8. まとめ:成功と失敗の分岐点
著者の結論はシンプルです。
✅ 成功者は「自分の投資ルールを持ち、それを守り続けた」
✅ 失敗者は「感情・ノイズ・欲望に流された」
つまり「正しい投資家」とは、
経済学的理論を理解した上で「行動を自己管理できる人」。
「成功例から学び、失敗例を反面教師とする」
これが個人投資家が実践すべき重要な姿勢です。
�� 以上が「第9章:実践者のケーススタディ ― 資産運用の成功例・失敗例」 です。
第10章:これからの投資 ― 未来への備え
10-1. 投資環境は常に変化する
著者・上念司氏は、投資家に次のように警告します。
「投資環境は決して一定ではない。
世界経済、技術、社会構造の変化を常に意識せよ。」
過去の成功体験に固執することは、
未来への適応を妨げ、
「アブない投資家」への道に他なりません。
10-2. テクノロジーの進化と投資
AI、ロボティクス、クラウド、バイオ、EV――
新しいテクノロジーは、
世界経済に変革をもたらし続けています。
✅ これらの成長分野を投資テーマとして取り入れる
✅ ただし「過熱感のある相場」には冷静に対処
著者は「未来の成長産業に分散して資産を置くことが、
中長期的に正しい投資行動」と述べています。
10-3. 気候変動とESG投資
著者は、気候変動が「規制・産業構造・エネルギーコスト」に影響を与えることを指摘。
ESG(環境・社会・ガバナンス)を意識した投資は、
もはや社会的意義だけではなく「経済合理性」もある時代。
✅ ESG対応の進んだ企業は中長期的に優位
✅ エネルギー転換関連企業への注目
著者は、盲目的な「流行り物投資」ではなく、
冷静な経済的視点からESGも判断材料に加えるべき としています。
10-4. 米中対立と多極化リスク
これからの世界は「米中二極」から「多極化」へ向かう可能性。
インド・ASEAN・アフリカなどの台頭
地政学的リスクの多発
著者は「今後は“国・地域の分散”がさらに重要」と述べ、
米国一極集中に過度に頼る投資からの脱却も検討課題としています。
10-5. 長寿化社会への対応
「人生100年時代」は、
投資家に「老後資金の更なる持続性」を求めます。
著者のメッセージ:
✅ 資産を「30年・40年単位で守り続ける視野」が必要
✅ 老後も「部分的に運用・配当収入でカバーする戦略」
これは単なる「FIRE後の引退生活」ではなく、
「資産とともに生き続ける知恵」が求められるということです。
10-6. 自律学習する投資家
未来への備えで最も重要なのは「学び続ける力」。
著者はこう断言します。
「正しい投資家は、変化に応じて自ら学び、行動を修正できる人。」
✅ 本質的な経済理論を理解する
✅ 流行に流されず「本当に成長する産業・国」を見極める
✅ 失敗を糧に「自分の投資ルール」をアップデートする
この「自律学習型投資家」こそが未来に勝てる投資家。
10-7. まとめ:「変化を恐れず、原理原則を貫く」
著者の最終メッセージ:
✅ 投資環境は今後も激しく変わる
✅ しかし「経済学的原理原則」は普遍
✅ 未来を予測するのではなく、変化に適応する投資家になる
「正しい投資家は、原理原則を軸に未来を見据え、
“変化を恐れず行動する人”である。」
あとがき
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
投資は「経済的自由を得るための手段」であると同時に、
インフレ・税負担・社会変化から「自分の資産を守る戦略」でもあります。
本書で学んだ知識と考え方を活用し、
短期的な利益を追い求めるのではなく、
自分らしい長期的資産形成をぜひ実践してください。
変化の激しい時代だからこそ、
「経済学的原理原則」を軸に、自分自身で考え行動できる
「強い個人投資家」を目指しましょう。





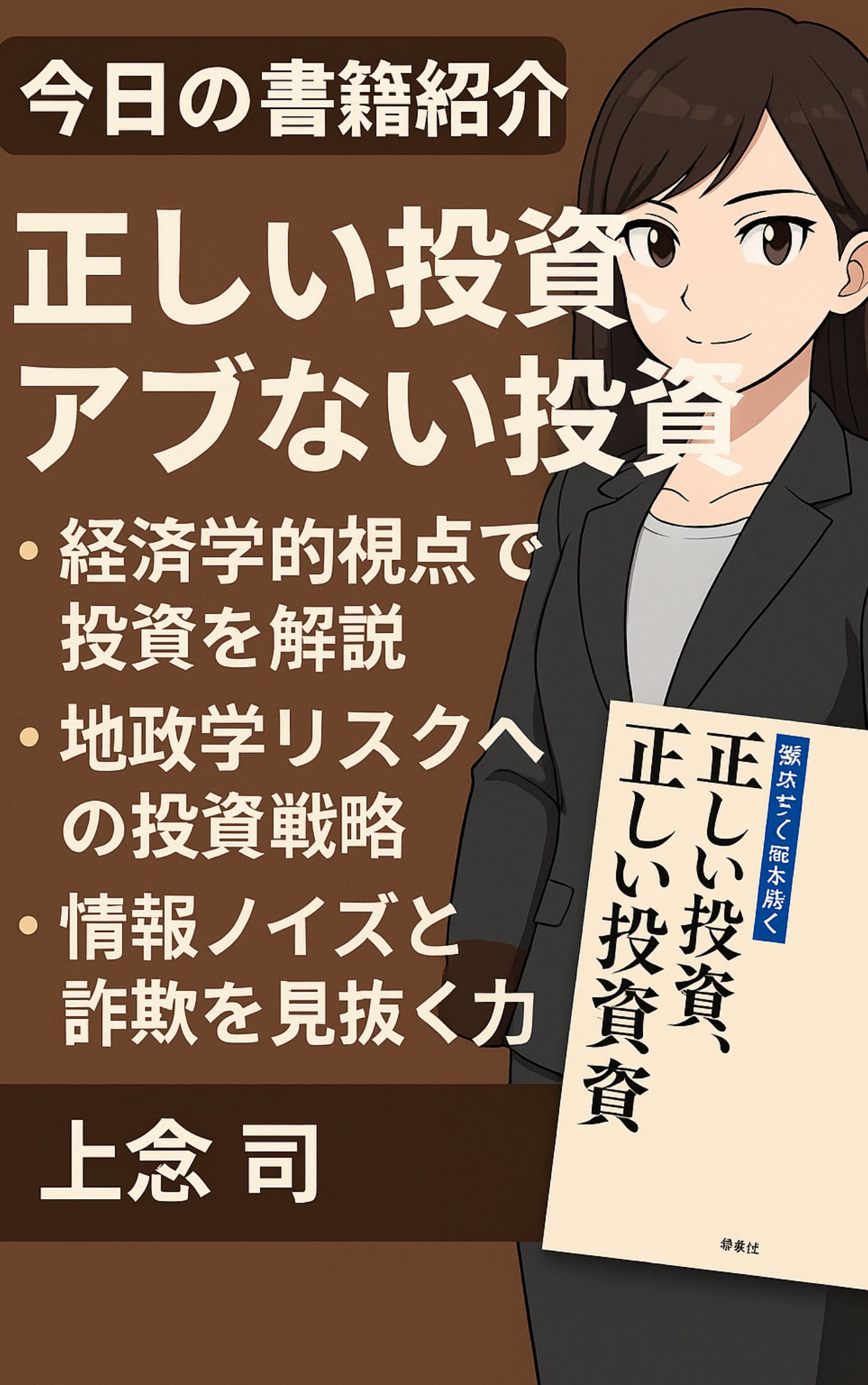
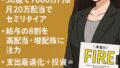

コメント