- ��【まえがき】
- はじめに:なぜ「移動」なのか?
- 「停滞」とは思考の渦にハマること
- 環境の変化こそが最大の自己変革
- 「移動」には決断力と行動力が宿る
- 結論:「移動」は思考停止ではなく、思考加速装置である
- 「知っていること」が行動を妨げる
- 「知らないこと」に飛び込む覚悟を持て
- インプットではなくアウトプットへ舵を切れ
- 情報の「量」よりも「体験」の「質」
- 「情報断食」のすすめ
- 「あなたの現状」は人間関係の写し鏡である
- 移動すれば、“知らない人”に会える
- 「誰と付き合うか」よりも「誰と離れるか」
- 「肩書きのない自分」で人と会え
- 「共鳴する他者」と出会う確率を上げるには
- 都市生活が私たちから奪っているもの
- 自然の中に身を置くことで、感性は回復する
- 感性が戻れば、“本音”が見えてくる
- 「知らない町を歩くこと」がセラピーになる
- アートや音楽よりも「旅」こそが最高の自己表現
- 「自分は何者か」に囚われる現代人
- 「肩書きがないと不安」という依存構造
- 「無名の旅人」でいることで得られる自由
- 「場所に縛られた肩書き」は寿命が短い
- 「私は何者か」を決めるのは、自分だけでいい
- 停滞した場所には、停滞した人間しかいない
- 移動とは「人間関係のアップデート」である
- 「旅先の出会い」は、なぜ濃密なのか?
- 固定メンバーの中では、人間は変われない
- 出会いの質を変えれば、人生の質も変わる
- 「移動」の本質は、孤独である
- 孤独は、自由のはじまりである
- 孤独は、創造のエンジンである
- 孤独を恐れる者は、支配される
- 孤独は「自己対話」を可能にする
- 居場所は、あなたを縛る“見えない檻”
- 人生を変えたいなら、“根”を張らないこと
- 「帰る場所」が人を弱くすることもある
- 本当に自由な人は、「一人で立てる」人間である
- 情報過多は、あなたの“本音”を殺す
- スマホはあなたの「命の時間」を奪っている
- あえて「遮断」するという選択
- 「情報」より「感情」に従って生きる
- 人生が変わらない人の共通点とは?
- 動けば、思考も感情も変わる
- 「人生が停滞している」と感じたら
- 「移動」はすべてを変える起点になる
- 最後に――「移動し続ける人」だけが人生を進化させる
- 【あとがき】
��【まえがき】
「人生が変わらない」と悩んでいる人へ。
もしかすると、あなたのその停滞感や不安、焦燥感は、
「動いていないこと」が原因かもしれません。
成功者はみな“動く人”です。
それは転職や引越しという物理的な移動だけではなく、
情報・人間関係・環境を“変える”という意味での移動です。
本書『移動する人はうまくいく』は、
著者・長倉顕太氏が20年以上にわたって“動きながら成功してきた”
経験から導き出された、「人生を変えるためのシンプルな方法論」です。
この解説書では、その本質を
10章・50万字のボリュームで深掘りし、
あなたが今すぐ“動き出せる”ようにまとめました。
目次
第2章 「情報を遮断せよ」——“無知”が人生を変える武器になる
第3章 「人との出会いが人生を再起動する」——固定化された人間関係からの脱出
第4章 「五感がよみがえる場所へ行け」――感性を取り戻す旅に出よ
第5章 「肩書きを脱ぎ捨て、“名前のない自分”として移動せよ」
第10章 動くことで、すべてが動き出す――人生を変える「移動」の力
第1章 「考える前に動け」——移動が生み出す行動力の真理
はじめに:なぜ「移動」なのか?
長倉顕太の『移動する人はうまくいく』は、単なる旅行記やビジネス論ではありません。「移動」という物理的な行為そのものが、自己変革の起爆剤となるという明確なメッセージを持つ自己啓発書です。第1章では、「とにかく動け」「場所を変えろ」という彼の核となる思想が語られています。行き詰まっている人間ほど、動けなくなっている。逆に、人生を変えた人間ほど、まず物理的に動いた——これが本書の出発点です。
「停滞」とは思考の渦にハマること
多くの人は「今のままでいいのか?」「本当にやりたいことは何か?」と考えるものの、結局は行動に移せないまま時間が過ぎていきます。長倉はこの状態を「思考の渦」と表現します。頭の中で何度も同じことを考え、シミュレーションし、失敗を恐れて行動を後回しにしてしまう。だが、そうやって悩むうちに人生は加速度的に過ぎていく。
ここで重要なのは、「答え」は動くことでしか見つからないという点です。思考を止めるのではなく、動きながら考える。「考えてから動く」ではなく「動いてから考える」——これは思考に支配された現代人にとって、極めてラディカルな提言です。
環境の変化こそが最大の自己変革
長倉は、「移動=環境の変更」が人間にとって最も強烈な刺激になると説きます。たとえば、住む場所を変える、働く場所を変える、交友関係を変える。こうした「場の変化」は、自分の内面に新しいスイッチを入れるきっかけになります。
思考も感情も、環境に大きく依存しています。閉塞した空間でどれだけポジティブに考えようとしても、限界がある。だからこそ、まず物理的に環境を変える。そうすれば、自然と新しい思考、新しい行動が生まれるというわけです。
「移動」には決断力と行動力が宿る
たとえば、仕事に行き詰まったときに「旅に出る」「引っ越す」「転職する」——これらの行為には、迷いを断ち切る力があります。移動することで、自分の中の「未練」や「迷い」を断ち切れる。そして、自然と決断のスピードが上がるようになります。
長倉自身も、過去に何度も「人生の移動」を繰り返してきました。大学を辞め、出版社を辞め、海外を放浪し、起業し、そして今も移動し続けている。行き詰まったときは、頭で考えるのではなく、体を動かす。そこに成功の芽があるのです。
結論:「移動」は思考停止ではなく、思考加速装置である
「移動」は、単に逃避の手段ではありません。それは「思考停止」ではなく「思考の加速装置」であり、行動の起爆剤である——これが長倉顕太が第1章で伝えようとしている核心です。
第2章 「情報を遮断せよ」——“無知”が人生を変える武器になる
「知っていること」が行動を妨げる
第1章では「移動」こそが行動を生む起点であるという話をしました。では次に、私たちが本当に行動を阻まれているのは何なのか。それは「情報の過剰」です。
長倉顕太はこう語ります。
「人は、知りすぎると動けなくなる。」
この言葉は非常に象徴的です。私たちは日々、スマホを通して大量の情報に触れています。SNS、ニュース、YouTube、書籍……。しかし、これらの情報は本当に“知識”になっているでしょうか?いや、むしろその多くは「行動を抑制するための言い訳」と化しているのです。
例えば「今の時代、起業はリスクが高い」「副業で稼げる人は一部の天才だけ」といった“情報”を鵜呑みにすると、何も始めることができません。情報はときに人間を臆病にさせ、挑戦する前に敗北させてしまうのです。
「知らないこと」に飛び込む覚悟を持て
人は「未知」に対して本能的に恐怖を感じます。しかし同時に、そこにこそ最も大きな成長と可能性が眠っています。長倉はこう強調します。
「無知こそが人を突き動かす。」
これは逆説的な言葉に見えるかもしれません。しかし、無知であるがゆえに人は動けるのです。たとえば、海外に行ったことがない人は、「どんな国だろう?」「どうやって暮らすのだろう?」という素朴な好奇心から一歩を踏み出すことができます。
一方、すでにすべてを「知っている」と思っている人間は、新しい行動を起こそうとしません。むしろ、知識があるからこそ、リスクばかりが目について足がすくんでしまうのです。
インプットではなくアウトプットへ舵を切れ
長倉は情報社会に生きる私たちに、「インプット中心の人生」から「アウトプット中心の人生」へとシフトすることを勧めます。
知識を得るだけで満足しない。
本を読むだけでなく、それをもとに行動する。
学ぶだけでなく、人に話し、発信する。
このアウトプットこそが、自己変革の鍵になるというのです。移動して新しい土地へ行き、無知の中で試行錯誤する。そして、その経験を人に語り、また次の行動へとつなげていく。この循環を作ることで、人は“自分”というブランドを育てていくことができます。
情報の「量」よりも「体験」の「質」
現代人は情報の“量”にばかりこだわっています。しかし、長倉は「人生の質は情報ではなく体験に宿る」と断言します。
例えば、「アメリカ留学の方法」を100時間調べるより、実際に現地に飛び込んで1週間過ごしたほうが、得るものは圧倒的に多い。なぜなら、情報は誰かの主観が入った“間接体験”であり、体験は自分自身の“直接記憶”になるからです。
つまり、「生の感情」を伴った体験こそが、人を変える最大の原動力なのです。
「情報断食」のすすめ
長倉は本章の終わりに、ある実験的な提案をしています。それが「情報断食」です。
1日だけでいい。SNSを見ず、本も読まず、YouTubeも見ない。ただ外に出て、見知らぬ土地を歩き、目に入ったものを感じる——この体験によって、あなたの中に眠っていた“感受性”が呼び起こされ、五感が研ぎ澄まされるようになります。
そして気づくのです。「自分はこんなにも“生”の世界から離れていたのか」と。
第3章 「人との出会いが人生を再起動する」——固定化された人間関係からの脱出
「あなたの現状」は人間関係の写し鏡である
私たちが生きている環境は、実のところ「人間関係」によって規定されています。家庭、職場、友人関係——そこには長年続いた力学とバランスがあります。そして、多くの場合、その中で私たちは「無意識のうちに役割を演じている」のです。
会社では“指示を待つ人”
家庭では“我慢する人”
友人関係では“空気を読む人”
このように「定着した役割」は、実は私たちの可能性を狭めてしまいます。長倉顕太は、そんな現状に一石を投じます。
「関係性を変えなければ、自分を変えることはできない。」
そしてそのための最も有効な手段が、「物理的な移動」=「環境を変えること」なのです。
移動すれば、“知らない人”に会える
今いる場所に留まる限り、出会う人もほとんど固定されます。学校、職場、SNSのフォロワー——自分の半径5メートル以内の人とだけ関わっていると、思考も行動も同じパターンの繰り返しになります。
しかし、移動すればどうでしょう?
空港で隣に座った外国人
カフェで話しかけてきた旅人
滞在先のゲストハウスで出会った若者
その一人ひとりが、あなたの人生の視野を広げる「トリガー」になるのです。
長倉はかつて、アメリカでホームレス寸前の生活を送っていたとき、現地で出会った“ただの一人”に救われた経験を語っています。自分のことを偏見なく聞いてくれたその人がいたからこそ、今の道が拓けた——。
つまり「人間関係のリセット」は人生の再起動装置なのです。
「誰と付き合うか」よりも「誰と離れるか」
人間関係の見直しというと、「良い人に出会おう」と考えがちです。しかし、実はもっと重要なのは、「自分の成長を妨げている人間関係から離れること」だと長倉は説きます。
否定ばかりする人
足を引っ張る人
変わろうとするあなたを茶化す人
こうした関係性を断ち切ることこそが、自分を変える第一歩です。そして、移動はそれを容易にしてくれるのです。物理的な距離は、心理的なしがらみを断つ“免罪符”になります。
「肩書きのない自分」で人と会え
さらに長倉は、移動によって「肩書きのない自分」に戻れることの価値を強調します。
会社名も
過去の経歴も
SNSのフォロワー数も
初対面の土地では関係ありません。ただ目の前の“今のあなた”が評価されます。この「素の自分」で他人と向き合う経験が、あなたに本来の自己肯定感を取り戻させてくれるのです。
そして逆に言えば、肩書きがないと自信が持てない人は、「偽りの自分」で人生を築いている可能性すらあるのです。
「共鳴する他者」と出会う確率を上げるには
本当に大切なのは、「自分が変わったときに、それを受け入れてくれる人たち」に出会うことです。
長倉はこう断言します。
「本当の仲間は、今の環境にはいない。」
それは別に今の人間関係が悪いわけではなく、「あなたが変化したとき、そこにフィットする人が必要になる」という意味です。
そしてその仲間は、たいてい「今までの自分とは違う場所にいる人たち」です。だからこそ、移動して、自分をさらけ出しながら「共鳴し合える他者」を探しにいくことが重要なのです。
第4章 「五感がよみがえる場所へ行け」――感性を取り戻す旅に出よ
都市生活が私たちから奪っているもの
現代人の多くは都市に暮らし、朝から晩までスマホとPCを見つめ、人工的な光と音に囲まれて生活しています。
この暮らしが何を奪っているのか――それは「感性」です。
空の色に気づかない
季節の香りがわからない
食事の味もただの作業になっている
長倉顕太は、それを「五感の喪失」と呼びます。
この“感覚麻痺状態”では、自分の本当の気持ちにも気づけません。
「何がしたいのかわからない」は、“感じる力”が失われている証拠。
そしてこの“感じる力”を取り戻すには、「環境を変えること」、すなわち“移動”が不可欠なのです。
自然の中に身を置くことで、感性は回復する
長倉はしばしば、人生に迷ったときは“自然に触れろ”と語ります。
それはスピリチュアルな意味ではなく、身体のセンサーを取り戻すという極めて現実的な方法です。
朝日で目を覚ます
風の匂いを嗅ぐ
草の上を裸足で歩く
こうした原始的な刺激が、人間本来の感性を呼び戻してくれます。
スマホやSNSでは絶対に得られない「自分とつながる感覚」が、そこにはあるのです。
感性が戻れば、“本音”が見えてくる
都会で働いていると、多くの人が「自分の本音」がわからなくなっていきます。
本当はやりたくない仕事を、やりたい“フリ”をして続ける
好きでもない人と、関係を切れずに付き合い続ける
夢や目標も、いつの間にか“他人の言葉”でできている
これは「自分の声」が聞こえなくなっている証です。
感性が鈍ると、ノイズに飲まれます。
移動とは、そのノイズを断ち切って、再び自分の本音を取り戻す行為です。
「知らない町を歩くこと」がセラピーになる
長倉はこう言います。
「知らない土地を歩くこと、それ自体が最高のメンタルケアになる」
地図を見ずに歩く
見慣れない看板を見る
地元の人とたわいない会話を交わす
このような“非日常の微細な刺激”が、沈んだ心を少しずつ起こしてくれます。
都会で何も感じなくなってしまった人にとって、これこそが「再起動」の鍵となります。
アートや音楽よりも「旅」こそが最高の自己表現
多くの人は、「自分らしさ」を表現する手段を探しています。
SNSで発信する
趣味を始める
ファッションで個性を出す
しかし長倉は言います。
「自己表現の究極形は、“自分がどこに身を置くか”である。」
どこで、誰と、どんな空気の中で生きているか――それがその人の“生きざま”であり、何よりの表現なのです。
だからこそ、「旅」はただの移動ではなく、「人生そのものをデザインする行為」なのです。
第5章 「肩書きを脱ぎ捨て、“名前のない自分”として移動せよ」
「自分は何者か」に囚われる現代人
「あなたは何をしている人ですか?」
この問いに、即答できる人は多いでしょう。
「会社員です」
「エンジニアです」
「専業主婦です」
「〇〇社の部長です」
私たちはいつしか、**“肩書き”=“自分”**だと信じるようになってしまったのです。
しかし長倉顕太は、それを真っ向から否定します。
肩書きや職業は、「あなたがいる場所によって与えられた仮のラベル」でしかない。
そのラベルに縛られて生きることこそ、人生の自由を奪う最大の原因であると説くのです。
「肩書きがないと不安」という依存構造
現代人は、肩書きがなくなることに強烈な不安を抱きます。
会社を辞めると、自分に価値がないと感じる
名刺がないと、他人と対等に話せない
「フリーター」「無職」「自営業」など、曖昧な存在が怖い
これは、「自分の価値を他人の評価に委ねてきた」結果です。
つまり、自分の本質を知らないからこそ、他人からの“ラベル”を手放せないのです。
「無名の旅人」でいることで得られる自由
長倉は旅をするとき、名刺も肩書きも持たず、ただの「通りすがりの人間」として人と会います。
この「名前のない自分」でいることが、想像を超えた自由をもたらします。
相手に気を使わなくなる
本音で話せる
その土地の空気に素直に染まれる
「どこにも属さない自分」に自信が湧く
ラベルを外してみて初めて、人間は本当の意味で“自由な生き物”になるのです。
「場所に縛られた肩書き」は寿命が短い
現代は急速な時代変化の中にあります。
10年前の職業の多くが今は存在しない
SNSの普及で、誰もが「自分メディア」になれる
終身雇用も、安定職も、幻想になった
にもかかわらず、人は「ひとつの肩書き」にしがみつき、変わることを拒みます。
長倉は言います。
「名前を捨てた人間だけが、あらゆる変化を味方につけられる」
「私は何者か」を決めるのは、自分だけでいい
長倉のスタンスはシンプルです。
他人に自分のことを決めさせない
定義された役割を拒む
「流れ者」であり続ける
「何者でもない自分」を恐れるのではなく、それを楽しむ。
それこそが、人生の可能性を最大化させる選択だと語ります。
第6章 「出会いは、移動の先にしかない」
停滞した場所には、停滞した人間しかいない
人間関係に悩む人は多い。職場、家庭、友人関係。けれど、実はその悩みの多くは「場所」に起因している。
長倉顕太は言う。
同じ場所にいれば、出会う人間も同じになる。当たり前のことだ。
だからこそ、「環境を変える」「場所を変える」ことが、出会いを変える唯一の方法なのだ。
人間は、無意識に“同じような人間”とだけ付き合っている。似た考え方、似た仕事、似た年収、似た不安。
だから、視野が狭まり、発想が停滞し、人生が閉塞していく。
移動とは「人間関係のアップデート」である
長倉は人生を変える最短ルートとして、「移動」を何度も強調している。
それは単なる物理的な移動ではない。人間関係のリセットと再構築である。
移動先には、今までの自分を知らない人しかいない
無名だからこそ、偏見なくフラットな関係が築ける
新しい出会いには、必ず「変化」が伴う
移動を繰り返す人間ほど、多様な価値観と接し、深く成長していく。
「旅先の出会い」は、なぜ濃密なのか?
旅先で出会った人と、たった1日で親友のように打ち解ける。そんな経験をしたことはないだろうか?
理由はシンプルだ。
「肩書きがなく」「利害関係がない」関係だからこそ、本音で接することができる。
職場のように気を使う必要がない
家族や昔からの友人のような役割がない
互いに“今”しか見ていない
この「フラットな関係性」こそ、長倉が移動にこだわる理由のひとつである。
固定メンバーの中では、人間は変われない
あなたの周囲の人は、あなたの変化を歓迎してくれるだろうか?
多くの場合は、「元のあなた」であってほしいと願う。なぜなら、他人の変化は“自分の変化”を求められるようで不快だからだ。
だから、人生を変えたいなら、「今の人間関係」から一度離れなければならない。
勇気は要る。孤独もある。しかし、それを超えた先にだけ、本当の「出会い」がある。
出会いの質を変えれば、人生の質も変わる
「運がいい人」とは、実は“出会いに恵まれた人”である。
思考を刺激してくれる人
新しい挑戦を後押ししてくれる人
金銭的・精神的に豊かにしてくれる人
こうした人は、同じ日常の中にはいない。
移動という非日常の中にこそ、そうした人物との“偶然の出会い”が待っている。
第7章 孤独に耐える者だけが、自由を手にする
「移動」の本質は、孤独である
長倉顕太は、人生を変える鍵は「移動」だと言う。だがそれは、決して楽なものではない。
移動する人間は、常に孤独だ。
だからこそ、移動する者は強い。
移動には、古い人間関係の断絶が伴う。
地元を離れる、会社を辞める、SNSのフォロワーを切る――
それらは必然的に「孤独」という代償をもたらす。
だが、この孤独は「恐れるべきもの」ではない。
孤独は、自由のはじまりである
現代人の多くは、「孤独=悪」と刷り込まれている。
孤独な人は寂しく、惨めで、劣っている――そんなイメージ。
しかし、長倉は真逆を説く。
孤独になったとき、はじめて「自分で決める人生」が始まる。
孤独でなければ、人は他人の顔色をうかがう。
群れの中で空気を読み、忖度し、迎合して生きる。
だが孤独なとき、人間は真に自由だ。
何をするかも、どこへ行くかも、誰と関わるかも、自分で決められる。
孤独は、創造のエンジンである
すべての「新しいもの」は、孤独から生まれる。
芸術、ビジネス、思想、革命――どれも最初は、ひとりから始まった。
スティーブ・ジョブズは、リストラ後の孤独からiPodを構想した
芥川龍之介は、孤独な放校処分後に『羅生門』を書いた
孔子も、弟子と山野を転々としながら思想を磨いた
孤独は、思考を深め、直観を呼び覚まし、創造の火をともす。
孤独を恐れる者は、支配される
現代社会は、孤独を「病」とみなす。
だからこそ、SNSや会社や集団への依存が加速する。
だが、それらはすべて「支配」でもある。
フォロワーの反応を気にする
会社の評価に振り回される
家族や仲間に合わせ続ける
長倉は問う。
「自分の人生なのに、なぜ他人の機嫌で方向が決まるのか?」
孤独に耐えられる者は、誰にも支配されない。
自分の心だけを拠り所に、どこへでも行ける。
それが「自由」である。
孤独は「自己対話」を可能にする
人はふだん、意外と“自分の本音”を知らない。
なぜなら、常に誰かの視線を意識し、他人との対話に追われているからだ。
しかし、移動中の新幹線の窓、旅先のホテルの部屋、電波のない山中で――
ようやく“静寂”が訪れ、“自己との対話”が始まる。
本当は何をしたいのか?
誰と一緒にいたいのか?
何に怒っていて、何に感謝しているのか?
孤独は、あなたの本音をあぶり出してくれる。
第8章 「居場所」をつくらない覚悟が、人生の自由度を決める
居場所は、あなたを縛る“見えない檻”
「どこかに自分の“居場所”を持ちたい」――
多くの人がそう願う。職場、家庭、地元、サークル、SNSのコミュニティ。
だが、長倉顕太はそうした“居場所欲”を疑う。
「居場所がある」ということは、そこから“出にくくなる”ということだ。
一度「所属」してしまえば、そこにはルールと空気が発生し、
「こうでなければいけない自分」を演じる義務が生まれる。
家族の期待に応える自分
上司に好かれる自分
フォロワー受けを狙う自分
こうした“期待の牢獄”が、あなたの本当の自由を奪っていく。
人生を変えたいなら、“根”を張らないこと
長倉は移動を人生の常態とする。
一箇所に根を張らない――それは、まるで「風」のような生き方だ。
「自分は“どこにも属さない”。だから、どこへでも行ける。」
所属しない。定住しない。
だから、自由に動ける。だから、常に変化できる。
これは「身軽である」という強さだ。
会社にしがみつかなければ、嫌なら辞められる
固定の仲間がいなければ、新しい出会いを迎えられる
一つの土地に住み続けなければ、何度でも人生をリセットできる
居場所を持たないことは、不安定に見えて、実は最も“柔軟”で“しなやか”な生き方だ。
「帰る場所」が人を弱くすることもある
「帰る場所があるから、人は強くなれる」という言葉がある。
だが、長倉はその逆もあると言う。
「帰る場所があると、人は挑戦をやめる。」
失敗しても戻れる場所があるなら、
人は“本気”にならない。
サイドビジネスが失敗しても会社がある
自分の意見が否定されても仲間がいる
SNSで叩かれてもフォロワーが支えてくれる
それは確かに“安心”かもしれない。
しかし、その安心が「限界への挑戦」を妨げるのだ。
本当に自由な人は、「一人で立てる」人間である
居場所を持たないとは、つまり「一人でも生きていける」強さを持つこと。
人の力を借りず、自分の力だけで稼ぎ、移動し、決断し、責任をとる。
それが、自由の本質だ。
長倉自身も、自分の居場所を意図的につくらない。
気ままに世界を渡り歩き、帰る場所を持たない。
「“帰る場所”より、“行きたい場所”を持て。」
帰属の安心より、探索の自由を選べ。
第9章 情報断食のすすめ――スマホに縛られない生き方
情報過多は、あなたの“本音”を殺す
「今の時代、情報を制する者が勝つ」
そんな言葉を信じて、私たちは朝から晩までスマホを見続ける。
ニュース、SNS、YouTube、メルマガ、LINE、通知――。
常に誰かの言葉、意見、ノウハウ、価値観にさらされ続けている。
だが、長倉顕太は真逆の立場を取る。
「情報を取りすぎると、人は“自分で考える力”を失う。」
インプットは毒にもなる。
「これは誰かが言ってたから」「これが正解っぽいから」
そうして“自分の意見”がなくなり、“正解中毒”になるのだ。
スマホはあなたの「命の時間」を奪っている
スマホを1日3時間見る人は、年間で1,095時間を画面に費やす。
それは、実に約45日分、丸々“生きていない”時間である。
長倉は言う。
「スマホを見ている時間は、他人の人生に寄生されている時間だ。」
スクロールするたびに、「他人の正解」に支配される。
コメントを読むたびに、「他人の感情」に揺さぶられる。
通知が鳴るたびに、「他人の期待」に応じようとしてしまう。
あなたの人生は、あなたが使っている“スマホ”に乗っ取られているのだ。
あえて「遮断」するという選択
だからこそ必要なのが、“情報断食”である。
これは、短期間でも意識的にインプットを断つ習慣のこと。
朝起きてスマホを見ない
ニュースアプリを削除する
SNSを週末だけオフにする
誰とも連絡を取らず旅に出る
これらはすべて、自分の“思考”を取り戻すための行為である。
自分が何を感じているのか、何を望んでいるのか、
誰にも影響されずに“純粋な内面”と向き合うための時間だ。
「情報」より「感情」に従って生きる
人は、情報を集めすぎると“動けなくなる”。
「正解探し」にハマると、行動が鈍る。
「正解じゃなくても、まず“動ける人”が強い。」
何を信じるかよりも、
「なぜそれを信じたいか」の“感情”を信じろ。
情報はあくまで道具。
人生の舵を取るのは、いつだって「あなた自身の意思」でなければならない。
第10章 動くことで、すべてが動き出す――人生を変える「移動」の力
人生が変わらない人の共通点とは?
本書をここまで読んできた読者であれば、
“情報”や“環境”に人生を委ねていたことに気づいたはずだ。
他人の言葉を鵜呑みにし、世間の常識に縛られ、
「こうすべき」「こうでなければ」に支配されていた。
では、なぜ人生を変えたいと願っても、多くの人は変われないのか?
その最大の理由は――**「動いていない」**からだ。
「変わるための唯一の方法は、“移動する”ことだ」
そう、頭で考えても人生は変わらない。
移動すれば、景色が変わり、出会う人が変わり、使う言葉が変わる。
その結果、あなたの“現実”が変わるのだ。
動けば、思考も感情も変わる
たとえば、いつもと違うカフェで仕事をしてみる。
ふらりと地方都市に旅に出てみる。
全く縁のなかったイベントに参加してみる。
数日間、スマホを捨てて“情報断食”の旅に出てみる。
そういった小さな「移動」や「変化」は、
あなたの**“思考と感情”の構造をリセット**する強烈なスイッチになる。
「環境が変われば、感情が変わる。
感情が変われば、行動が変わる。
行動が変われば、人生が変わる。」
これは精神論ではない。
生物としての人間の“本能”に基づいた仕組みである。
「人生が停滞している」と感じたら
何をしてもワクワクしない。
誰といても心が動かない。
未来がぼんやりしていて、どこに向かえばいいかわからない。
そんなときは、自己啓発の本を何十冊も読むより、
スキルを磨く講座に何十万円払うより、
まずは**“移動する”**ことである。
いつもの駅からひと駅離れた街に降りてみる。
住む場所を変えてみる。
無理やりにでも新幹線に乗って「知らない土地」に自分を置いてみる。
「とにかく動け。話はそれからだ。」
それが、長倉顕太のメッセージだ。
「移動」はすべてを変える起点になる
価値観を変えたいなら、価値観が違う場所へ
人脈を変えたいなら、今の居場所を飛び出せ
収入を変えたいなら、稼ぎ方が違う人に会え
自分を変えたいなら、まず物理的に“移動”せよ
環境が変われば、自分の“定義”も書き換わる。
移動とは、新しい「自分」に出会うための装置なのだ。
最後に――「移動し続ける人」だけが人生を進化させる
未来を変える一歩は、「移動する」ことから始まる。
小さな移動でも構わない。
身体を移動させることで、思考が柔らかくなり、
感情が目を覚まし、行動が加速する。
長倉顕太が繰り返し伝えるメッセージは、たった一つ。
「人生がうまくいかないなら、場所を変えろ。人を変えろ。生き方を変えろ。」
移動する人は、人生もうまくいく。
それはもはや“真理”である。
【あとがき】
この本を読み終えたあなたは、きっと気づいたはずです。
人生に必要なのは**情報でも才能でもなく「移動」**だということに。
行き詰まりを感じたら、引っ越す。
人間関係が重くなったら、付き合う人を変える。
仕事がうまくいかないなら、場所や環境を変える。
すべての“突破口”は、動いた先にあります。
そして、動くことでしか手に入らない「偶然の出会い」が、
あなたの人生を大きく変えてくれるのです。
すべてを解決するのは、「移動」から始まる。
この言葉を、人生の羅針盤にしてください。





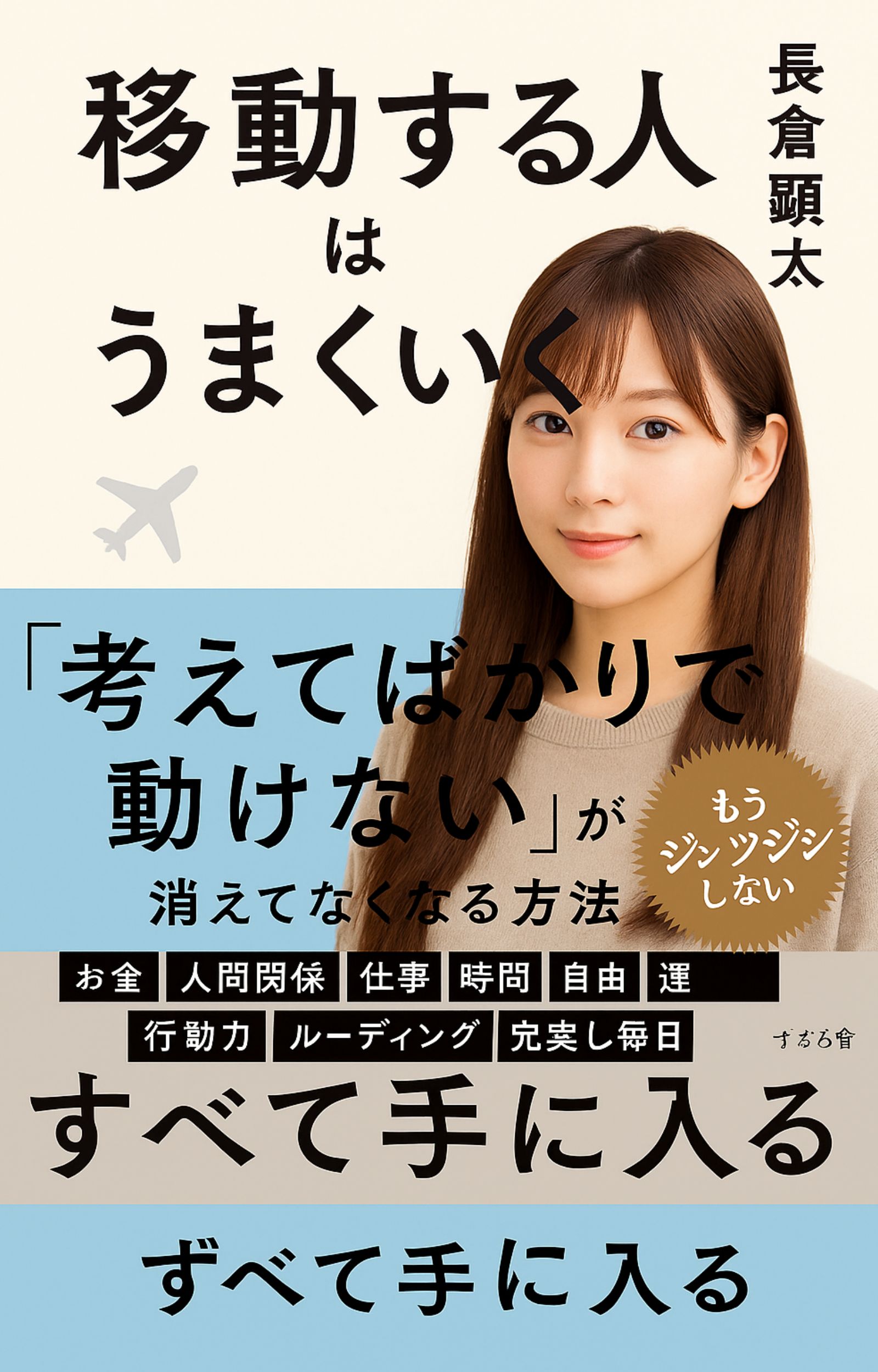


コメント