第1章 資産8,000万円時代の現実と錯覚 ― 社畜の戦略マップ
「8,000万円」。
この数字を聞くと、多くの人は「十分だ」と思うかもしれない。
だが実際には、それは**“防衛ライン”**にすぎない。
年金、物価上昇、税制改正。
資本主義社会では、富は静止しない。
今日の8,000万円は、10年後には6,000万円の価値になる。
それを理解しているかどうかで、人生の後半戦は分かれる。
2025年10月。
筆者の総資産は 8,040万2,948円。
構成は以下の通りだ。
不動産:4,820万円(11室・月CF34万円)
年金:1,955万円
預金・暗号資産:674万円
株式:588万円
表面的には安定している。
しかし、このバランスには**「脆弱性」と「再現性」**が同居している。
🔸資産ポートフォリオは“生態系”である
資産運用は、単なる数字の管理ではない。
それは「経済的エコシステム(生態系)」の設計だ。
株が成長期の“光合成”を担い、
不動産が“根”として安定を支える。
そしてキャッシュは“水分”だ。
どれか一つが枯れれば、全体は一瞬で崩れる。
筆者はこのエコシステムを、「社畜資本主義モデル」と呼んでいる。
平日は労働による安定キャッシュフロー、
休日は不動産・株式・インデックスの“副脳”が稼働する。
人が眠っている間に、資産は動く。
この「24時間稼働の構造」が、現代社畜の真の防衛だ。
第2章 IGLDとJEPQ ― 配当再投資がつくる複利の帝国
「キャピタル」と「インカム」。
多くの投資家はどちらかに偏る。
だが、長期的に富を築くのは両方を兼ね備えた戦略だ。
💰IGLD ― インカムの守護神
IGLD(First Trust International Equity Dividend Leaders ETF)。
利回りは年 11.5%。
筆者は現在 1,000株(25.53ドル取得) を保有。
直近の評価損益は −12,330円。
だが、インカム狙いであれば短期の含み損はノイズだ。
配当金は、税引前で年間 61万6,240円。
この金の流れが、時間とともに“第二の給料”を形成する。
IGLDは、米国・欧州・アジアの高配当銘柄を均等に組み入れる構成。
つまり、単一リスクを避けながらグローバルな利回り分散ができる。
ポイントは、「分配を再投資しない」という意思決定だ。
インカムを生活キャッシュフローに組み込み、
“消費する複利”を回す。
トマ・ピケティのr>gの論理に沿えば、
労働所得(g)よりも資本収益(r)を増やすことが重要。
IGLDはまさにその“r”の代表格である。
📈JEPQ ― キャピタルとインカムの中間地帯
一方、JEPQ(JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)はAI時代の新配当銘柄。
ナスダック銘柄にカバードコール戦略を組み合わせ、
高配当(10%前後)と値上がり益の両立を狙う。
IGLDが「守りの資産」なら、JEPQは「攻めの配当」。
筆者は現在、暴落待ちで買い増し予定。
戦略上、IGLD900株+JEPQ900株を最適バランスと見ている。
米市場ではインフレ鈍化が進み、
金利低下と共にカバードコール型ETFへの資金流入が再加速している。
JEPQの強みは、「キャピタルを諦めないインカム投資」。
このハイブリッド構造が、2020年代後半の主流となるだろう。
第3章 不動産11室とアパート1棟計画 ― “見えないキャッシュフロー”の力
筆者の最大の武器は、11室から生まれる 月34万円のキャッシュフロー だ。
サラリーマン給与とは無関係に流れるこの“地下水”が、人生を支える。
🏢キャッシュフローとは「現金の呼吸」
家賃は入金される。
ローン、管理費、修繕、固定資産税が出ていく。
この流れの残余が、実質的な自由を作る。
たとえば、今後予定しているアパート買い替えでは、
自宅売却益 +800万円 とキャッシュ 1,200万円 を合わせた 2,000万円 投入で、
月CFを 34万円→50万円 に引き上げる。
資産拡大の本質は、金額ではなく「現金流量の最大化」。
r>gの“r”を最も安定的に高めるのが、不動産なのだ。
💡不動産は「心の安定剤」
株式市場が乱高下しても、
不動産の入金は変わらない。
このメンタル安定効果は、金額以上に価値がある。
社畜が資本主義を生き抜くには、
メンタル資本こそ最重要。
「心が折れない設計」が不動産の真の意味である。
第4章 市場の混沌とチャンス ― 日本株・金利・為替の相互作用
2025年10月20日、
日経平均先物は 48,295円(+745円)。
ドル円は 150.62円。
NYダウは +238ドル。
そしてビットコインは +1.68% 上昇中。
📊日本市場の構造変化
金利は1.62%、VIX指数は20.78(−4.53)。
恐怖が減り、リスクマネーが戻り始めている。
だが、本質的な変化は「個人投資家の復権」だ。
NISA改正以降、個人の配当・再投資構造が日本市場を押し上げている。
これは「社畜の反乱」であり、金融民主化の始まりである。
今後、IGLD・JEPQのようなインカム重視ETFと、
ソニーFGのような金融優良株が柱となる。
💴ソニーFG(8729)― 日本のキャピタル代表
筆者は 1万株保有。
前日比+18,000円(+1.18%)。
配当利回り2.9%。
だが本命は配当ではなく、金融テック構想による中期キャピタル。
国内保険・銀行・証券の統合モデルとして、
今後AI・資産運用・個人金融の主役になる可能性が高い。
日本版バークシャー・ハサウェイになれるのは、
この銘柄以外にない。
第5章 社畜の哲学 ― 働かないおじさんとピケティと橘玲
最後に、哲学の話をしよう。
「r>g」というピケティの公式は、
橘玲の『お金持ちになれる人』の思想と共鳴する。
つまり、「労働で得られる幸福よりも、資本で自由を得る幸福」を目指すということだ。
社畜は努力の象徴ではあるが、
現代では“構造的搾取”の最前線でもある。
そこから抜け出すには、仕組みと距離感を持つことだ。
🌐働かないおじさんは、資本主義を生き抜いている
彼らは「会社からの疎外」を逆手に取り、
時間を支配している。
無能ではなく、むしろ制度を読んだ生存者だ。
彼らの真似をする必要はないが、
彼らの距離感から学ぶことはできる。
“働かない”とは“依存しない”ということ。
🧠最後に ― 資本主義の戦場で生きる者たちへ
人間関係は最大のリスク。
株も不動産もリスクは限定できるが、
人間だけは予測不可能だ。
だからこそ、
自分自身を司令塔に据える。
資本の群れをコントロールし、
市場のノイズを見下ろす。
誰も助けてくれない。
だが、資本は嘘をつかない。
それが、社畜が見つけた唯一の真実だ。
💡結論:
今、買うべきなのは――
IGLD(配当複利の基礎)とソニーFG(成長の中核)。
JEPQは押し目で。
そして何より、自分の思考と時間を資産化せよ。(了)





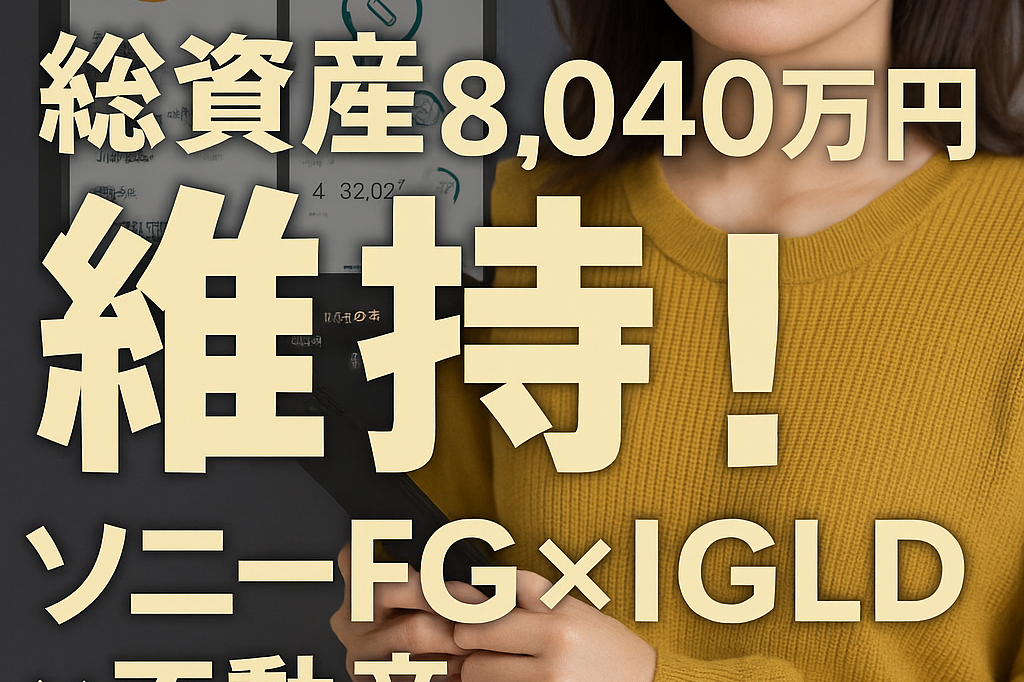

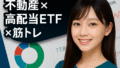
コメント