●まえがき
本書『糖尿病は、体にいいはずの油が原因だった』の解説は、単なる食事法の紹介にとどまらず、現代の医療、栄養教育、行政指導、そして家庭生活の根幹にまで深く関わるテーマを扱っています。
「糖のとりすぎが糖尿病の原因」という従来の常識を覆し、奥山治美氏は「本当に危険なのは質の悪い油である」と力強く訴えています。
本書ではその視点を10章構成で丁寧に掘り下げ、読者が日々の選択によって自分と家族の健康を守る力を取り戻せるよう構成しました。
今こそ、情報に流されるのではなく、自分で選び、自分で守るという「健康の主権者」としての覚醒が求められているのです。
目次
【第1章:糖尿病の常識が覆るとき――「糖」の犯人探しから「油」への視点転換】
第4章:「健康食品」という名の加速装置 〜その油があなたを蝕む〜
■4. 「小麦」「グルテン」「砂糖」ではなく「油」が主犯だった
高温加熱(揚げ物・炒め物)には動物性脂肪 or ココナッツオイルが適している
非加熱(和え物・後がけ)にはえごま油・亜麻仁油などのオメガ3を
リノール酸の摂取を意識的に減らす(できるだけゼロに近づける)
加熱に強い安定した脂肪を調理に用いる(ラード・ギー・ココナッツオイルなど)
「植物油脂」「加工油脂」「ショートニング」と記載された商品は避ける
「トランス脂肪酸ゼロ」表示でも油の種類を確認する(完全ではない)
「コレステロール0」は意味がない表示(植物油には最初から含まれない)
リノール酸の過剰摂取によるインスリン抵抗性への影響が無視されている
トランス脂肪酸の害には触れるが、酸化リノール酸には言及しない
製薬業界は“高コレステロール”を病気にし、スタチン等の薬を普及させた
■1. 65歳男性の逆転劇:HbA1cが8.2 → 5.8へ
■1. 家庭が変われば、社会が変わる:キッチンから始まる革命
- 【第1章:糖尿病の常識が覆るとき――「糖」の犯人探しから「油」への視点転換】
- 第2章:植物油が引き起こす代謝の異常と糖尿病のメカニズム
- ●まとめ:植物油は「善玉」ではなかった
- 第4章:「健康食品」という名の加速装置 〜その油があなたを蝕む〜
- ●まとめ:健康を求める人ほど“見えない罠”にかかっている
- 第5章:「“摂るべき油”の選び方と実践」
- 第6章:冷蔵庫から糖尿病を追い出す
- ●まとめ:日常の風景を変えることが、体質を変える
- 第7章:医学と栄養学が見落としてきた油の真実
- 第8章:油を変えて人生が変わった人々
- 第9章:なぜ“油が原因”という情報が広まらないのか
- 第10章:健康を取り戻すための“油革命”
- 最終結論:油を変えれば、人生が変わる。
【第1章:糖尿病の常識が覆るとき――「糖」の犯人探しから「油」への視点転換】
これまでの糖尿病治療や予防の常識は、ほぼすべて「糖質=悪」という前提に基づいて構築されてきた。甘いもの、炭水化物、白米、パン、ケーキ、ジュース――糖尿病の原因とされてきた食品はどれも「糖質」を多く含むものばかりである。そのため、医師の指導でも、栄養士の指導でも、糖質制限が第一に挙げられ、多くの患者たちは甘いものを我慢し、炭水化物の摂取量を減らし、食生活を律してきた。
だが、本書『糖尿病は、体にいいはずの油が原因だった』の冒頭で著者・奥山治美は、こうした常識に鋭い疑問を突きつける。果たして本当に「糖質だけ」が糖尿病の元凶なのか? 著者が注目するのは、「植物油」と呼ばれる油の摂取量の急激な増加である。
近年、日本人の糖質摂取量は減少傾向にある。特に意識の高い層は、白米より玄米を選び、ジュースよりも無糖のお茶や水を選ぶようになってきた。ところが、糖尿病の患者数は減るどころか、むしろ増加している。これは一体どういうことなのか? その答えとして提示されるのが、「油の質」なのである。
著者が問題視するのは、現代の食卓にあふれる「植物油」の存在だ。サラダ油、大豆油、キャノーラ油、コーン油――こうした油は、かつて健康に良いと信じられてきた。動物性脂肪よりもヘルシーで、コレステロールを抑え、ダイエットにも効果的だとされていた。しかし、奥山氏はこうした通説を否定する。むしろ植物油に含まれる「リノール酸」などの過剰摂取こそが、体内で炎症を引き起こし、インスリンの働きを妨げ、結果的に糖尿病を引き起こしている可能性があるというのだ。
本章では、糖質悪玉説に固執してきた日本の医療界や食品業界の背景に触れつつ、なぜ今「植物油」が新たな犯人として注目されているのか、その根拠と問題提起を詳述している。
そしてこの章の結論は明快である。
「糖を減らしても糖尿病は治らない。油を見直さなければ、根本的な改善は望めない」
この一文に集約されるように、著者の提案は、食生活のパラダイムシフトを促すものであり、読者に強い衝撃を与える。糖尿病という病の真の姿を明らかにするには、糖質の陰に隠れていた“もう一つの黒幕”に目を向けなければならないのである。
第2章:植物油が引き起こす代謝の異常と糖尿病のメカニズム
近年、「植物油=健康に良い」という常識が、医療や栄養の現場でも疑問視され始めている。とりわけ、糖尿病患者の増加と植物油の消費量の上昇との間に相関関係が見られる点は、多くの研究者の注目を集めている。第1章では、植物油が健康神話の影でいかにして生活習慣病の背景に存在しているかを概観した。本章では、より踏み込んで、植物油が私たちの代謝系にどのような異常を引き起こし、それが糖尿病にどのように関係するのかを明らかにしていく。
■1. オメガ6脂肪酸とインスリン抵抗性
多くの植物油には、リノール酸に代表されるオメガ6系脂肪酸が高濃度で含まれている。これらの脂肪酸は、摂取されると体内で代謝され、アラキドン酸へと変換される。アラキドン酸は体内でプロスタグランジンやロイコトリエンなど、炎症性メディエーターへと変化する。これは、体が必要とする一時的な炎症反応には有益だが、慢性的に摂取されると、全身性の微小炎症状態を引き起こす。
この「微小炎症状態」がインスリンの働きを阻害し、インスリン抵抗性を生む。インスリンは血中の糖を細胞に取り込ませるホルモンであるが、細胞がインスリンに鈍感になると、血糖が下がりにくくなり、結果として高血糖状態が持続する。
■2. 炎症がもたらす膵臓β細胞の障害
糖尿病の発症メカニズムには、膵臓のβ細胞が機能を失うというプロセスも含まれる。植物油に含まれる酸化脂質や過酸化脂質は、膵臓の組織にダメージを与える可能性がある。
とくに高温で調理された植物油に含まれる**ヒドロキシノネナール(HNE)やマロンジアルデヒド(MDA)**などの酸化副産物は、DNA損傷やタンパク質の変性を引き起こし、β細胞のアポトーシス(細胞死)を誘導する。これは、インスリン分泌能力の低下を引き起こし、結果として糖尿病の進行を加速させる。
■3. 肝臓における脂肪代謝の乱れ
植物油を多量に摂取した食生活では、肝臓に脂肪が蓄積しやすくなることも分かっている。これが「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」の温床となり、さらに進行すると「インスリン抵抗性」を引き起こす。
NAFLDの患者では、肝臓が糖をうまく処理できなくなり、血糖の異常が助長される。また、植物油に含まれるエストロゲン様作用を持つ化合物も、肝臓の酵素活性を抑制し、脂質代謝異常の一因となっている。
■4. ミトコンドリア毒性とエネルギー障害
植物油の摂取によって体内に蓄積された酸化脂質は、細胞内のミトコンドリアにダメージを与えることも知られている。ミトコンドリアは「細胞の発電所」とも言われるように、糖質や脂肪をエネルギーに変換する役割を持つ。
ところが酸化ストレスによってミトコンドリア機能が低下すると、代謝効率が悪化し、糖の処理能力が低下する。この影響は全身に及び、糖の利用障害と高血糖状態をもたらす。
■5. 植物油と腸内環境の悪化
最近の研究では、植物油の過剰摂取が腸内環境の悪化にも関与していることが明らかになっている。とくにオメガ6脂肪酸は、腸内細菌のバランスを乱し、腸壁の透過性(リーキーガット)を増加させる可能性がある。
腸壁が傷つき、未消化物質が血流に漏れ出すと、体内で慢性的な炎症が起こり、インスリン抵抗性や代謝異常の誘因となる。つまり、腸の健康もまた、糖尿病の発症と植物油摂取における重要な接点となっている。
■6. サラダ油やキャノーラ油は特に注意
日常的に使われるサラダ油やキャノーラ油は、安価で加熱調理に向いているという理由から多用されるが、その一方で酸化しやすく、オメガ6脂肪酸比率が高いという性質を持っている。これらは工業的に精製され、トランス脂肪酸が微量でも含まれている場合がある。
また、「揚げ物」文化が根付く日本において、これらの油が過熱され、再使用される過程で生じる有害物質が蓄積しやすいのも問題である。毎日のようにこれらの油を摂取していれば、知らず知らずのうちに代謝系に深刻なダメージを与えることになる。
●まとめ:植物油は「善玉」ではなかった
この章を通して明らかになったのは、植物油が「健康的」というイメージとは裏腹に、代謝異常を引き起こし、糖尿病の引き金になりうる実態である。オメガ6系脂肪酸の過剰摂取が慢性炎症を誘発し、インスリン抵抗性、膵臓β細胞障害、肝機能障害、腸内環境の乱れなど、糖尿病に直結するメカニズムが多数明らかにされている。
今こそ、栄養学の常識を見直し、日々の食生活で**「何を避けるべきか」**に目を向けるべきときである。次章では、これらの知見を踏まえ、どのような油脂を「摂取しても良いのか」、そしてその選び方について徹底的に解説していく。
第3章:オメガ6脂肪酸の誤解とリノール酸の真実
オメガ6脂肪酸は、かつては「必須脂肪酸」として栄養学の教科書でも推奨されていた。リノール酸、アラキドン酸などがこれに該当し、「動脈硬化を防ぐ油」「心臓に良い油」として、健康志向の高まりとともにサラダ油、ひまわり油、グレープシードオイルなどに多く含まれた形で、私たちの食生活に浸透していった。しかし、著者・奥山治美はこの章で、そうした栄養常識がいかに危険な誤解に基づいているかを、科学的に、かつ痛烈に暴いてゆく。
■「体にいい油」がなぜ糖尿病を招くのか
まず著者が警鐘を鳴らすのは、オメガ6脂肪酸が持つ“炎症促進作用”である。特にリノール酸は、体内でアラキドン酸へと変換され、そこから「プロスタグランジン」や「ロイコトリエン」など、炎症を誘発する物質が生成される。慢性的な炎症が糖尿病、心血管疾患、自己免疫疾患の根幹にあることは、近年の研究でも明らかだ。
リノール酸を摂ると血糖値が上がるわけではない。むしろ、一見して血糖値には影響を与えない“無害な油”に見える。しかし、その油が引き起こす内臓レベルの炎症こそが、インスリン抵抗性を強め、膵臓のβ細胞を破壊し、やがて糖尿病を引き起こすのである。
■リノール酸の摂取が急増した背景
戦後、食糧難を乗り越えた日本は欧米の食文化を急速に受け入れた。パン食の普及、加工食品の発展とともに、安価な植物油の大量流通が始まる。米国で余剰となった大豆・トウモロコシから抽出した油が、日本の食卓に“健康的なサラダ油”という名で売られたのだ。
この背景には、アメリカの食用油業界と医療団体、栄養学会との密接な関係がある。コレステロール理論が流布され、動物性脂肪を減らし植物油を摂るよう奨励された。が、その代償として、オメガ6の過剰摂取が静かに進行し、日本人の体内は“炎症体質”へと変わっていった。
■オメガ6とオメガ3のバランス崩壊
オメガ6が悪いのではない。本来はバランスの問題である。人間の体はオメガ6とオメガ3脂肪酸を、理想的には1:1〜2:1程度の比率で摂ることが望ましい。しかし、現代の日本人の食生活では、この比率が20:1にもなると言われている。
つまり、体内の油脂構成がリノール酸に極端に偏っていることで、炎症性サイトカインの暴走を招き、糖尿病、脂肪肝、アレルギー疾患、自己免疫疾患の土壌を育ててしまっているのだ。
■マーガリン・ショートニングの罠
さらに奥山氏は、リノール酸の過剰摂取に加え、「トランス脂肪酸」の摂取が追い討ちをかけていると指摘する。マーガリンやショートニングは、リノール酸を水素添加して作られる加工油で、酸化に強く、保存性も高い。しかしその分、体内では分解しにくく、細胞膜を硬化させ、血管や神経の機能を著しく阻害する。
アメリカではトランス脂肪酸の表示義務が導入され、使用が制限されている一方で、日本では「不使用」と書かれていても微量混入が許容されている現状がある。私たちは知らず知らずのうちに、加工食品や外食を通じて“見えない毒”を摂取しているのだ。
■医療と栄養学の「誤解された常識」
著者が本章で最も強調するのは、「医者も栄養士も、リノール酸の危険性を正確に知らない」という現実である。従来の栄養学では、リノール酸はコレステロールを下げる効果がある“良い脂肪”とされてきたが、それはコレステロール神話に基づいた誤情報に過ぎない。
実際、近年では動物性脂肪を控えすぎた人の方が、心疾患や糖尿病リスクが高まるというデータもある。つまり、良かれと思ってリノール酸中心の生活を送ることで、逆に健康を損なってしまっているケースが多数あるのだ。
■リノール酸を避けるには?
では、どのようにしてリノール酸の摂取を避けるべきか? 著者は以下のような対策を提案する。
サラダ油・ひまわり油・グレープシードオイルを使わない
加工食品・総菜・菓子パンなどの油脂表記に注意
マーガリン、ショートニングを完全に排除
自炊で使う油はオリーブオイル、亜麻仁油、ココナッツオイルに切り替える
外食を減らし、油の出所が明確な食生活へ移行する
これらは決して簡単なことではない。しかし、糖尿病という生活習慣病と真正面から向き合うためには、“摂るべきではない油”を見極める知識と行動が不可欠である。
第4章:「健康食品」という名の加速装置 〜その油があなたを蝕む〜
現代社会において「健康」を意識する人ほど、危険にさらされている。皮肉なことに、“体にいい”と信じて積極的に摂取している食品群の中に、糖尿病を進行させる「隠れた加速装置」が潜んでいるというのが、著者・奥山治美の鋭い警告である。
第3章では、オメガ6脂肪酸、とりわけリノール酸の過剰摂取がインスリン抵抗性や膵臓β細胞障害を引き起こすメカニズムを解説した。本章では、それらを含む「意外な食品」や、「健康志向のワナ」ともいえる食材・調理法・商品について、科学的に暴いていく。
■1. “サラダ”が危険になる理由
私たちは「サラダ=ヘルシー」という固定観念を持っている。だが、レストランやコンビニ、ファミレスなどで提供されるサラダには、たいてい市販のドレッシングがかけられている。このドレッシングの主成分はほぼ「植物油」、それも**安価なサラダ油(=リノール酸が豊富な精製植物油)**である。
さらに、揚げたクルトン、カリカリベーコン、加工されたチーズ、マヨネーズなども加わることで、サラダはあっという間に“酸化脂質の塊”へと変貌する。これを日々「健康のために」と摂取していれば、知らぬ間に代謝異常の道を歩んでいることになる。
■2. 「植物性=健康」の誤認
日本人の多くは「植物性=体に良い」「動物性=体に悪い」というイメージを抱いている。この図式がいかに危険であるかを、著者は繰り返し訴えている。
植物油は、植物から採れるからといって“自然”ではない。溶剤(ヘキサンなど)を使って抽出され、漂白・脱臭・加熱精製されることで、大量生産される工業製品である。そこには、自然界には存在しない酸化物質やトランス脂肪酸の痕跡が残っており、体内で強い炎症反応を引き起こす。
一方、動物性脂肪、特に牛脂・豚脂・ラードは、古来より人類が摂取してきた安定した脂肪であり、酸化しにくくエネルギー効率にも優れている。にもかかわらず、カロリー至上主義の栄養学によって悪者扱いされてきた歴史がある。
■3. 健康食品ブームの陰に潜む業界構造
著者は、健康食品市場がいかにして「消費者の不安を煽り、ニセの健康イメージを押し売りしてきたか」を鋭く追及している。
たとえば:
「コレステロールゼロ」と表示された油 → 実は植物油には最初からコレステロールは含まれない。
「トランス脂肪酸フリー」と書かれたマヨネーズ → 微量の酸化脂質は表示されない。
「ヘルシー系スナック菓子」→ オーブン焼きと見せかけて実際は植物油がたっぷり噴霧されている。
これらはすべて、“健康に良さそう”という心理的バイアスを利用したマーケティング戦略である。裏の成分表をよく見れば、「植物油脂」「ショートニング」「加工油脂」などの記載がびっしりと並ぶ。
■4. 「小麦」「グルテン」「砂糖」ではなく「油」が主犯だった
糖尿病のリスク要因としては、よく「小麦製品」「砂糖」「白米」などが挙げられる。しかし奥山は、それらよりもはるかに強く糖尿病を“促進”させる真犯人が植物油であると主張している。
なぜなら、同じ炭水化物を摂取したとしても、植物油と一緒に摂った時に限って、炎症とインスリン抵抗性が増悪するからだ。たとえば:
フレンチフライ(じゃがいも+植物油)
ドーナツ(小麦+砂糖+ショートニング)
カツ丼(ご飯+小麦衣+油)
これらはいずれも「油」が糖質のダメージを拡大している組み合わせである。糖と油の複合摂取が、糖尿病発症の最強コンボとなるのだ。
■5. ダイエット食品・プロテインバーの罠
体重管理を意識して、ダイエット用の食品やバータイプのスナックを日常的に取り入れている人も要注意だ。こうした食品には、糖質を減らす代わりに「油脂」で満足感を補おうとするものが多く、その油脂の多くは酸化しやすい植物油である。
また、ダイエット向けプロテインバーや「糖質オフスナック」にも、「植物油脂」「加工油脂」の記載が多い。こうした商品は、短期的にはカロリーや糖質制限になるが、中長期的には代謝異常・慢性炎症を引き起こし、むしろ糖尿病体質を強化してしまうという逆説的なリスクを孕んでいる。
●まとめ:健康を求める人ほど“見えない罠”にかかっている
本章では、健康志向の人々が陥りやすい“油のワナ”を明らかにした。「サラダ」「ヘルシーオイル」「植物性」「オーガニック」「ダイエット食品」…こうした言葉の裏に隠された真実は、あまりにも知られていない。
著者・奥山治美が繰り返し主張するのは、「健康は知識から始まる」という事実だ。イメージで食品を選ぶのではなく、成分と製法を見極め、科学的根拠をもって摂取することが、糖尿病予防の最も効果的な手段である。
次章では、「本当に摂るべき油とは何か?」をテーマに、体に必要な脂肪の種類、正しい選び方、摂取タイミングについて徹底的に掘り下げていく。
第5章:「“摂るべき油”の選び方と実践」
―― 糖尿病を遠ざける“正しい脂肪”の知識と習慣
ここまでの章で、糖尿病をはじめとする生活習慣病の根底に、過剰なリノール酸摂取と酸化植物油の害が潜んでいることを解説してきた。本章では視点を転じて、「では、どんな油を摂ればよいのか?」という問いに向き合っていく。
脂肪は本来、ホルモン合成・細胞膜構築・エネルギー代謝に不可欠な栄養素であり、“敵”にするのではなく、“味方”につける必要がある。
著者・奥山治美は、現代人が本当に摂るべき脂肪酸を明示し、その選び方・摂り方・調理法まで、具体的かつ実践的に指南している。
■1. 動物性脂肪の復権:牛脂・ラード・バターの底力
長らく“悪者”扱いされてきた動物性脂肪。だが、近年の栄養学では見直しが進んでいる。
奥山氏によれば、動物性脂肪は飽和脂肪酸が主体であり、酸化に強く安定しており、ホルモンバランスや脳機能の維持にも不可欠な存在である。
とくに注目すべきは、以下の3種である:
牛脂(ヘット):エネルギー効率が高く、安定性が高い。高温調理にも強く、揚げ物にも最適。
ラード:ビタミンDが豊富で、腸内環境の改善にも寄与。中華や和食にも合いやすい。
無塩バター/ギー:脂溶性ビタミン群(A・D・E・K)を含み、腸壁の保護や免疫機能に貢献。
飽和脂肪酸に対する「心疾患リスク」というネガティブイメージは、もはや過去の常識である。酸化しない脂肪を摂ることこそが、糖尿病を含む生活習慣病の予防に直結すると、著者は明言している。
■2. 体に優しい“植物油”もある:オメガ3脂肪酸の力
すべての植物油が悪いわけではない。大切なのは脂肪酸の**“種類”と“バランス”**である。著者が積極的に推奨するのが、以下のオメガ3系油である:
これらはα-リノレン酸というオメガ3脂肪酸を多く含み、抗炎症作用が強く、インスリン感受性を高め、血糖値の安定にも寄与することがわかっている。とくに現代人はオメガ6過多になりがちであり、意識的にオメガ3を補うことが重要である。
ただし、注意点がひとつある。これらの油は酸化に非常に弱い。したがって以下の点を守ることが推奨される:
加熱調理には使わず、生で使用(ドレッシング、スープ後入れなど)
遮光瓶で冷蔵保存し、1ヶ月以内に使い切る
酸化臭がしたら即廃棄する
■3. 調理法が油を変える:使い方こそがリスクを分ける
“どの油を選ぶか”と同じくらい重要なのが、“どのように使うか”である。著者は調理法によって、油が「健康食品」にも「毒物」にもなることを明確に説いている。
高温加熱(揚げ物・炒め物)には動物性脂肪 or ココナッツオイルが適している
非加熱(和え物・後がけ)にはえごま油・亜麻仁油などのオメガ3を
このように、調理温度・時間・素材との組み合わせによって、油の健康影響は大きく変わる。特に、加熱に弱い油を高温調理することで酸化が進み、アクロレインやヒドロキシノネナールといった有害物質が生じてしまうリスクがある。
■4. サプリメントより“毎日の油”を変えよ
「サプリメントで栄養バランスを補っているから安心」と考える人も多いが、奥山氏はその考えに疑問を投げかける。
オメガ3サプリ(EPA・DHA)やマルチビタミンでは、炎症体質を根本から改善するには不十分であり、油そのものを変えなければ、腸内環境や代謝は変わらないという。
毎日使う油を変えること。それは、薬に頼らず生活習慣病を遠ざける“最も根本的なセルフメディケーション”である。
■5. 糖尿病予防・改善における「油の黄金ルール」
著者は、糖尿病を改善・予防するための“油の黄金ルール”として、以下の3原則を提示している:
リノール酸の摂取を意識的に減らす(できるだけゼロに近づける)
加熱に強い安定した脂肪を調理に用いる(ラード・ギー・ココナッツオイルなど)
これらのルールを守ることで、インスリン抵抗性の改善・膵臓の保護・血糖値の安定・炎症体質の緩和といった多方面の効果が期待できる。
つまり、「油を変えること」は、単なる“食習慣の見直し”ではなく、慢性疾患から命を守る“予防医学”そのものなのである。
第6章:冷蔵庫から糖尿病を追い出す
―― 日常生活の油リセット術
「健康になるにはまず冷蔵庫を変えよ」――
これは奥山治美氏が繰り返し語る言葉である。本章では、糖尿病予防・改善のために最も現実的かつ効果的な行動である“冷蔵庫の中身の見直し”を中心に、家庭における油の管理と生活習慣改善の具体的方法を提示していく。
これまでの章で、現代型糖尿病の裏に「過剰なリノール酸摂取」「酸化植物油」が潜んでいることを解説してきた。だが、それを理解するだけでは不十分である。実際に何を“買い”、何を“捨て”、何を“使うか”という行動の転換こそが、生活習慣を変え、病を遠ざける鍵となる。
■1. 冷蔵庫の中に潜む「糖尿病製造機」
まず冷蔵庫の中を開けてみてほしい。おそらく、多くの家庭には以下のような「見えざるリスク商品」が眠っているはずだ。
サラダ油(キャノーラ油・大豆油など):加熱時に酸化しやすく、血糖調整機能を低下させる。
市販ドレッシング類:リノール酸と糖質の複合体であり、体内炎症を誘発。
マーガリン・ショートニング使用のパン・お菓子:トランス脂肪酸と酸化脂質の塊。
加工食品・冷凍食品:保存性を高めるため植物油が多用されている。
市販の総菜や弁当:調理過程で何度も使い回された酸化油が使用されがち。
奥山氏は、「油は食品ではなく“化学物質”として選別せよ」と語る。つまり、味や値段ではなく、酸化度や脂肪酸の種類で判断すべきなのだ。
■2. 冷蔵庫に「入れるべき油」
では、逆に冷蔵庫に常備すべき“糖尿病と闘う油”とは何か?
以下は著者が推奨する「選ばれし油たち」である:
とくにオメガ3系の油(えごま油など)は、冷暗所・遮光瓶で保管し、開封後は1か月以内に使用するのが理想である。
■3. 「買い物リスト」を変える
糖尿病を改善したいなら、「買い物の基準」を変える必要がある。
奥山氏は、「成分表示を読む」習慣こそが、自分と家族を病気から守る最も重要なスキルであると述べている。
買い物の際には、以下の点をチェックすべきである:
「植物油脂」「加工油脂」「ショートニング」と記載された商品は避ける
「トランス脂肪酸ゼロ」表示でも油の種類を確認する(完全ではない)
「コレステロール0」は意味がない表示(植物油には最初から含まれない)
代わりに選ぶべきは、素材そのものがシンプルな食品(肉・魚・野菜・卵・豆類など)。油は後から“自分で選んで加える”ことが最善の選択肢である。
■4. 調理法と調味料の見直し
どれだけ良い油を買っても、調理法を誤れば台無しになってしまう。
奥山氏は、「台所は“薬局”であり、“化学工場”でもある」と表現する。つまり、どんな“化学変化”をキッチンで起こすかが、健康を左右する。
推奨される調理法は以下のとおり:
揚げ物 → ラードやギーを使用、油の温度と再利用に注意
炒め物 → ココナッツオイル、オリーブオイルで低温調理
サラダ → 市販ドレッシングを避け、オリーブ+レモン+塩で自作
また、調味料も重要である。市販のドレッシング・たれ・ソースの多くは、油+糖質+添加物の複合体であり、極力避けたい。
■5. 外食・コンビニとの付き合い方
現代生活では避けて通れない外食やコンビニ食。ここにも油の罠が潜んでいる。
奥山氏は、「食べないことを選べない状況では、“最悪を避ける”ことが最善」と述べる。
外食時のポイント:
揚げ物・炒め物を避け、焼き・蒸し調理を選ぶ
サラダにドレッシングをかけないよう頼む
コンビニでは、焼き魚・冷奴・ゆで卵・無添加ナッツなどを選ぶ
つまり、“完全を求める”のではなく、リスクを最小化することが、現実的な選択なのだ。
●まとめ:日常の風景を変えることが、体質を変える
「病気とは、生活の結果である」――この言葉は、まさに本章のテーマに通じる。糖尿病という慢性疾患を改善するには、劇的な手術や薬ではなく、“冷蔵庫”“買い物”“調理”といった日常の風景を変えることが必要不可欠なのだ。
油は、目に見えない「炎症の種」である。どんな油を選び、どのように扱い、どこに保存し、どう料理するか――それが、血糖値の安定を左右し、代謝を根本から変えていく。
第7章:医学と栄養学が見落としてきた油の真実
―― なぜ“体にいい油”が糖尿病を加速させたのか
本章では、なぜ現代の医療や栄養学が、「油と糖尿病」の関係について重大な誤認をしてきたのかを深掘りしていく。
「脂質=悪」「コレステロール=敵」「植物油=体に良い」という固定観念は、どのように生まれ、なぜここまで広まったのか。
そしてその結果として、どれほど多くの人が慢性的な糖尿病や生活習慣病に陥ってしまったのか――。
奥山治美氏は、本書の中で現代医学の盲点を浮き彫りにし、真の原因に迫る“油の真実”を明らかにしている。
■1. 医学教育に欠けていた「油の知識」
日本の医学部では、6年間のカリキュラムのうち、栄養学に割かれる時間はわずか数時間にすぎない。
医師は「診断」と「薬物療法」には詳しくとも、「食事の本質的な構成」や「油の生理作用」にはほとんど触れずに現場に出てしまう。
このため、多くの医師が以下のような誤認を抱えたまま患者に接している:
飽和脂肪酸はすべて動脈硬化の原因になる
植物油はヘルシーで心疾患リスクを減らす
コレステロール値は低ければ低いほど良い
脂肪はできるだけ避けるべき栄養素である
だが、奥山氏の研究は、これらの常識を根底から覆すものである。
脂肪には“良いもの”と“悪いもの”があり、特に現代の精製植物油は“炎症の元凶”となっている。それを理解していない医療者が、逆に患者を「脂肪制限=糖質依存」に導き、症状を悪化させているケースが多々あるのだ。
■2. 医療ガイドラインが推進してきた“油の罠”
日本糖尿病学会のガイドラインでも、依然として「飽和脂肪酸の摂取制限」「植物油の活用」が推奨されている。
これらの記述は、旧来の疫学研究や20世紀型の臨床試験に基づくものであり、近年の炎症性研究・脂質代謝研究とは乖離している。
奥山氏は、以下のような問題点を指摘している:
リノール酸の過剰摂取によるインスリン抵抗性への影響が無視されている
トランス脂肪酸の害には触れるが、酸化リノール酸には言及しない
その結果、医療者は「油を減らす指導」に偏り、糖尿病患者の多くは“炭水化物に偏った脂質制限食”を強いられ、炎症体質が固定されてしまう。
■3. 背景にある「産業構造」と「栄養マーケティング」
なぜ誤った「油=ヘルシー or 悪玉」という二元論が浸透してしまったのか?
その背景には、**植物油業界・食品業界・製薬業界の思惑が絡む“栄養マーケティングの歴史”**がある。
製薬業界は“高コレステロール”を病気にし、スタチン等の薬を普及させた
これにより、以下のような社会構造が完成してしまった:
植物油の大量摂取 →
インスリン抵抗性の悪化 →
糖尿病・高血圧・脂質異常症の増加 →
薬物療法の拡大 →
根本原因が無視され、患者は増え続ける
この連鎖を断ち切るには、生活の中の油を変えることが、最も即効性のある“改革”であると、奥山氏は警鐘を鳴らしている。
■4. 新たな脂質代謝学:オメガ6とインスリン抵抗性
近年の栄養医学では、リノール酸とインスリン抵抗性の関係が明確になりつつある。
特に、「酸化リノール酸」がもたらす炎症性サイトカインの活性化は、インスリン受容体の働きを妨げ、血糖値を上昇させる。
また、以下の作用も認められている:
これらの生理反応は、「油=カロリー」では片付けられないほど複雑かつ深刻である。
■5. 医療と栄養の分断を超えるアプローチへ
奥山治美氏の提唱する「油から見直す栄養医療」は、従来の“糖質制限”や“薬物療法”を否定するものではない。
むしろ、**医療と栄養をつなぐ“第三の道”としての「脂質改革」**こそが、慢性疾患に立ち向かう新たな武器となる。
本章の結論は以下の通りである:
医療者の栄養知識アップデートが急務
医療ガイドラインも“油の質”を評価すべき
生活者は「油=見えない薬」として付き合う必要がある
つまり、糖尿病と闘うためには、「糖」を見るだけでは足りないのだ。
「油」を見直すことこそが、隠れた原因にメスを入れる“真の治療”なのである。
第8章:油を変えて人生が変わった人々
―― 血糖値改善の実録と検証
これまでの章では、糖尿病と「悪い油」との関係について、理論的・医学的な背景を整理してきた。だが本章ではいよいよ、「理論が現実になった瞬間」を明らかにしていく。
油の選び方を変えたことで血糖値が改善した、インスリン注射をやめられた、HbA1cが下がった、疲れが消えた――そうした“人生の反転劇”は、決して奇跡ではない。
ここでは、奥山治美氏のもとに実際に寄せられた症例・体験談・数値変化をもとに、油の変更が糖尿病に与える影響を検証していく。
■1. 65歳男性の逆転劇:HbA1cが8.2 → 5.8へ
定年後に糖尿病を宣告されたAさん(65歳・男性)は、医師から食事制限とインスリン導入を指導され、投薬を続けながら「リスク管理」の人生を余儀なくされていた。
しかしある日、奥山氏の著書に出会い、「糖ではなく油が犯人かもしれない」と考え始める。
Aさんが実施した主な変更は以下の通り:
サラダ油・キャノーラ油 → ラード、ギーに変更
市販ドレッシング廃止、オリーブオイル+塩に
加工食品を極力避け、素材から自炊
朝食を卵+納豆+味噌汁に固定(油を生かす構成)
その結果、わずか3か月でHbA1cは8.2から5.8へと劇的改善。主治医からは「薬の中止」も許可され、以後は食事と運動のみで正常範囲を維持している。
Aさんはこう語っている。
「油を変えるという発想はなかった。ずっと“糖のせい”にしていたが、原因はもっと見えないところにあったんです。」
■2. 30代女性の疲労回復とPMS改善
Bさん(36歳・女性)は、血糖値こそ正常値内にあったが、慢性的な疲労感・むくみ・生理前の体調不良(PMS)に悩まされていた。医療機関では「自律神経の乱れ」と診断されるも、根本的な改善は得られなかった。
そこで、彼女は「油リセット生活」にチャレンジ:
植物油・調理済み食品の断捨離
グラスフェッドバターで朝食を調理(バターコーヒー含む)
1日スプーン1杯の亜麻仁油を習慣化
自作ドレッシング(オリーブ+酢+塩+にんにく)
1か月後、彼女はこう語る。
「まず、朝から元気になったのが一番の驚きでした。生理前のイライラや頭痛もかなり軽くなり、“体が静かになった”感じです。」
後の血液検査で、中性脂肪が改善し、空腹時血糖も5ポイント低下。
油の質の改善が、女性ホルモンバランスや血糖安定に寄与していたと推測される。
■3. 50代夫婦の共同実践:共に糖尿病予備軍脱出へ
Cさん夫妻(55歳・58歳)は、共に糖尿病予備軍と診断され、医師からも「生活習慣を一変させなければ本格的な治療になる」と言われていた。
当初は糖質制限に取り組んでいたが、空腹感とストレスが強く、夫婦喧嘩が増えるばかりだった。
そこで、アプローチを「糖質」から「脂質」に変更:
食事の中心を「肉と良質脂肪」に切り替え
揚げ物はココナッツオイルかラードに限定
サラダは毎回“油を摂る”目的で意識して食べる
ストレス軽減と睡眠の質向上を意識し、PFCバランスを最適化
この結果、HbA1cが夫婦共に6.3 → 5.9まで低下し、再検査でも正常域を維持。
なにより、日常のストレスが大幅に減り、「夫婦関係も良くなった」と語っている。
■4. 中学生の母親の気づき:弁当の油が子どもを守る
Dさん(42歳・主婦)は、息子のアトピー体質と食後の眠気、集中力低下に悩んでいた。
成績も落ちてきたことで、「栄養面から見直したい」と考え、弁当作りを全面的に改革。
変更点:
ウインナーや揚げ物惣菜を排除し、手作りメインに
炒め物はギーまたはラードを使用
サラダに毎日亜麻仁油を小さじ1使用
朝食は「卵・納豆・味噌汁・白米」で固定
3か月後、息子の肌はつるつるになり、学校からも「授業中の集中力が増している」との報告。体重も自然に減少し、血糖コントロールが改善された可能性が高い。
■5. 共通点は「継続できた」こと
これらの症例からわかるように、「油を変える」ことは糖尿病改善だけでなく、疲労・ホルモンバランス・肌・集中力にも影響する全身的な改善に直結している。
しかも、この方法は以下の点で“継続しやすい”:
お金がかからない(むしろ加工食品を減らして節約)
極端な我慢がいらない(糖質制限よりストレスが少ない)
家族全体で取り組める(健康意識の共有)
「意識する」だけで変えられる(料理法・買い物選び)
奥山氏が伝えるメッセージは明確だ。
「糖尿病は、食べすぎではなく、“間違った食べ方”の結果である」
そして、「その食べ方は、まず“油”から始まる」のだ。
第9章:なぜ“油が原因”という情報が広まらないのか
―― 情報統制と産業構造が生む“生活習慣病の迷路”
これまでの章で、「糖尿病と悪い油の関係」「油を変えた実例による改善効果」などを述べてきた。しかしここに至って最大の疑問が残る。
それは――
**「なぜ、これほど重要な事実が、世間に広まっていないのか?」**ということである。
本章では、医療、行政、教育、メディア、そして食品・製薬業界を巻き込んだ「生活習慣病情報の流通構造」の深層を明らかにし、なぜ正しい知識が届かないのか、どのようにして私たちは“油の罠”にかけられてきたのかを明確にしていく。
■1. 医学の限界:「病気を治す」が「薬を処方する」に
日本の医療は世界的に見ても精密で高度なシステムを持っている。
しかし、糖尿病のような慢性疾患において、現場の医師の多くが採っているアプローチは、
「薬で数値を下げる」
「定期的な血液検査で管理する」
「自己管理を徹底させる」
という形式的なものであり、根本原因――たとえば「油の種類」や「代謝環境の変化」には目を向けていない。
その理由は明白である。
医学部では栄養教育が数時間しかない
ガイドラインは過去の研究と薬剤効果に基づいている
医師の多忙な診療現場では、生活指導まで手が回らない
「治すより管理する」方が継続的な利益になる
つまり、「油を変えるだけで血糖値が改善する」ことを本気で学んでいる医師は極端に少ないのだ。
■2. 行政の食育がもたらす“植物油推奨”
日本の文部科学省や厚労省が推進する食育では、「動物性脂肪は控えましょう」「植物性食品はヘルシーです」という方針が強く打ち出されてきた。
学校給食や保健指導で使われる資料にも、次のような図式がしばしば登場する。
脂質の種類:「飽和脂肪酸=悪」「不飽和脂肪酸=善」
植物油を活用しよう(サラダ油・大豆油など)
動物性脂肪(バター・ラード)は心臓病の原因
このような情報が子どもの頃から刷り込まれていることで、大人になってから「植物油が原因」と言われても信用できない土壌が形成されてしまう。
さらに、こうした行政方針の背後には、農水省や産業界と結びついた「大豆余剰処理」「輸入油活用」「低コスト給食食材確保」などの政治的理由があることも忘れてはならない。
■3. メディアの構造:スポンサーは誰か?
テレビ番組、雑誌、Webニュース――これらの媒体は、誰のカネで動いているのか?
答えは明白である。スポンサー企業、とくに食品・医薬・健康関連の商品を扱う大企業だ。
サラダ油・ドレッシングを製造する大手食品メーカー
コレステロール低下食品を売る健康食品会社
糖尿病治療薬を展開する製薬企業
これらの企業が提供する番組や広告で、
「植物油が糖尿病の一因である」
「リノール酸がインスリン抵抗性を悪化させる」
という内容が報道されることは、事実上あり得ない。
メディアは視聴者ではなくスポンサーの方を向いている。
そして視聴者は、「中立な情報」と信じて、その言葉を鵜呑みにしてしまう。
■4. 栄養学の分断と“古い常識”の壁
栄養学そのものも、内部で大きな分断がある。
一方では最新の脂質代謝学・ホルモン栄養学が進展しているが、
一方では「カロリー計算と三大栄養素のバランス」の古典理論が未だに主流を占めている。
「摂取カロリーを抑えれば痩せる」
「油は1g=9kcalだから減らすべき」
「糖質制限が行き過ぎると危険」
このような“教科書的理論”が、医療現場でも栄養士の間でも依然として生き続けている。
「油の質がすべてを決める」という視点は、依然として傍流扱いされているのだ。
■5. 情報リテラシーの欠如と“サイレント誘導”
結局、われわれ一般生活者が抱える最大の問題は、**「何を信じればいいか分からない」**という情報過多社会の迷路である。
奥山氏が指摘するように、**事実は“言われていない”のではなく、“言われないようになっている”**のである。
情報リテラシーがなければ、
「テレビで紹介された健康食品」に飛びつく
「病院でもらった指導パンフレット」を鵜呑みにする
「ネットで見たから」と信じてしまう
こうして、「自分の体を守るための判断力」が失われていく。
■結論:自分の健康は、自分で取り戻すしかない
このように、正しい情報が届かない原因は複合的であり、誰か一人の責任ではない。
しかし明らかなのは、**「糖尿病の原因は糖のとりすぎ」だけではなく、「見えない油によって代謝環境が狂っている」**という事実が意図的に見落とされているということである。
奥山氏は繰り返しこう語る。
「本当に体に悪いのは、糖よりも“油”なのです。」
そして、その油の情報が届かないという構造こそが、今の日本社会が抱える最大の健康リスクなのである。
第10章:健康を取り戻すための“油革命”
―― 家庭・教育・社会にできること
長年、「糖のとりすぎが糖尿病の原因」とされてきた常識が、実は“油”という見えざる因子によって支配されていた。
奥山治美氏の提唱するこの視点は、単なる食事法の提案にとどまらず、個人・家庭・社会全体の“健康観”そのものを根底から揺さぶるものである。
最終章では、今後、私たちが実践できる変革の具体策――すなわち「油革命」について、家庭・教育・社会の各視点から考察していく。
■1. 家庭が変われば、社会が変わる:キッチンから始まる革命
すべての食事は、家庭の台所から始まる。
そこに並ぶ調味料や油の種類が、10年後の自分や家族の健康を決める。
奥山氏が最も強調するのは、「選ぶこと」の力だ。
サラダ油・キャノーラ油 → ラード・バター・ギーに
市販ドレッシング → 自家製オイルベースのものに
揚げ物 → ラード・ココナッツオイルで短時間調理
加工食品 → 原材料と油脂の項目を必ず確認する
家庭で油を変えることは、未来の医療費・家族の健康寿命・子どもの集中力・親の活力すべてを左右する。
毎日の選択が、“沈黙の炎症”か“細胞の再生”かの分岐点となる。
■2. 教育の現場にこそ、「脂質教育」を
学校給食、保健指導、食育授業――現在の教育現場では、脂質に関する指導は表面的で、「カロリー制限」「動物性脂肪=悪」といった旧来の知識が教え込まれている。
今後、以下のような教育改革が必要である:
「油の質が代謝に与える影響」についての正しい教材整備
学校給食の油の見直し(使用する揚げ油の質など)
栄養士・調理員への最新脂質代謝に関する研修
「バター=悪」のような単純な二元論からの脱却
子どもの脳神経やホルモンは油によって形成されており、子ども時代の油の摂取は、知能・集中力・精神の安定に直結している。
教育現場の意識変革が、社会全体の健康水準を底上げする鍵となる。
■3. 医療と行政に求められる「構造的な再設計」
医療と行政には、より根本的な構造変革が求められる。
たとえば:
医学部における栄養教育の大幅拡充
糖尿病治療における食事指導の「油中心型」への転換
医療現場と管理栄養士の連携強化(薬より食を重視)
食品表示の義務強化(トランス脂肪酸・オメガ6脂肪酸の記載義務化)
サラダ油の過剰使用への警告を含む行政啓発
奥山氏が繰り返し提言するように、「医療の目的は病気を治すことではなく、病気をなくすこと」であるべきだ。
その視点を持つならば、「なぜ糖尿病患者が増え続けているのか」という問いに、正面から向き合わなければならない。
■4. 情報リテラシー時代の「食の自立」
個人ができる最大の対策は、「自分で選ぶ力」を持つことだ。
メディアの情報を鵜呑みにしない
表示を見る習慣をつける(原材料・脂質の種類)
「なぜこの油なのか?」と常に問い直す
試しに1週間、油を全部変えてみる(体感が変わる)
同調圧力に屈せず、自分と家族の体で判断する
奥山氏が語るのは、「知っている人が、次の人に伝えていくこと」の大切さである。
ひとりの行動が、家族に伝わり、職場に広がり、社会を動かす力になる。
■5. 未来への提言:「食べる油」は「生きる思想」
奥山治美氏のメッセージは、食事のノウハウを超えた“人生哲学”でもある。
「人は“何を食べるか”で、思考も感情も人生も決まっていく」
「油は、命の火を灯す“芯”のようなもの。
良質な芯がなければ、どんなに火を点けても、炎は揺らいでしまう。」
食事を整えることは、単なる健康法ではなく、「生き方を整える」ことに他ならない。
糖尿病の本当の克服とは、薬を減らすことでも血糖値を正常に保つことでもなく、
「自分の体に責任を持つ人間として、自分の選択で生きること」である。
最終結論:油を変えれば、人生が変わる。
糖尿病は、「糖」のとりすぎのせいではない。
真の原因は、「質の悪い油が細胞を攻撃していた」ことにある。
この視点の転換が、すべての始まりである。
油を変えることは、薬をやめるよりも先にできる。
未来を変えるのは、医者でも政府でもなく、あなたの台所とその手の選択である。
●あとがき
私たちは知らぬ間に、過剰な糖や添加物、そして質の悪い油に囲まれた生活を送っています。
そして「病気になったら病院へ」「薬があれば安心」と信じ込まされ、根本的な解決を置き去りにしてきました。
しかし、奥山治美氏の提示する「油の真実」は、そうした常識に一石を投じる強烈なメッセージです。
日々の料理の油を変えることが、未来を変える――その一歩が、あなたと家族の人生を救う可能性を持っているのです。
本書が、すべての読者にとって「気づき」と「行動」のきっかけとなることを願ってやみません。







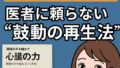
コメント