まえがき
あなたは最近、最後に本をじっくり読んだのはいつでしょうか。
「スマホなら見続けられるのに、本はどうしても続かない」
そんな悩みを抱える人は、きっと少なくないでしょう。
本書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、
現代の社会構造と読書習慣の変化を、歴史と実体験から紐解きながら、
「文化的時間を取り戻すヒント」を示すためにまとめました。
読書はただの趣味ではなく、
人間が「自分のペースで生きるための手段」。
この本が、あなたが再び本を楽しむきっかけになれば幸いです。
第1章:本が読めないのは「忙しさ」のせいではなかった
1-1. スマホ時間はあるのに、本が読めない
著者は冒頭でこう問いかけます。
「スマホは長時間見られるのに、本が読めないのはなぜだろう?」
多くの現代人は一日中スマホでSNSやニュースを追う一方で、
かつてのように腰を据えて本を読むことが難しくなっています。
これは単なる「時間がない」という話ではありません。
スマホを見る余裕があるのに本が読めない。
そこには現代特有の「心の余裕の喪失」が潜んでいるのです。
1-2. 本を読むことは「余計なこと」を受け入れる行為
著者は、本を読むという行為が「余計な情報を許容すること」だと指摘します。
ネットでは「知りたいことだけ」「自分が求めた情報だけ」が即座に手に入る。
しかし本は違います。
物語にしろ、論考にしろ、背景や物語の寄り道、著者の脱線、
すぐには「役に立たない話」に溢れているのです。
本を読むには「余計なもの」「関係ないもの」を一緒に受け止める心の余裕が必要です。
1-3. ノイズを嫌う現代の労働者
現代社会では「効率化」「最適化」が良しとされます。
そしてその価値観は、仕事だけでなく日常のあらゆる場面に浸透しています。
SNSのタイムラインも、自分にとって都合の良いものだけが流れてくるように最適化される。
ネットニュースも「自分の興味ある分野」だけが表示される。
Amazonのレコメンドも「自分が買いそうな商品」だけが並ぶ。
この「ノイズ排除志向」が、読書にも影響を与えます。
読書は、余計な話、背景、著者の個人的意見といった
「無駄な情報」を含んだ時間。
最適化に慣れた頭と心では、これを楽しめなくなってしまうのです。
1-4. なぜ労働者は余裕を失うのか
著者は現代の労働環境にも原因を見出します。
長時間労働、責任、成果主義、
そして「生活のすべてを仕事に捧げることが良しとされる風潮」。
この環境は、
「読書に必要な心の柔軟性」「じっくり考える余白」
を奪います。
つまり、単に時間が奪われたのではなく、
「思考の余裕」「許容の余裕」そのものが削られているのです。
1-5. 読書は「能動的な余白」づくり
著者は、読書を「能動的に余白をつくる行為」だと位置づけます。
本の中に没入し、寄り道を楽しみ、
著者の背景に想いを馳せ、
自分のペースで読み進める――。
これは、「仕事の効率化」に染まった頭では
到底楽しめない時間です。
本を読めなくなったのは、
働く人々が余白を排除する社会構造に包まれているからだ。
第2章:読書と労働の歴史的関係
2-1. 読書文化の始まりと「階級」
著者は、そもそも「本を読む」という文化が
歴史的にはごく限られた人たちのものだったことを指摘します。
かつて本を読むのは、
貴族、知識階級、宗教者など、
「労働」から自由な階層の人々。
なぜなら、読書には「長い時間」「集中できる環境」「余裕」が必要だったからです。
物理的な「時間の余裕」だけではなく、
精神的に「読書に没入できる余白」も不可欠でした。
2-2. 日本における「大衆読書文化」
日本では明治時代以降、出版業界の発展により
「庶民でも本を買える環境」が整いました。
この頃から、
読書は「知識の習得」「教養人の証」として
労働者や中流層にも広がり始めます。
とりわけ戦後、文庫本の普及が「大衆読書文化」を加速させました。
通勤電車で文庫本を読むサラリーマン。
出張先の宿で寝る前に本を開く人。
この時代には、
「働く人こそ、本を読む」という価値観が
社会の中に根づいていったのです。
2-3. 高度経済成長と「読書からの乖離」
ところが、高度経済成長期には、
長時間労働と猛烈な競争社会が進みます。
企業戦士という言葉が生まれ、
男性正社員は「余暇すら会社のために使う」ことが
称賛されるようになりました。
これにより、
「読書は時間に余裕のある人の趣味」
「本を読む暇があるなら働け」という価値観が
少しずつ浸透していきます。
2-4. 2000年代のIT化と自己啓発ブーム
21世紀に入り、
インターネットが社会に普及します。
その中で、本のあり方も変わっていきました。
「速読術」ブーム
「1冊10分で要約できる」サービスの登場
「本は自己啓発のためのツール」への変質
この変化は、「本を楽しむ」から
「本を効率的に使う」へと読書の目的を変えていきました。
「本を読むこと自体」が楽しみだった時代から、
「読書は目的のための手段」として消費される時代への移行。
これも、現代人が本を読むことから離れていく
大きな原因だったのです。
2-5. 読書から切り離された「文化の時間」
こうして「労働」と「文化的な時間」が分離し、
労働者は「文化的な時間」を
人生のどこかに“特別に設けなければならない”状況に置かれるようになりました。
著者はここで問い直します。
かつては、
「働きながら本を読むことが当たり前」だったのではないか。
なぜ現代は、それが難しくなったのか。
労働と文化が自然に交わる「生活のあり方」を取り戻さなければ、
これからも「本を読む心の余裕」は失われ続けるだろう。
第3章:ノイズとしての本の本質
3-1. ネットと本の「情報の質」の違い
スマートフォンやネットは「自分が知りたいこと」を
効率的に提供するメディアです。
一方、本は必ずしも「知りたいこと」をすぐには教えてくれない。
著者はこの違いを「情報の質の差」と言います。
ネット → ノイズを削ぎ落とした情報
本 → ノイズを含んだ情報
本には、著者の脱線や背景説明、思想的文脈が詰まっており、
それが「読書の豊かさ」の源泉でもあります。
3-2. 読書は「ノイズを楽しむ行為」
この章の核心は、
「読書はノイズを楽しむ行為である」という視点です。
物語の回り道、思想書の冗長な理屈、
すぐに役立たない蘊蓄――。
そうした「無駄」にこそ、本を読む喜びがある。
しかし、最適化・効率化された現代社会においては、
この「無駄」を楽しむ心の余白が奪われてしまう。
その結果、
「本が読めない」と感じる人が増えているのです。
3-3. 読書の時間と「非合理性」
スマホのように短時間で情報を得るのではなく、
読書は数時間〜数日をかける「非合理的な営み」です。
この「非合理性」も、現代人が本を手放す原因になっています。
現代は合理性が最も尊ばれる時代。
その中で読書は「無駄」「趣味の贅沢」と見なされがちです。
しかし、著者はこの「非合理性」こそが読書の本質であり、
「非合理だからこそ人間らしい営み」だと位置付けます。
3-4. ノイズを許容できる社会構造の必要性
ここで著者は社会的提案をしています。
労働時間が長く、
成果を短期的に求める社会構造の中では、
「ノイズを楽しむ」時間は確保できない。
働く人が本を読めるようになるためには、
単に「個人の努力」で解決できる問題ではなく、
社会がノイズを許容する構造改革が必要だ
という主張です。
3-5. 読書の再定義
最後に、著者は読書の再定義を試みます。
読書とは:
ノイズを楽しむ
非合理に時間を費やす
役に立たないものに価値を見出す
つまり、本を読むことは「役立つ・効率的」から最も遠い場所にあり、
だからこそ、人間らしい文化的営みなのです。
第4章:半身社会の可能性
4-1. 「全身労働社会」の弊害
現代は「全身で仕事をする」社会です。
著者はこれを「全身労働社会」と呼びます。
スマホがあれば、
通勤中、休日、寝る前でも仕事ができる。
SNSで仕事仲間と24時間つながる。
これが「働きすぎ社会」をつくりあげてきました。
全身を仕事に捧げることは、
効率化・成果主義に適応するには理にかなっています。
しかしその代償として、
人間が「文化的な時間」や「趣味の時間」を失うようになりました。
4-2. 半身で働くという思想
ここで著者が提唱するのが「半身社会」という考え方です。
「半身社会」とは:
仕事に全身全霊をかけず、
どこか半分は「文化的な余裕」に身を置く。
この「半身の余白」によって、
人間らしい時間を確保し、
ノイズを楽しみ、
「読書できる自分」を取り戻すことができるという発想です。
4-3. 働き方改革を「文化の側から考える」
これまでの「働き方改革」は、
労働時間を減らす
残業を減らす
有給休暇を消化する
といった「働く側」だけに焦点を当ててきました。
著者はここに疑問を投げかけます。
「本当に“文化の時間”が戻ってきたか?」
答えはノーです。
むしろ、余った時間はスマホや効率的な消費に使われ、
「文化的なノイズ」はますます減少しました。
これからの「働き方改革」には、
「文化の側からのアプローチ」が必要だと著者は主張します。
4-4. 半身で働く人の具体像
では「半身で働く」とは具体的にどんな働き方か。
週4勤務で生活する
兼業・副業を活用して「余白」を作る
在宅勤務で通勤時間を「文化的な時間」に変える
生産性を上げ、敢えてゆとりを持つスケジュールを選ぶ
半身で働くとは、
労働から完全に離脱することではありません。
自分の時間の中で「文化を受け入れる余地」をつくることです。
4-5. 半身社会の可能性と希望
「半身社会」は「全身労働社会」のアンチテーゼです。
著者は次のように結びます。
労働の効率と文化の時間は相反しない。
「文化的な余裕」がある人こそ、
長期的には豊かな労働成果を生む。
半身で働き、半身で文化的活動をする社会は、
労働者の幸福度を高めると同時に、
社会全体をしなやかに強くする。
第5章:実践ガイド ― 働きながら読書を楽しむ方法
5-1. 時間管理術 ― スキマ時間の活用
まずは現代的な「忙しい人でもできる読書法」です。
通勤時間の「10分」を読む時間にする
スマホ時間の5分を「Kindle」や電子書籍アプリに切り替える
夜寝る前の15分間だけ「紙の本を開く」
大事なのは「長時間一気に読む」ことを目標にしないこと。
「短時間でもページをめくれば、必ず読了に近づく」というマインドが必要です。
著者自身も、
「まとまった時間が取れないからこそ、
こまぎれ読書を楽しむようになった」と述べています。
5-2. メンタルリセット ― ノイズを許す心
読書ができないのは、
「ノイズを嫌う脳」に慣れすぎた結果です。
そこで次のような「読書モードへのメンタルリセット」を試みます。
読み始めるときに「役に立つか立たないか考えない」と決める
「脱線上等」の気持ちで物語に没入する
一気に読もうとせず、途中で考え込む時間をあえて作る
「ノイズを含む時間」を楽しむ姿勢そのものが、
読書の楽しさを取り戻すカギです。
5-3. 習慣化技術 ― 読書を日常の一部にする
著者は、
「読書を“特別な行為”から“日常習慣”に戻すことが重要」
と指摘します。
朝起きたらスマホではなく本を開く
食事中に本をテーブルに置いておく
読みかけの本をバッグの中に必ず1冊入れておく
「本が手の届くところにある」だけで、
人は自然にページをめくるようになります。
5-4. 読書会・共有のすすめ
現代人は「孤独な読書」を強いられがちです。
そこで「読書会」や「SNSでの感想共有」を活用するのも一つの手。
「他人と話す前提」で読むと、
集中力も増し、意外な視点を得られることもあります。
本を「個人の趣味」から「他人と交流する場」へ変換することで、
読書が続けやすくなります。
5-5. 文化的時間の意義
最後に著者が伝えたいこと。
それは「文化的時間はぜいたくではなく、
人間の尊厳を守る時間だ」ということです。
本を読む時間は、
効率も目的も超えて「自分のペースで生きる時間」。
だからこそ、忙しい現代人が失いがちな
「自分自身を取り戻すための行為」なのです。
「半身で働き、半身で文化的時間を楽しむ」――
その第一歩として、「まず1ページだけ読む」ことから始めてほしい。
あとがき
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本を読む心の余裕を失ったのは、決して個人の怠慢ではありません。
社会全体が「効率」「即効性」を重視する中で、
読書に必要な「無駄」「寄り道」「ノイズ」を排除してきた結果です。
「半身社会」という提案は、
決して仕事を怠けることではありません。
半分は労働に、半分は文化に身を置くことで、
人生に豊かさと余白を取り戻す生き方です。
本書を通じて、
あなたの日常に再び「本を読む時間」が訪れることを願っています。





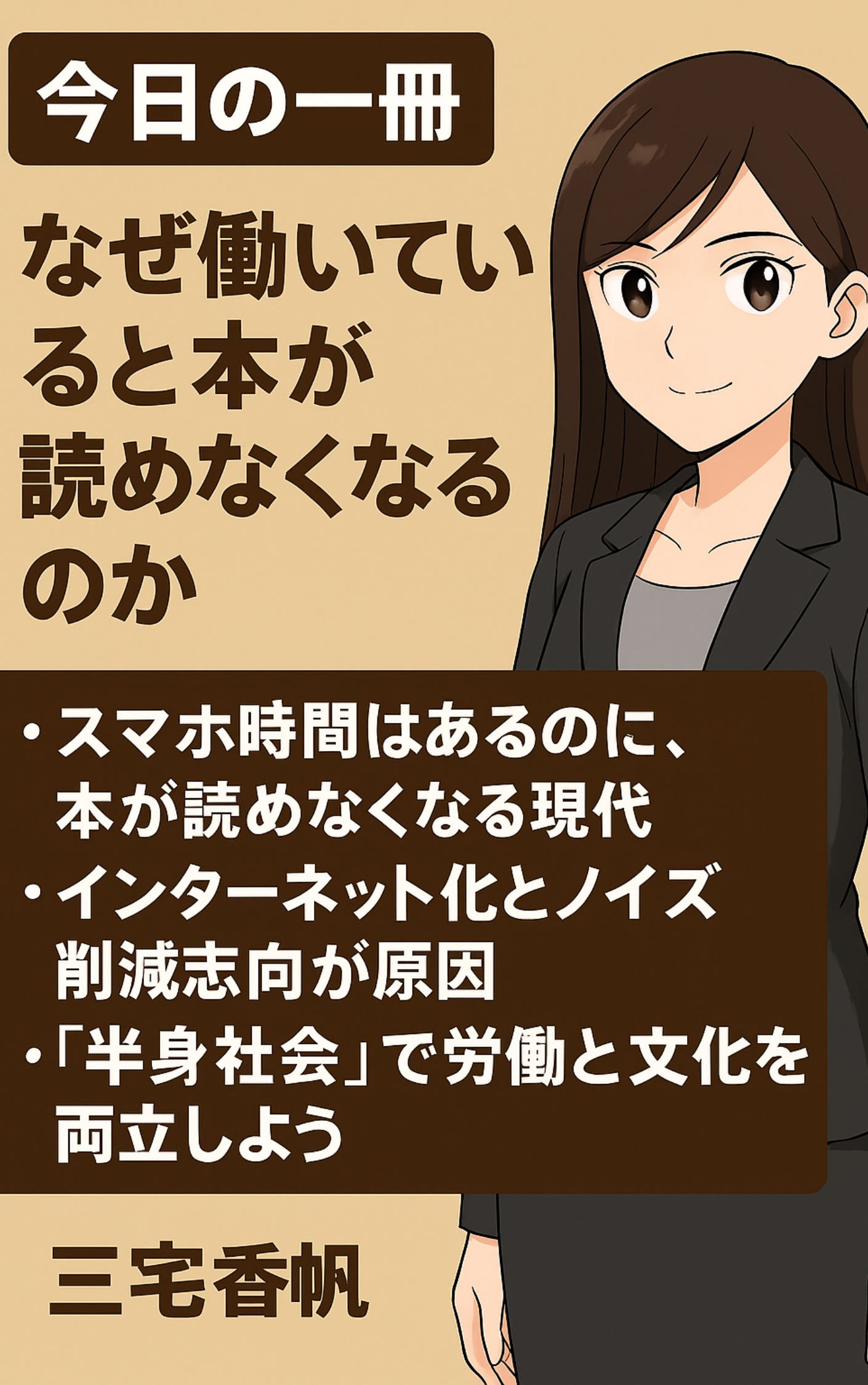


コメント