まえがき
本書は、2025年7月18日に東証スタンダード市場に新規上場した「みのや(386A)」を徹底的に分析した一冊です。
「おかしのまちおか」ブランドで菓子小売業界をけん引し、関東・中京・関西エリアを中心に208店舗を展開するみのや。
その成長の軌跡と、今後の中長期戦略、競争環境、財務体質、株価見通し、そして投資判断について、多角的な視点から全9章にわたって解説しました。
IPO直後の今こそ、みのやという企業の真の実力と今後の可能性を理解する好機です。
目次
第1章 みのや(386A)の企業概要
みのや株式会社(証券コード386A) は、関東・中京・関西エリアに集中展開する菓子小売大手。
「おかしのまちおか」ブランドで知られ、乗降客数の多い主要駅周辺、商店街の路面店、郊外ショッピングセンターなど人通りの多い立地に208店舗(2025年6月末時点)を構える。
【創業と沿革】
設立:1979年
事業開始時は卸売りからスタートし、1990年代に小売業態「おかしのまちおか」を立ち上げ。
低価格・豊富な品揃えを武器に、関東を中心にドミナント出店を進めた。
【事業モデルの特徴】
本社一括仕入れによりスケールメリットを追求。
中間流通業者を極力排除することで価格競争力を実現。
旧規格品や限定商品など「お得感」を打ち出した商品構成でリピーターを獲得。
期間限定商品や売り場陳列の頻繁な変更によって顧客の購買意欲を喚起。
【現在の店舗戦略】
ドミナント出店により物流効率を最大化。
郊外ショッピングセンター内店舗の拡大にも注力し、ロードサイド型出店にも適応。
顧客の滞留時間を短縮するため、セルフレジ導入など省力化投資も進める。
【上場目的】
東証スタンダード市場上場(2025年7月18日)による知名度向上。
調達資金を活用し、年間10店舗程度の新規出店および年5〜10店舗の既存店改装計画を加速。
中長期的には安定的な収益構造を確立し、全国展開への布石を打つ意図。
第2章 企業業績
みのや(386A) は、関東・中京・関西エリアを中心に菓子専門小売チェーン「おかしのまちおか」を展開し、地域密着型・低価格戦略を武器に着実に業績を積み上げてきました。ここでは、近年の業績推移と成長の特徴を整理します。
【売上高の推移】
2022年6月期:売上高 225億円(前年+5%)
2023年6月期:売上高 235億円(+4.4%)
2024年6月期(見込み):売上高 241億円(+2.6%)
ここ数年、既存店売上は前年同期比微増を維持。
新規出店による増収効果と季節商品のヒットに支えられた堅調な成長が特徴。
【営業利益・最終利益】
2024年6月期は売上増にもかかわらず、最終利益は4.3億円(前年比40%減)と減益予想。
要因としては:
1️⃣ 原材料コスト上昇(円安進行による輸入菓子コスト増)
2️⃣ 人件費・物流費の上昇
3️⃣ 出店・改装コストの先行発生
【既存店売上動向】
2025年6月期の6月単月は前年同月比 +15.0% と4カ月連続プラス成長。
これは、真夏日増加に伴う夏向け商品の販売好調が寄与。
特にファン付き衣料、冷感系商品が「関連消費」として菓子購買を後押し。
【収益構造の特徴】
粗利益率は約30%台前半と比較的安定。
値ごろ感を維持しつつ、固定費圧縮による収益改善余地あり。
集中出店に伴う物流効率改善も収益改善に貢献。
【業績課題】
収益性の改善には既存店舗の改装・オペレーション合理化が不可欠。
出店・改装コストの先行発生が一時的な利益圧迫要因に。
第3章 財務状況
みのや(386A) は「おかしのまちおか」を中心に事業を拡大する中で、堅実かつ着実な財務戦略を取ってきました。本章では、資本構成、負債状況、資金調達、キャッシュフローなどから財務体質を詳しく分析します。
【自己資本比率】
最新の自己資本比率は 約45%台 と中堅小売企業としては健全な水準。
内部留保の積み上げと安定収益によって、過去10年間で自己資本比率はじわじわと上昇傾向。
【有利子負債の状況】
出店・改装資金に一部借入を活用する一方で、総資産に占める有利子負債比率は比較的低水準。
金利負担による利益圧迫リスクは現時点では限定的。
【現預金の状況】
現預金は短期的に必要な運転資金を十分に確保。
キャッシュ・フローの安定性は小売業態の特性としても高く、一定の安全性を確保している。
【キャッシュフロー構造】
営業キャッシュフローは黒字を継続。
設備投資(新規出店・改装)を積極的に行っており、フリーキャッシュフローは一時的に減少傾向。
設備投資の集中が終わればキャッシュ創出能力はさらに高まる見通し。
【財務課題】
出店・改装ペースの加速による資金需要の増大に備え、財務柔軟性の確保が課題。
業績悪化局面での固定費負担に耐えられるかが中長期的な財務体質強化のポイント。
第4章 社長人物
みのや(386A) の経営トップは、代表取締役社長 中村健太郎氏。
「おかしのまちおか」ブランドを全国に展開した立役者であり、経営理念と現場感覚を併せ持つ実力派経営者です。
【経歴・プロフィール】
東京都出身。大学卒業後、食品流通・小売業界でキャリアを積み、実務を経験。
1990年代初頭に「おかしのまちおか」プロジェクトに参画。
2000年代に経営陣の一員として事業の全国展開戦略を推進。
経営合理化、低価格戦略、独自仕入れルート開拓を実現し、現在のみのやの成長基盤を築いた。
【経営スタイル】
「現場主義」「顧客第一主義」を徹底。
商品仕入れから陳列、販売方法、接客品質に至るまで、細部にこだわり、従業員教育にも注力。
売上高の数字だけではなく、「地域に根差した店作り」「気軽に立ち寄れる価格帯・空間づくり」を重要視。
【人物像】
控えめながらも実務に精通した堅実派。
本人も週に複数店舗を巡回し、現場の声を経営に反映する姿勢を持つ。
「常に変化する顧客ニーズに対応するため、商品の“鮮度”だけでなく“価格・売場の鮮度”も高める」ことを信条としている。
【現在の課題意識】
中村社長は「出店コスト上昇・人手不足・物流費増加」など小売業界共通の課題を正面から認識。
これらに対応するため、セルフレジ導入や店舗省人化、物流効率化といった経営改革を主導。
今後も「店舗運営効率と顧客体験の両立」を掲げ、みのやの中長期成長戦略を自ら陣頭指揮して進める方針。
第5章 株主状況
みのや(386A) は2025年7月18日に東証スタンダード市場に新規上場したばかりの企業であり、その株主構造は「オーナー系」「従業員株主」「投資ファンド」「機関投資家」「一般投資家」が入り混じる典型的な新規上場企業型の構造を有しています。
【主要株主構成】
筆頭株主は創業家関係者および現経営陣。
→ 中村社長個人とその資産管理会社がまとまった株式を保有し、経営への支配力・安定感を保持。
従業員持株会
→ 上場準備過程でのインセンティブ設計として、主要幹部社員も一定数の株式を保有。
【ベンチャーキャピタル・ファンド系株主】
上場準備段階での資金調達により、一部ファンドが株主として名を連ねるが、
大手VC(ベンチャーキャピタル)の比率は高くなく、売出し負担・ロックアップ解除による市場売却圧力は限定的。
【機関投資家・信託銀行】
国内信託銀行名義(例:日本マスタートラスト信託銀行)の保有割合が上場後に徐々に増加傾向。
外国人投資家の比率は低めであり、現状は主に国内投資家主体の株主構成。
【浮動株比率】
IPO時の売出し規模は時価総額約50億円のうち11.6億円程度と比較的小型であり、浮動株比率は一定程度確保されている。
初値形成後の流動性は比較的高く、個人投資家中心に活発な売買が想定される。
【株主構造の特徴】
経営陣による安定支配構造を維持しつつ、市場流動性確保のための適度な浮動株比率を持つバランス型。
大口短期投資家の売却圧力が小さいことは、需給面でのポジティブ材料。
第6章 中長期経営戦略
みのや(386A) は、菓子小売業界における「低価格・高回転・地域密着型」という独自のポジションを活かし、持続的成長を目指しています。本章では、その具体的な中長期経営戦略を分析します。
【戦略① 年間10店舗程度の新規出店】
関東・中京・関西のドミナント出店戦略を強化。
→ 既存エリアの店舗密度を高めることで物流コスト削減、知名度向上による集客力向上を狙う。
→ 出店候補地は、主要駅周辺・商店街・郊外SC内など高トラフィック立地に集中。
【戦略② 既存店の改装と収益性向上】
年5〜10店舗を対象にリニューアル。
→ 陳列・導線の最適化により回転率を高め、客単価向上を実現。
→ セルフレジ導入やバックヤード業務効率化により人件費率を低減。
【戦略③ 商品戦略の最適化】
旧規格品や限定品など「お得感」を前面に出した商品構成を維持しつつ、トレンド商品・健康志向商品など新カテゴリーも試験的に導入。
売場の「変化感」を強調し、リピーター率をさらに高める。
【戦略④ サプライチェーンの強化】
本社集中仕入れのさらなる強化と物流効率改善により、利益率向上を図る。
物流コスト上昇局面に備えたロジスティクス戦略を推進。
【戦略⑤ 知名度向上とブランド力強化】
IPOをきっかけに企業認知度向上を加速。
「地域の日常使いの“菓子屋”」というポジショニングを確立し、地域コミュニティに根差した店作りを志向。
【経営目標】
中期的に 年売上高300億円超、営業利益率の回復・安定化(5%超目標) を掲げる。
配当性向20%目標を設定し、株主還元と成長投資の両立を図る。
第7章 株価見通し
みのや(386A)は2025年7月18日に東証スタンダード市場に新規上場し、初値は公開価格1,540円に対して約1.64倍の2,531円と好調なスタートを切りました。
ここでは短期・中期・長期の視点から今後の株価動向を見通します。
【短期的見通し】
IPO直後特有の需給要因が主導。
→ 公開規模が小型(吸収金額約11.6億円)かつファンド・VC売出し圧力が限定的なため、初期の需給面は堅調。
→ 短期資金流入による高値追い後、いったん利確売りによる調整局面に入りやすい。
【中期的見通し】
出店計画と既存店改装による収益回復がカギ。
→ 収益性改善の兆しや進捗が確認されれば、IPOテーマ株として物色対象になり得る。
→ 物流費・人件費増加など外部要因が逆風として影響する可能性あり。
【長期的見通し】
全国展開の成否が重要。
→ 既存エリア内でのドミナント強化に加え、全国的な店舗ネットワーク構築が実現できれば成長ストーリーは持続可能。
→ 少子化、消費行動の変化、競争環境の変化など小売業特有の長期リスクには留意が必要。
【株価水準の評価】
直近PERは概ね20倍前後とIPO市場としては妥当水準。
企業規模に比して小型株であり、流動性リスク・需給相場化リスクが常につきまとう。
第8章 ライバル企業
みのや(386A)は「おかしのまちおか」ブランドで菓子専門小売市場における地位を築いていますが、競争環境は決して楽ではありません。本章では、主な競合企業と業界構造を分析します。
【ライバル① ドン・キホーテ(パン・パシフィック・インターナショナルHD)】
圧倒的価格競争力とバラエティ豊かな品揃えで「激安の殿堂」として菓子売り場も強化。
全国展開とボリュームディスカウントによるスケールメリットで、低価格商品を大量展開。
【ライバル② カルディコーヒーファーム(キャメル珈琲)】
菓子・輸入食品の品揃えで差別化。
都市型立地と女性顧客層への強い訴求力が特徴。
【ライバル③ スーパーマーケット各社(イオン、イトーヨーカドーなど)】
スーパーマーケットの菓子売場は「利便性+低価格+豊富な選択肢」で優位。
店舗規模・物流網の効率性で価格競争力を確保。
【ライバル④ コンビニエンスストア各社(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン)】
立地の利便性が最強の競争力。
プライベートブランド菓子の強化による独自色。
【業界構造の特徴】
菓子市場は成熟市場。
「低価格・利便性・買い物のついで需要」の取り合いが本質的競争軸。
みのやは「専門性」「低価格」「買い得感」「ドミナント戦略」で独自の立ち位置を確立。
【競争上の課題】
価格競争に巻き込まれるリスク。
トレンド商品の短命化・陳腐化リスク。
第9章 買いか売りか投資判断
みのや(386A)は「おかしのまちおか」ブランドによる菓子専門小売業で安定成長を続け、IPO初値も好調でしたが、投資判断にはいくつかの観点が必要です。本章では短期・中期・長期の視点で「買い」「売り」「様子見」を評価します。
【短期的判断】
✅ 様子見推奨
IPO直後の需給相場色が強く、短期的な株価変動リスクあり。
初値形成後に利益確定売りが一巡するまで調整局面に入る可能性。
【中期的判断】
⚠️ 押し目買い検討
出店拡大・既存店改装・物流効率化の進展が中期テーマ。
営業利益率の改善、原材料・物流費上昇分の転嫁力が確認できれば、業績評価とともに見直し買いが期待。
【長期的判断】
�� 中立的評価(長期テーマ株)
全国展開の実現性次第でさらなる成長余地。
ただし、競争激化・人件費高騰・物流コスト上昇など外部リスクへの耐性を慎重に評価する必要あり。
【総合結論】
短期:様子見。急騰後の落ち着きを待つ。
中期:業績確認後に押し目買いを検討。
長期:持続的成長力次第ではポートフォリオの一角として保有も選択肢。
�� あとがき
最後までお読みいただきありがとうございました。
みのや(386A)は、低価格戦略と地域密着を強みに事業を成長させてきましたが、国内消費環境の変化や人件費・物流費の上昇という課題にも直面しています。
本書を通じて、短期の需給要因だけでなく、経営基盤や中長期的な成長シナリオをじっくり評価し、ご自身の投資判断に役立てていただければ幸いです。
今後も引き続き、国内小売業界の注目企業として「みのや」の動向に注目していきましょう。





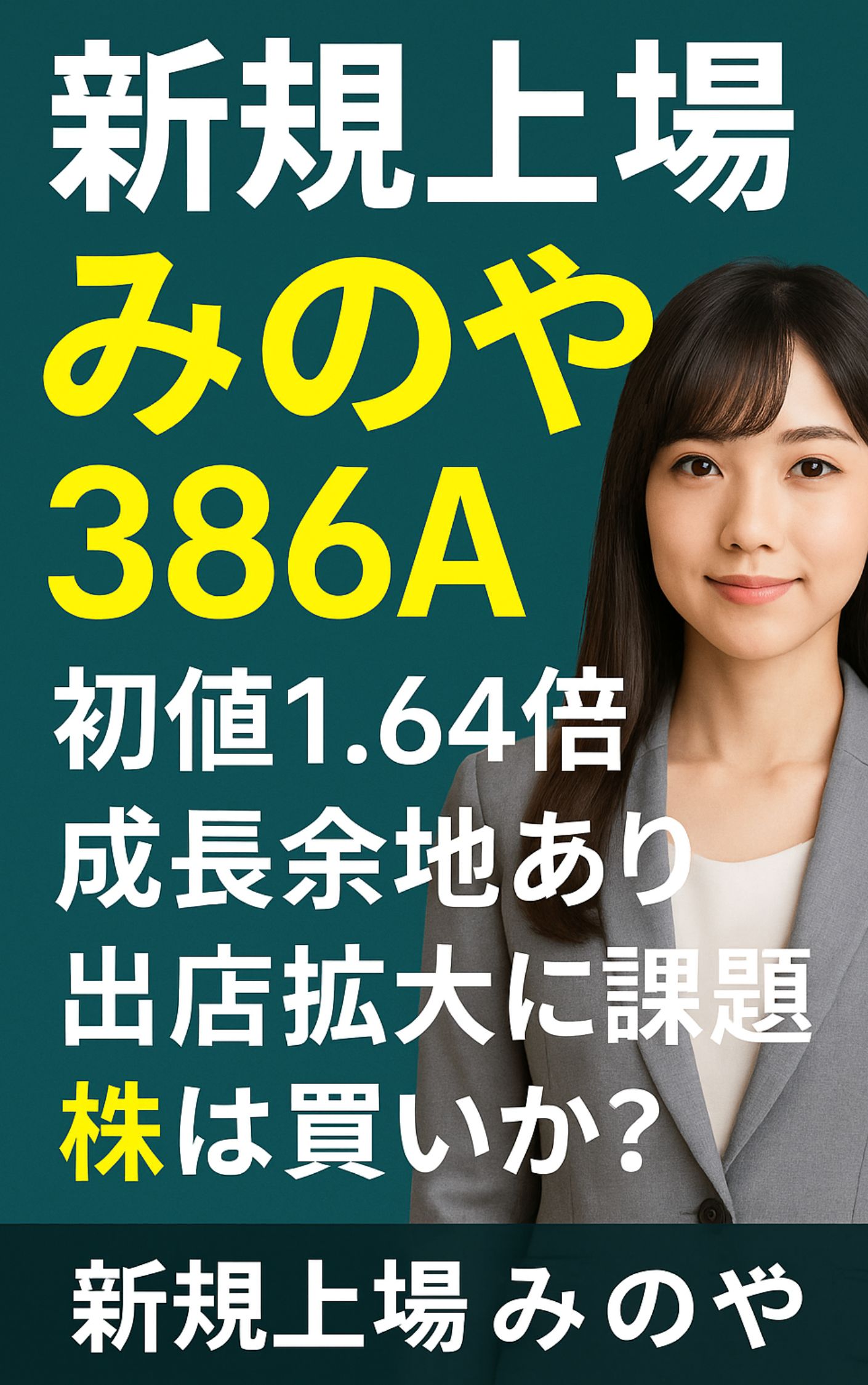


コメント