まえがき
「女王は、ただ美しかったのではない――歴史を動かした。」
古代エジプト最後のファラオ、クレオパトラ。
彼女の名は、二千年を超えてもなお、神話のように語られる。
美貌、知性、戦略、愛。
そのすべてを武器に、ローマという世界帝国と渡り合った唯一の女性君主。
しかし、そこにあるのは単なる浪漫ではない。
彼女は「国家を生かすために愛を使い、国を守るために命を懸けた」リアルな存在だった。
本書では、
クレオパトラの全人生を、政治・外交・文化・思想から立体的に描く。
歴史の中に埋もれた「本当のクレオパトラ」を掘り起こし、
現代に生きる私たちにとっての「自立」と「選択」の意味を問う。
目次
第5章 愛と政治の交差点 ― マルクス・アントニウスとの同盟
登場人物一覧
| 名前 | 役割・紹介 |
| クレオパトラ7世 | 本書の主人公。プトレマイオス朝最後の女王。 |
| カエサル | ローマの英雄。クレオパトラとの関係がエジプトの運命を変える。 |
| プトレマイオス13世 | クレオパトラの弟で共治者。内戦の相手。 |
| マルクス・アントニウス | ローマの将軍。クレオパトラの盟友で恋人。 |
| オクタウィアヌス(後のアウグストゥス) | アントニウスの政敵。クレオパトラを滅ぼした男。 |
| セラピオン | 宮廷の宦官・助言者。 |
| アルシノエ4世 | クレオパトラの妹。反乱を起こす。 |
第1章 ナイルのほとりに生まれて
紀元前69年、エジプトのアレクサンドリア。地中海に面したこの都市は、当時世界でも有数の文化と交易の中心地だった。そこに生を受けた一人の少女が、後に世界史にその名を刻むことになる。
彼女の名はクレオパトラ・フィロパトル。プトレマイオス朝最後の女王となる運命を背負ったその存在は、誕生の瞬間からすでに政治と権力の渦の中にあった。
クレオパトラの一族――プトレマイオス家は、アレクサンドロス大王の死後にエジプトを治めることとなったマケドニア系ギリシア人の王朝である。エジプト人とは文化も言語も異なるこの王家は、数世代にわたりギリシア語を話し、ギリシア文化に親しみながら、ナイルの土地を支配してきた。
だが、クレオパトラは違った。彼女はギリシア語だけでなく、エジプト語を学び、現地の神々を敬い、ナイルの民と共に生きようとした。女王としての資質は幼いころから顕著で、歴史学者たちは、彼女の知性と教養の深さ、そして政治への鋭い洞察を早くから認めていたと語る。
その時代、エジプトはすでにローマ帝国の圧力を受けていた。プトレマイオス朝の王位継承は複雑で、陰謀と裏切りに満ちていた。クレオパトラが成長するにつれ、王宮の中には常に緊張が走っていた。
幼いながらも、彼女はその渦中で目を凝らしていた。王族の女性として、ただ美しくあるだけでなく、言葉の力と知性によって自らの道を切り開こうとする彼女の姿勢は、他の王女たちとは一線を画していた。
教育はギリシアの哲学、数学、天文学、修辞学に加え、古代エジプトの宗教と歴史にも及んだ。クレオパトラの「言葉の力」はここで磨かれ、後のカエサルとの会話、アントニウスとの交渉、そしてローマ元老院への働きかけに繋がっていく。
アレクサンドリアの図書館――当時最大の知の宝庫であったこの場所に、彼女は足繁く通ったという。宮殿から抜け出し、一般市民に混じって古代文書に触れた少女の眼差しは、やがて世界帝国との対峙に向かう王の眼差しへと変わっていく。
父プトレマイオス12世アウレテスは、ローマの支援を受けて王位を維持していたが、その対価として多額の貢ぎ物を贈るなど、エジプトの財政は傾いていた。王国は外からも内からも揺らぎつつあった。
その中で、クレオパトラは「知の女神」としての自覚を深める。彼女にとって政治とは、血と剣ではなく、言葉と象徴の力で国を導くことであった。
この章の終わりに、アレクサンドリアの港に沈む夕陽の描写が残っている。赤く染まる空の下、少女はナイルを見つめながら、小さくこう呟いたという――
「私の時代が来る」
それは、運命を自らの手に取り戻そうとする者の確信に満ちた、未来への宣誓だった。
第2章 ナイルの姫、政争の渦へ
アレクサンドリアの港町は、朝もやの中で静かに目を覚まし始めていた。帆船のマストが風にきしむ音、商人の怒声、遠くの神殿から聞こえる祈祷の歌声――そのすべてが、地中海の十字路であるこの都市の鼓動だった。
クレオパトラは、まだ十代の少女だったが、すでに「言葉」と「知恵」が武器であることを知っていた。彼女は父プトレマイオス12世の許で、ギリシア語、ラテン語、エジプト語、さらにはヘブライ語、アラム語、ペルシャ語までを習得した。代々のプトレマイオス朝ファラオが軽んじてきたエジプト語を、彼女はむしろ愛した。
だが、王宮の中に流れる空気は、どこか冷ややかだった。
父王は、ローマに過度に依存し、財政は破綻寸前だった。重税に苦しむ市民たちの怒りは、やがて王権そのものに向かい、王族たちも互いを疑い合っていた。クレオパトラの姉ベレニケ4世は、すでに父に反旗を翻し、クーデターを画策していた。
その年、プトレマイオス12世はローマに逃れた。王国は、若きベレニケの手に渡る。そしてそのベレニケに立ち向かう形で、クレオパトラは初めて「王宮政治の闇」に身を投じることになる。
彼女は、戦士ではなかった。剣も槍も使えない。だが、言葉と微笑み、沈黙と観察、そして完璧なタイミングで真実を突く知性――それらは、剣よりも鋭く、盾よりも堅牢だった。
クレオパトラは、ベレニケ陣営に潜り込み、内部から情報を得た。王宮の使用人、宦官、神官――すべての人間関係を彼女はつぶさに観察し、やがて決定的な「密書」を握った。それをローマへ逃れた父王の元へ送る。
2年後、父王はローマの軍勢と共に帰還する。ベレニケは処刑され、王権は復古する。
この瞬間、まだ15歳だったクレオパトラは「王の娘」から「王の影」へと変貌した。
だが、彼女はまだ知らなかった。
この政争は、ほんの序章にすぎないということを。
そして、さらに大きな渦――ローマの内乱とカエサルの登場が、彼女の人生を大きく揺るがすことになるということを。
第3章 ローマから来た男 ― カエサルとの邂逅
紀元前48年、地中海世界を震撼させる嵐が吹き荒れていた。
ローマではカエサルとポンペイウスの内戦が勃発し、共和政ローマの均衡は崩壊の瀬戸際にあった。
その波は、ナイルの女王が統治するエジプトにも容赦なく押し寄せた。
クレオパトラは、父王の死後、弟プトレマイオス13世と共同統治者となったものの、実権を巡る争いは激化していた。まだ10歳そこそこの弟は、宦官ポテイノスをはじめとする有力廷臣たちに操られており、クレオパトラを王宮から追放する工作が密かに進められていた。
――クレオパトラは再び都を追われた。
だが、彼女は「待つ」ことを選ばなかった。
彼女はただちにシリア方面へ向かい、傭兵を集め、王位回復の準備を整えた。
だが同時に、彼女の胸に芽生えていたのは、力による奪還ではなく、もっと巨大な権力を「味方にする」ことだった。
そこへ――運命の男が現れた。
ローマの将軍ガイウス・ユリウス・カエサル。
アレクサンドリアに入ったカエサルは、エジプト王家に王位争いを即時停止するよう命じ、両者を対面させることを命じた。
王宮の片隅。
クレオパトラは、夜陰に紛れて密かに運び込まれた。
彼女は豪華な絨毯の中に身を包み、女官の手によってカエサルのもとへと運び入れられたのだ。
カエサルの目前で、巻物がほどかれ、黒髪の若き女王が姿を現す。
その瞬間――時代が変わった。
カエサルは驚き、やがてその瞳に宿る知性と覚悟に魅了された。
彼女はただ美しいだけではない。
ローマにとっても必要な秩序と安定をもたらす存在――そのことを、老将軍は即座に理解した。
翌朝には、カエサルはクレオパトラの共同統治の正当性を宣言した。
これに激怒したポトイノスは武力蜂起を画策。
エジプトは内乱へと突入し、カエサルとクレオパトラは、アレクサンドリア宮殿に立て籠もる形で戦いを迎え撃った。
数週間の攻城戦。
炎上する王立図書館。
燃える街。
迫る死の影。
だが、カエサルの軍略とクレオパトラの不屈の意思がそれを退けた。
やがて増援が到着し、敵勢力は敗退。
プトレマイオス13世はナイルに沈み、クレオパトラは新たに弟プトレマイオス14世との共同統治者として即位することになった。
彼女は、ただ「王に選ばれた」のではない。
自らの知略と行動で、「ローマを動かし、王になった」のだった。
この時、カエサルとの間には、すでに新しい命が芽生えていた。
その名はカエサリオン。
そして、彼女の運命は――さらに深く、ローマと結びついていく。
第4章 カエサルの女王 ― ローマでの栄光と孤独
クレオパトラがアレクサンドリアの玉座に返り咲いた後も、エジプトは静かではなかった。
政治の安定は見かけのものであり、実態はローマの庇護下にある「従属王国」に近い存在。
しかしクレオパトラは、それをよしとしなかった。
彼女は、自らの意思でこの関係を「対等」にしようと考えた――それが、彼女を再びローマへと導いたのである。
紀元前46年。
クレオパトラは、カエサリオンを伴い、カエサルの招きでローマへ渡る。
その登場は、まさに“現代のイシス神の降臨”とまで称された。
エキゾチックな服装、堂々たる態度、洗練された修辞――
多くのローマ市民が、この異国の女王に目を奪われ、そして戸惑い、畏れすら抱いた。
クレオパトラは、カエサルの私邸に滞在することを許され、まるで“ローマのもうひとつの女王”としての振る舞いを見せた。
だがそれは同時に、保守派の元老院やカエサルの政敵にとっては耐えがたい挑発だった。
ローマ市内には、カエサルとクレオパトラ、そしてカエサリオンの像が並んで建てられた。
「王政復古の気運」がささやかれ、共和政ローマの理念を重んじる人々は震撼した。
特にカエサルが終身独裁官の地位を得たことで、「王への野望」が疑われたのだ。
そして――悲劇が訪れる。
紀元前44年3月15日。
ローマ元老院の会場、ポンペイ劇場。
“イドゥスの3月”の日、カエサルは暗殺された。
23回の刃。
その多くは、かつての信頼の証として与えた者たちによるものだった。
クレオパトラは、呆然とするローマの空気の中で、その死を知った。
彼女はただちに宮邸を離れ、息子を抱えて静かにナイルへと帰還する。
泣き叫ぶこともなく、哀悼を公言することもなく、ただ沈黙のまま。
だが彼女の心には、はっきりとした決意が宿っていた。
カエサリオン――この幼い子こそ、カエサルの血を継ぐ「真の後継者」。
ローマの地に散った愛と権力の証を、自らが守り抜くのだと。
ナイルに戻った彼女は、より強く、より賢くなっていた。
ローマで得た知識、政治術、人心掌握術を駆使し、エジプトの体制を再編する。
彼女は、もはや「美貌の女王」ではなかった。
「知と力を持つ女王」へと変貌していた。
カエサルの死から生まれた空白。
そこに名乗りを上げる者たちが現れる。
――マルクス・アントニウス。
――オクタウィアヌス(のちのアウグストゥス)。
だが彼女は、恐れなかった。
むしろ、その渦中に身を投じ、もう一度「ローマを動かす」覚悟を抱いていた。
物語は、再びローマとの交差へと進む。
第5章 愛と政治の交差点 ― マルクス・アントニウスとの同盟
紀元前41年。
ナイルの女王は再び、ローマの政治劇へと歩を進める。
だが今回は、ローマが彼女を呼んだのではなかった。
彼女自身が、ローマの心臓を揺るがす準備を整え、舞台に立ったのである。
カエサルの死後、ローマは再び動乱の渦に巻き込まれていた。
カエサルの後継者を自認するオクタウィアヌスと、実力派軍人マルクス・アントニウス、
そしてライバルたちの間で三頭政治が成立し、ローマは表面上の平静を保つ。
だがその裏では、権力の座をめぐる激しい駆け引きが続いていた。
そんな折、アントニウスはクレオパトラを召喚する。
彼女がカエサルの遺産――つまり「カエサリオン」を抱えているということ、
そしてエジプトの富と軍が戦略的に重要であることを理解していたからだ。
クレオパトラは、慎重に準備を進めた。
アレクサンドリアからタルソスへの旅路。
豪華な黄金の船、香を焚きしめた帆、輝く衣装に身を包み、
彼女はイシス神の化身として、ゆっくりと川を上って現れた。
アントニウスは息を呑む。
戦場で何度も死地をくぐった英雄が、女王の一瞥に言葉を失った。
それはただの美ではなかった。
威厳と知性、そしてどこか憂いを帯びた神聖さが彼女を包んでいた。
クレオパトラはアントニウスに歩み寄る。
それは「服従」でも「誘惑」でもなかった。
対等なる者として、彼女はアントニウスに語りかけたのだ――
「ローマの未来に、エジプトの知恵と力を与えましょう」と。
この出会いは、両者にとって運命的なものとなる。
政治的な同盟は、やがて私的な愛へと転じ、
ふたりは戦略と情熱を重ねながら、世界の再編を夢見るようになる。
アレクサンドリアに帰還したクレオパトラとアントニウスは、
古代世界における“新たな帝国の核”を構築しようとする。
エジプトの富とローマの軍、知と剣の結合。
その中心にいたのが、クレオパトラのカリスマだった。
だが、ローマは冷ややかだった。
アントニウスは妻をローマに残し、エジプトの女王と暮らしている――
それはスキャンダルであり、裏切りと見なされた。
オクタウィアヌスは、この状況を利用し、次なる戦いの口実を練っていた。
クレオパトラは知っていた。
この愛が、ローマを分断するナイフとなりうることを。
だがそれでも彼女は、アントニウスを選んだ。
女王は賭けに出たのである。
それは「愛の賭け」ではなく、「未来の賭け」だった。
第6章 栄光と脅威 ― 東方の夢とローマの怒り
アレクサンドリア――地中海世界の知と富が集まる都。
そこに、クレオパトラとアントニウスは「新たなローマ」を築こうとしていた。
彼らは政治と愛を両輪にして、古代世界を再構築しようとした。
アントニウスは東方統治を強化する一方、
クレオパトラはその背後で外交と財政、宗教政策を操る。
ふたりの間には3人の子が生まれ、エジプトとローマの「新たな王朝」を象徴する存在となった。
この時期、アントニウスはローマ元老院の命令を無視し、
アルメニア遠征を断行、王族を捕虜として連れ帰り、アレクサンドリアで盛大な凱旋式を挙行した。
彼はローマの伝統を逸脱し、アレクサンドリアを新たな「帝都」に仕立てあげたのだった。
そして決定的な事件が起きる。
「アレクサンドリアの布告」――
アントニウスはクレオパトラを「女王中の女王」と宣言し、
息子たちにはアルメニア、メディア、シリアといった東方の王国の支配権を与えた。
これはローマにとって、まさに「挑戦状」であった。
オクタウィアヌスはこの行動を「反ローマ的」と断じ、
アントニウスに妻(オクタウィアヌスの姉)を返せと迫るが、彼は拒否。
ローマは、もはや「東の女」と結託したアントニウスを、
カエサルの正統な後継者とは見なさなかった。
元老院は動く。
オクタウィアヌスはアントニウスを「国家の敵」とし、
戦争の大義名分を得る。
だがこの「戦争」は、ローマ対アントニウスではなかった。
オクタウィアヌスは巧みに構図を変えた。
「これは、ローマ対エジプト、
すなわち――クレオパトラとの戦いである」と。
女王が直接、ローマの敵として位置づけられた瞬間だった。
クレオパトラは知っていた。
この戦争が「政治」ではなく、「象徴」の戦いになることを。
東方の栄光と、女王という存在そのものが、
ローマの男性支配を脅かす異物として描かれていたのだ。
だが彼女は退かない。
アントニウスと共に戦うと決めたその日から、
彼女はエジプトと自らの運命を重ね合わせていた。
アレクサンドリアでは戦の準備が進む。
だが海の向こうでは、ローマの大軍が静かに牙を研いでいた。
戦乱の嵐が、ついに近づいてくる。
第7章 アクティウムの戦い ― 帝国の黄昏
紀元前31年9月2日――
ギリシア西岸、アクティウムの海にて。
地中海を二分する歴史的な海戦が幕を開けた。
片や、オクタウィアヌス率いるローマ艦隊。
堅実で統制された布陣に、アグリッパという名将が指揮を執る。
片や、アントニウスとクレオパトラの連合艦隊。
数では劣らぬも、統率に乱れが生じ、士気に陰りがあった。
この日、海は静かだった。
だが、歴史が揺れた。
開戦直後、アントニウスの艦は奮戦を見せるが、
中央の突破に失敗し、側面からアグリッパ軍の攻撃を受ける。
混乱のさなか、クレオパトラの黄金の艦船が突然、戦場を離脱――
南へ向かって全速で撤退を始めたのだった。
これは裏切りだったのか?
それとも、最初から決められていた作戦だったのか?
真実は今もなお歴史の霧の中にある。
だが、アントニウスはそれを追った。
戦線を放棄し、女王の後を追い、戦場を離れた。
その瞬間、連合軍の士気は崩壊し、戦は終わったも同然だった。
敗北。
それは軍事的なものだけでなく、
ローマ世界における「正統性」の喪失でもあった。
オクタウィアヌスは勝利者となり、
「ローマの守護者」「共和政の再建者」として賞賛を浴びる。
実際には皇帝政の始まりだったにも関わらず。
クレオパトラとアントニウスは、エジプト・アレクサンドリアへと帰還する。
だがその都も、すでに死の気配に包まれていた。
クレオパトラは城塞にこもり、
過去の記録と星の運行を調べる日々を送る。
自らの運命が、いかにして神話へと繋がっていくかを計算しているかのようだった。
ローマの大軍は静かに近づいていた。
アクティウム――
それは単なる戦いではなかった。
ローマの未来と、エジプトの終焉と、
一人の女王の夢が砕ける瞬間だった。
クレオパトラはそれを受け入れた。
だが、屈するつもりはなかった。
第8章 アレクサンドリアの終焉 ― 女王の最期
アクティウムの敗戦から一年。
紀元前30年、ローマの大軍はナイル川を下り、ついにアレクサンドリアへ到達する。
かつて学問と芸術の都と称されたこの都市も、
もはやその輝きを失っていた。
宮殿の壁はひび割れ、民衆は不安に沈黙していた。
ローマの旗が、港の灯台から翻るのも時間の問題だった。
クレオパトラは最後まで戦略を考え抜いた。
「降伏すべきか。生き残るべきか。女王として死ぬべきか。」
アントニウスは絶望の淵にあった。
忠臣を失い、軍も民心も去り、ただ女王だけがそばに残った。
やがて、誤報が届く――
「クレオパトラが死んだ」と。
この報せを聞いたアントニウスは、
短剣を胸に突き立て、自ら命を絶とうとした。
だが死にきれず、瀕死の体で、クレオパトラのもとに運ばれる。
神殿の奥、香の薫る部屋で、
アントニウスはクレオパトラの腕の中で息絶えた。
女王は泣いた。
だが涙の意味は、誰にもわからなかった。
――数日後。
オクタウィアヌスが宮殿に入った。
彼はクレオパトラを生かしてローマに連れ帰ろうとした。
凱旋式の見せ物にするために。
だが、女王はそれを拒んだ。
自らの死を演出し、神話として生きる道を選んだ。
毒蛇――アスプ――
あるいは、猛毒の香油、あるいは秘密の短剣。
その方法は謎に包まれている。
ただ、クレオパトラはローマの目の前で、
静かに、その命を閉じた。
彼女のそばには、
金の髪飾り、アントニウスの肖像、
そして最後の詩が残されていたという。
その死は、単なる終わりではなかった。
クレオパトラは、自らの死をもってローマに挑み、
永遠の存在となった。
第9章 女王の再生 ― クレオパトラ神話の誕生
クレオパトラの死は、
エジプトの終焉であり、プトレマイオス王朝の幕引きだった。
だが、その死は同時に、
一つの「物語」の始まりでもあった。
ローマが創った「妖婦」
オクタウィアヌス(後のアウグストゥス)は、
クレオパトラを「国家を惑わす東方の魔女」として語った。
アントニウスを堕落させた異国の女王。
ローマの秩序を乱した危険な存在。
それはローマにとって必要な「物語」だった。
自らの支配を正当化するための、
「東洋の悪女」という記号。
凱旋式では、女王の彫像が鎖に繋がれ、
群衆の前に晒された。
だが、それがクレオパトラ本人ではないことを、
誰もが知っていた。
死してなお、彼女はローマを翻弄していたのだ。
東方での神格化
一方、エジプトでは違った。
彼女は「イシスの化身」として崇められた。
神殿にはクレオパトラの名が刻まれ、
人々の口承で、その美しさと知恵が語り継がれた。
アレクサンドリアでは、
「彼女は死んではいない。
ナイルの底で、再び王国を築いている」と囁かれた。
クレオパトラは神話となり、信仰となった。
中世・近世の再発見
時が流れ、ヨーロッパ中世。
クレオパトラは「堕落の象徴」として語られる。
ダンテの『神曲』には、地獄の一角で呻く彼女の姿がある。
しかし、ルネサンスに入ると、
その知性と権力の象徴として再評価され始める。
ウィリアム・シェイクスピアは『アントニーとクレオパトラ』で、
気高き女王として彼女を描いた。
やがて、ナポレオンのエジプト遠征によって、
アレクサンドリアの遺跡が発掘され、
クレオパトラの名は再び世界に響くようになる。
現代における象徴
20世紀には、映画『クレオパトラ』(1963年)によって、
エリザベス・テイラーが彼女を演じ、
新たな女王像が定着した。
美貌、知性、恋愛、戦略、死。
あらゆる要素を兼ね備えた「究極の女性像」として、
クレオパトラは現代女性のロールモデルともなった。
フェミニズムの文脈では、
「男たちの物語に抗った唯一の古代の女王」としても語られる。
クレオパトラは死して滅びず、
時代と共にその姿を変え、
私たちの想像力の中で生き続けている。
第10章 永遠の女王 ― クレオパトラの遺産
遺された問い
クレオパトラの死後、
エジプトはローマ帝国に併合され、
アウグストゥスの「属州エジプト」となった。
だが、彼女が遺したものは、
国家や領土ではなかった。
それは、「生き方」の記憶であり、
「支配とは何か」「女性の力とは何か」という、
永遠の問いだった。
政治的遺産
クレオパトラは単なる恋多き女王ではない。
その外交手腕は、
ローマという超大国を翻弄した稀代の戦略家だった。
・カエサルとの連携は内戦に勝利をもたらし、
・アントニウスとの同盟は一時的に東地中海の覇権を握った。
つまり彼女は、
「感情」と「国益」を巧みに重ね合わせ、
時に女であり、時に王であったのだ。
彼女の政治手法は、後の女帝エリザベス1世や
エカチェリーナ2世にも影響を与えたとされる。
女性史の中のクレオパトラ
歴史において女性は、しばしば「語られる対象」に甘んじてきた。
だが、クレオパトラは「語る主体」として記録された稀有な存在である。
しかもその語りは、時代と共に塗り替えられ、
妖婦、聖女、神、戦略家、女優――
様々な仮面をつけられてきた。
その多面性こそ、
現代における「ジェンダーの象徴」としての魅力だ。
歴史の中で、彼女ほど多くの顔を持つ人物は、他にいない。
芸術と物語の中の再誕
古代ローマでは敵として、
中世では罪の象徴として、
近代ではロマンティックな女王として描かれた。
そして現代、
映画、舞台、小説、アニメ、ゲーム――
あらゆるメディアでクレオパトラは蘇っている。
それは「記憶」ではなく「創造」だ。
人々はクレオパトラを語ることで、
時代の理想の女性像を投影してきたのだ。
彼女自身が神話であり、
メタファーであり、
象徴なのだ。
クレオパトラという永遠
私たちは知っている。
その姿を、声を、考えを、正確に知る術はないことを。
だが、それでも語らずにはいられないのが、
クレオパトラという存在である。
彼女の名は、
「愛」と「権力」、
「美」と「知性」、
「誇り」と「滅び」――
そのすべてを含んだ、一つの宇宙だ。
終章に寄せて
もし歴史が「誰が世界を変えたか」を記す書だとするならば、
クレオパトラはその筆頭に記されるべきだろう。
なぜなら、彼女は「女性でも、国を、歴史を、愛を動かせる」ことを証明したからだ。
その意志と戦略と美と情熱のすべてが、
21世紀を生きる私たちに、
生き方の可能性を示してくれている。
クレオパトラは、ただの過去ではない。
今を照らす光であり、未来への問いかけなのだ。
あとがき
クレオパトラという名を聞くとき、私たちは何を思い浮かべるだろうか。
恋? 美貌? 裏切り? それとも悲劇?
本書で描いた彼女は、どれも正しく、どれも間違っている。
なぜならクレオパトラとは、「ひとつの顔で語れない人間」だったからだ。
彼女は、単なる「古代の女性」ではない。
政治家であり、母であり、愛人であり、王であり、そして思想家だった。
読者のあなたが「クレオパトラ」という名の重みを、
より鮮やかに感じていただけたなら、これに勝る喜びはない。





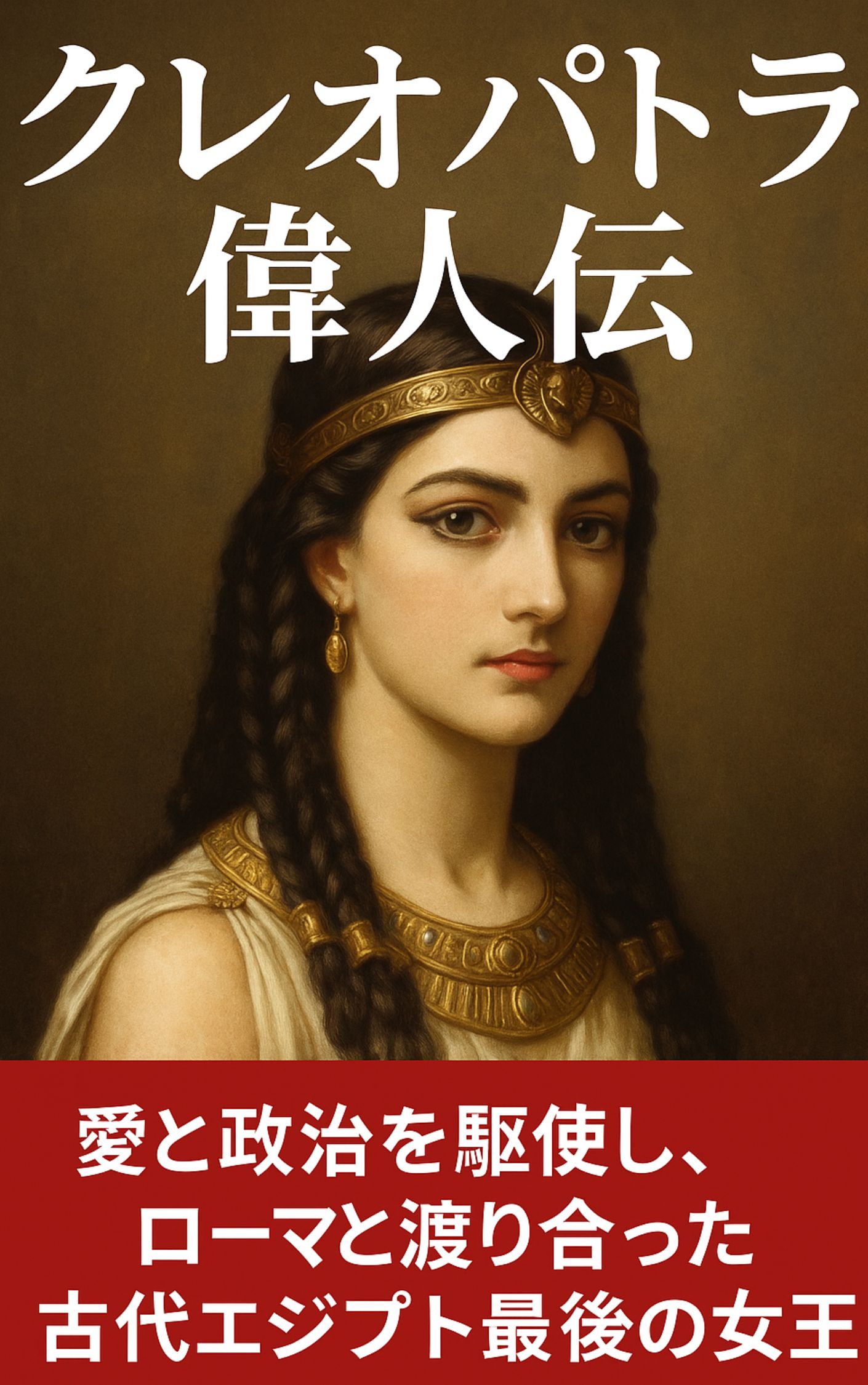
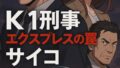

コメント