はじめに ― 「治す力」はあなたの中にある
現代社会に生きる私たちは、「病気=治療」「健康=医者頼み」といった価値観に染まりすぎています。
ですが、実は…
体は自ら治す力(自然治癒力)を持ち、心と環境はその鍵を握っている。
この原理を深く理解することこそが、
慢性的な不調、原因不明の症状、そしてストレス社会のなかで苦しむ多くの人たちにとって、最大の処方箋となります。
本解説書では、世古口裕司氏が提唱する
「医者と薬に頼らず、自分の人生を整える方法」について、
一章一章、丁寧に紐解いていきます。
単なる医学的解説を超え、
「自分と向き合う」「生き方を見直す」ための読書体験となることを願って。
あなたが、ほんとうの意味での健康を手に入れるきっかけになりますように。
目次
第3章 腸を整えれば、すべてが整う:免疫の司令塔・腸内環境の驚異
第4章 「毒を出す力」を取り戻せ:病気を生む“蓄積”と解毒・排泄の真実
第6章 「血流」がすべてを決める:ドロドロ血の正体と、めぐる体の作り方
第7章 排泄こそが最強の治療:便・尿・汗の秘密とデトックス力
第8章 ホルモンと自律神経の再起動:体と心のスイッチを整える法
第10章 健康とは“生き方”である:医者に頼らない人生のすすめ
第1章 医者と薬に頼る前に知るべきこと
- ◆はじめに:現代医療の限界
- ◆医療依存の危険性
- ◆「病気」とは何か
- ◆医者の本来の役割
- ◆まとめ:自分の健康は自分で守る
- ◆自然治癒力とは何か?
- ◆なぜ私たちは自然治癒力を信じられなくなったのか
- ◆自然治癒力の発動条件
- ◆熱を下げるべきか?下げないべきか?
- ◆医者は必要ないのか?
- ◆まとめ:自分で治すという覚悟
- ◆なぜ「腸」がそこまで大切なのか?
- ◆腸内細菌のバランスが病気のカギ
- ◆腸を整える三原則
- ◆うつ・不眠も「腸」で治る?
- ◆まとめ:医者も薬も要らない「腸活」という処方箋
- ◆病気は「体内のゴミ溜め」から始まる
- ◆解毒を担う「3大臓器」とは?
- ◆毎日できる「排毒・解毒」の生活術
- ◆感情もまた“毒”となる
- ◆まとめ:「出す力」は「治す力」
- ◆慢性炎症が「すべての病気の根源」
- ◆「炎症体質」をつくる5つの原因
- ◆「炎症体質」から脱却する生活術
- ◆「炎症」は沈められる
- ◆なぜ「血流」が生命のすべてなのか?
- ◆現代人の「ドロドロ血液」の実態
- ◆サラサラ血液を作る5つのステップ
- ◆「めぐる体」が自律神経もホルモンも整える
- ◆結論:「血流が良ければ、病気にならない」
- ◆病気の本質は「出せないこと」にある
- ◆デトックスの3大経路:便・尿・汗
- ◆便秘は“体内腐敗”を意味する
- ◆現代人が“出せない”理由とは?
- ◆出せる体をつくる7つの習慣
- ◆“腸・腎・皮膚”は排泄トライアングル
- ◆まとめ:医者より先に“トイレ”へ行け
- ◆体と心のバランスを決める“2つのスイッチ”
- ◆現代人は“交感神経オン”で疲弊している
- ◆ホルモンの乱れは「自律神経の失調」から始まる
- ◆自律神経を整える“7つの生活習慣”
- ◆“脳と腸”はホルモン分泌の司令塔
- ◆医者に行く前に、自分の“スイッチ”を見直そう
- ◆薬では「治った」ことにならない理由
- ◆再発の原因=「回復させる時間」と「材料」がない
- ◆「体内清掃システム」の再構築
- ◆“病気に強い人”がやっている7つのこと
- ◆体の声を聞く力=“再発しない”最大の知恵
- ◆病気は「敵」ではなく「メッセンジャー」
- ◆医者いらずの生き方を実現する「7つの転換」
- ◆医者と薬を“卒業”するために
- ◆人生そのものが“治療法”になる
- ◆読者へのラストメッセージ
◆はじめに:現代医療の限界
病気になったとき、私たちはごく自然に病院へ行き、薬を処方してもらいます。医者に診てもらい、薬をもらえば安心――多くの人がそう信じています。しかし、著者・世古口裕司氏は、その“常識”に強く疑問を投げかけます。
本書の主張はシンプルでありながら根本的です。「病気は医者と薬で治るのではなく、そもそも自分の体が治す力を持っている」という考え方が貫かれています。つまり、“自然治癒力”を信じ、それを高める生活こそが、真の治癒の道だというのです。
◆医療依存の危険性
現代医療は進歩を続け、治療の幅は広がっていますが、その一方で、過剰な投薬・過剰な検査が問題視されています。風邪や軽い体調不良でもすぐに抗生物質が処方される現実。生活習慣病と診断されると、年単位で薬を飲み続けるよう勧められる――こうした医療依存の状況が、かえって人間の自然な回復力を損なっている可能性があると著者は指摘します。
さらに、慢性的な症状の多くは、根本的な生活習慣の乱れに起因しています。つまり、薬を使って症状を抑え込むだけでは、真の意味で「治った」とは言えないのです。
◆「病気」とは何か
病気とは、単なる異常ではなく、身体が本来のバランスを取り戻そうとする“警告”であり“反応”です。たとえば、発熱はウイルスを倒すための免疫反応であり、咳は異物を排出するための反射行動です。
著者は、「病気=悪」とみなす現代的な見方を改めるべきだと述べています。むしろ、病気とは「体からのメッセージ」であり、それに耳を傾けることが第一歩である――という視点が重要です。
◆医者の本来の役割
医師は“治す人”ではなく、“気づかせる人”であるべき――これが本書の根幹にある考えです。患者が自らの生活や体調の変化に気づき、自らの意思で健康な方向へ生活を改めること。それこそが「治癒」への正道だというのです。
医者はアドバイザーであり、体の主役はあくまで“自分自身”。この主体性を取り戻すことで、薬に頼らずとも病気に打ち勝てる道が開かれるのです。
◆まとめ:自分の健康は自分で守る
第1章では、医者や薬に依存することのリスクを明らかにし、病気との向き合い方を根本から問い直す視点が提示されました。著者は決して「医療を全否定」しているわけではありません。必要なときには医療を使い、そうでないときは自分の自然治癒力を信じる――その“バランス感覚”こそが、これからの健康管理に必要なのです。
第2章 自然治癒力を信じるという革命
◆自然治癒力とは何か?
「自然治癒力」とは、病気やケガを自らの力で治す、生き物としての本質的な機能です。切り傷が自然とふさがるように、風邪が寝ているだけで治るように、私たちの身体には本来、外からの介入がなくとも元の状態に戻ろうとする強力な力が備わっています。
著者の世古口氏は、現代人がこの“身体の声”を無視しすぎていることを憂いています。病気になるとすぐに病院へ駆け込み、症状を薬で押さえる。だが、それは自然治癒力が働く前に、無理やり症状を「黙らせている」だけなのではないか、と警鐘を鳴らすのです。
◆なぜ私たちは自然治癒力を信じられなくなったのか
それは“現代医療の成功体験”によるものです。抗生物質が感染症を治し、手術が命を救う。たしかに医学の進歩は、私たちに多くの恩恵を与えてきました。
しかし同時に、「病気=すぐに治療」「治療=薬や手術で抑える」という思考が刷り込まれ、本来の治癒のプロセスを軽視するようになったのです。
また、メディアや製薬会社による過剰な健康不安の煽りも大きな原因です。「◯◯を飲まないと危険」「毎日測定しないと手遅れになる」といった情報が、私たちの不安を刺激し、「治す力は外部にある」という誤解を助長しています。
◆自然治癒力の発動条件
自然治癒力は、ただ「信じる」だけでは働きません。発動させるには、次のような条件が必要です:
十分な休養と睡眠
体を温める(冷やさない)
内臓に負担をかけない食生活
ストレスのコントロール
良質な水と呼吸
腸内環境の整備
これらの土台が整ったとき、自然治癒力は最大限に機能します。つまり、薬に頼らずに治すとは、「生活を整え、身体が本来持っている力を信じて引き出すこと」なのです。
◆熱を下げるべきか?下げないべきか?
著者は「熱は下げない方がよい」と明言します。発熱はウイルスや細菌をやっつけるために体が戦っている証拠であり、無理に解熱剤を使うことは、免疫システムの邪魔をしてしまうからです。
もちろん、命に関わるような高熱は例外ですが、多くの場合は、静かに休ませることが最善なのです。熱は体の味方であり、敵ではない。こうした“身体の知恵”に目を向けることが、自然治癒力の理解につながります。
◆医者は必要ないのか?
決して医療を否定しているのではありません。著者は、「緊急医療」や「外科手術」などの重要性を認めたうえで、「慢性的な病気や体調不良においては、医者に“治してもらう”という考えを改めるべき」と述べています。
医者は「相談相手」であり、「処方箋を出す人」ではなく、「治癒のきっかけを与えてくれる存在」として見るべきなのです。
◆まとめ:自分で治すという覚悟
自然治癒力を信じるとは、突き詰めれば「自分の体を信じること」です。そしてそれは、誰かに治してもらうという“受け身”ではなく、「自分の体調や生活に責任を持つ」という“主体性”を意味します。
この考え方こそが、「医者と薬に頼らない」という一歩目であり、真の意味での“病気の本当の治し方”に近づく道だと、著者は語っています。
第3章 腸を整えれば、すべてが整う:免疫の司令塔・腸内環境の驚異
◆なぜ「腸」がそこまで大切なのか?
「病気の9割は腸で治る」と言われるほど、腸の健康は身体全体に影響を及ぼします。著者・世古口裕司氏は、腸を「第二の脳」であり、また「最大の免疫器官」とも呼び、全身の健康の要と位置づけます。
私たちの腸内には約100兆個もの腸内細菌が存在し、それぞれが代謝・免疫・栄養吸収において重要な役割を果たしています。つまり、腸内環境が乱れれば免疫力は低下し、代謝異常が起き、アレルギーや感染症、さらにはうつや不眠といった精神症状にまで波及するのです。
◆腸内細菌のバランスが病気のカギ
腸内細菌は大きく次の3つに分類されます:
善玉菌(例:ビフィズス菌・乳酸菌)
悪玉菌(例:ウェルシュ菌・大腸菌の一部)
日和見菌(どちらにも転ぶ)
健康な人の腸内では、善玉2割・悪玉1割・日和見7割のバランスが保たれています。しかし、食生活の乱れ、ストレス、抗生物質の乱用によって、悪玉菌が増え、このバランスが崩れると、便秘や下痢はもちろん、アトピーや花粉症、自己免疫疾患にまで発展する可能性があります。
◆腸を整える三原則
著者は、腸内環境を整えるために次の3原則を提唱しています:
① 「食物繊維」と「発酵食品」を摂る
腸内の善玉菌のエサとなる「プレバイオティクス(食物繊維)」と、善玉菌そのものを摂取できる「プロバイオティクス(発酵食品)」を意識的に摂ること。
食物繊維:海藻、ゴボウ、きのこ、雑穀など
発酵食品:納豆、味噌、漬物、ヨーグルト、キムチなど
② 「小麦・乳製品・糖質」の摂り過ぎを控える
グルテンやカゼイン、精製された糖質は、腸壁を傷つけ、腸漏れ(リーキーガット)を引き起こす可能性があります。これがアレルギーや慢性疲労、不定愁訴の原因になることも。
「完全に断つ」のではなく、「摂り過ぎない」というスタンスが大切です。
③ ストレスを減らす
腸は脳と密接にリンクしており、強いストレスがかかると、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)が乱れ、善玉菌が減少することが分かっています。深呼吸、瞑想、ウォーキング、自然とのふれあいなど、ストレスコントロールを日々意識することが求められます。
◆うつ・不眠も「腸」で治る?
最新の研究では、「腸は脳よりも先に感情を感じる」とも言われています。腸内環境が整うと、幸福ホルモン「セロトニン」の分泌が促進され、気分が安定し、睡眠の質も向上します。
逆に、腸が乱れると自律神経も乱れ、メンタル不調に陥りやすくなります。だからこそ、薬に頼る前に、まず「腸を整える」という発想が必要なのです。
◆まとめ:医者も薬も要らない「腸活」という処方箋
病気を治す鍵は、「腸を整える」ことにあります。著者は、腸を“育てる”ための生活こそが、真の意味での健康であり、病気を未然に防ぐ最高の手段だと強調します。
「腸を変えれば、人生が変わる」
これは決して誇張ではなく、食事・生活・意識を整えるだけで、自分の中の“治す力”がよみがえり始める。その一歩目が、腸活=腸のメンテナンスなのです。
第4章 「毒を出す力」を取り戻せ:病気を生む“蓄積”と解毒・排泄の真実
◆病気は「体内のゴミ溜め」から始まる
著者・世古口裕司氏は、現代人の多くが「毒を溜めすぎている」と警鐘を鳴らします。ここでいう「毒」とは、以下のようなものを指します。
食品添加物、残留農薬、環境ホルモン
重金属(水銀・鉛など)
体内で発生する老廃物(乳酸、アンモニア、過酸化脂質など)
未消化物や便秘による腸内腐敗物
情報・ストレス・ネガティブ感情
これらの毒が体内に蓄積すると、免疫やホルモンバランス、自律神経が乱れ、病気の“下地”ができてしまいます。慢性疲労、アレルギー、頭痛、うつ、不眠などもこの「排毒の詰まり」が原因のことが少なくないのです。
◆解毒を担う「3大臓器」とは?
解毒・排泄のために働く主な臓器は以下の3つです。
① 肝臓(解毒の司令塔)
肝臓は、アルコールや薬物、化学物質などの異物を代謝・無害化する「デトックス工場」。ただし、糖質や脂質の過剰摂取、薬の飲みすぎでオーバーワークになりやすい臓器でもあります。
② 腸(排泄の出口)
腸内で解毒された老廃物や胆汁は便として排泄されます。しかし、便秘状態だと再吸収され、体内に再び毒が巡ってしまう「腸肝循環」が起きてしまいます。
③ 腎臓(血液のフィルター)
腎臓は、血液中の老廃物を濾過し、尿として体外へ排出します。水分不足やタンパク質過多により負担がかかると、腎機能が低下し、体に毒素が溜まりやすくなります。
◆毎日できる「排毒・解毒」の生活術
著者は、日々の生活で“毒を出す”力を取り戻す方法をいくつも紹介しています。
● 白湯(さゆ)を飲む
朝起きてすぐの白湯は、内臓を温め、腸の蠕動運動を促進します。これにより便通が改善され、老廃物の排出がスムーズになります。
● 汗をかく(入浴・運動・サウナ)
皮膚は“第三の腎臓”とも呼ばれ、発汗は非常に有効な解毒法です。ぬるめの半身浴や、週に数回の軽い運動でも発汗は促せます。
● 食べ過ぎない・断食を取り入れる
著者は、「食べない時間」が解毒に有効だと述べています。断続的断食(インターミッテント・ファスティング)や、週1回のプチ断食は、消化器官を休ませ、解毒に集中させる時間を与えてくれます。
● 「毒を入れない」努力も重要
加工食品を減らす
有機野菜を選ぶ
プラスチック容器を電子レンジにかけない
合成洗剤や柔軟剤を見直す
これらの生活改善によって、「溜めない・出す」体質へとシフトしていくのです。
◆感情もまた“毒”となる
見落とされがちなのが、怒り、妬み、不安、悲しみといった「感情の毒」。東洋医学では、これらの負の感情も肝・心・肺・脾・腎といった臓器に悪影響を与えるとされます。
たとえば:
怒り→肝臓に悪影響
悲しみ→肺に悪影響
不安→腎を弱める
「感情のデトックス」もまた、体の浄化には不可欠なのです。
◆まとめ:「出す力」は「治す力」
病気を治すには、まず「溜めないこと」、そして「出せる体を取り戻すこと」が重要です。サプリメントや健康食品に走る前に、自分の体が「捨てられているか?」を見つめ直すことが大切だと、著者は繰り返し説いています。
毒を出せる体になると、自然治癒力がよみがえり、治療に頼らなくても、日常の中で「自分で治す力」が育っていく。
つまり、“解毒”こそが、本当の意味での“治療”の第一歩なのです。
第5章 炎症を抑えろ:病の根を断つ“体内火災”の鎮め方
◆慢性炎症が「すべての病気の根源」
著者・世古口裕司氏は「病気とはすべて“炎症”の延長線上にある」と明言します。炎症とは本来、免疫によって体が異物や損傷に反応する自然なプロセス。しかし、これが慢性化し、長期間続くと、むしろ体を攻撃してしまう「敵」に変わるのです。
現代人に多い以下の症状や病気は、すべて慢性炎症が関わっているとされています:
動脈硬化・高血圧・心筋梗塞
糖尿病・脂肪肝
アトピー性皮膚炎・喘息
花粉症・慢性鼻炎
うつ・不眠・脳疲労
認知症・がん
◆「炎症体質」をつくる5つの原因
炎症を起こす引き金は、生活の中に潜んでいます。著者は以下の5つを「炎症スイッチ」として紹介します:
① 糖質過多(特に精製糖)
白砂糖や小麦、清涼飲料水などの摂取は血糖値を乱高下させ、「糖化」という炎症を起こします。AGEs(終末糖化産物)という有害物質が血管や内臓に蓄積するのです。
② トランス脂肪酸・オメガ6脂肪酸の過剰
マーガリン、サラダ油、加工食品に多く含まれる脂質は、体内で「炎症性ホルモン(サイトカイン)」を増やします。これが血管や脳を蝕む元凶になります。
③ 腸内環境の乱れ(リーキーガット)
腸のバリア機能が壊れると、未消化物や細菌が血中に漏れ出し、全身性の炎症を引き起こします。アレルギーや自己免疫疾患の根底にはこの問題が潜みます。
④ 睡眠不足・ストレス
交感神経の緊張、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌異常も、炎症を慢性化させる大きな要因です。特に睡眠中は「炎症リセット時間」なので、不眠は致命的。
⑤ 慢性感染・ウイルス・化学物質
口腔内の炎症(歯周病)やピロリ菌、カンジダ菌、ウイルス感染も、炎症の火種となります。さらに農薬、重金属、PM2.5などの化学的刺激も無視できません。
◆「炎症体質」から脱却する生活術
では、どうすれば炎症を鎮めることができるのか? 著者は次の5つを推奨しています。
● 抗炎症食を実践する
白米→玄米や雑穀米に
精製糖→甘酒、はちみつなど自然の糖に
揚げ物→蒸し・煮る調理法に
オメガ6→オメガ3(青魚・えごま油・亜麻仁油)へ
野菜中心(特に緑黄色野菜と海藻類)
● 1日15分以上の軽い運動
ウォーキング、ストレッチ、ヨガなどで血流を良くすることで、「炎症ゴミ」が流れやすくなります。
● 睡眠の質を高める
就寝90分前に風呂に入り、体温をゆっくり下げる
部屋は暗く・静かに
寝る前スマホ・カフェイン断ち
起床後すぐ朝日を浴びて、体内時計を整える
● 腸内環境を整える
発酵食品(味噌、ぬか漬け、納豆、ヨーグルト)を摂取
食物繊維(野菜・きのこ・海藻)を意識的に
グルテン・カゼイン(小麦・牛乳)の摂りすぎに注意
● メンタルケアを習慣に
日記を書く、感謝を記録する
瞑想・深呼吸を取り入れる
自然の中を歩く
笑う、泣く、感情を表現する
◆「炎症」は沈められる
世古口氏が繰り返し説くのは、「病名よりも“炎症の火元”を探せ」ということ。対症療法で炎症を抑えるのではなく、「なぜ火が点いたのか?」を生活の中で見つけ、消していく。それが真の根本治療です。
第6章 「血流」がすべてを決める:ドロドロ血の正体と、めぐる体の作り方
◆なぜ「血流」が生命のすべてなのか?
著者・世古口裕司氏は、本章で「血流こそが健康を左右する最大の鍵」であると断言します。なぜなら、血液は全身に酸素・栄養・ホルモン・免疫細胞を運び、老廃物を排出する「命の運搬システム」だからです。
血流が滞れば、細胞は飢餓状態になり、毒素が溜まり、炎症・酸化・糖化などの“病の温床”ができあがってしまうのです。
◆現代人の「ドロドロ血液」の実態
現代人の多くは、以下のような生活習慣によって「血液ドロドロ化」が進んでいるといいます。
過剰な糖質と脂質:スイーツやジャンクフードの摂りすぎは血液中の中性脂肪や糖を増やし、血液粘度を高める
水分不足:コーヒーやアルコールは利尿作用があり、脱水傾向に。血液は濃縮される
運動不足・ストレス:筋肉ポンプが使われず、交感神経優位になると血管収縮し、流れが悪化
冷え・低体温:血管が収縮し、血液が滞りやすくなる
タバコ・睡眠不足:酸化ストレスにより赤血球の柔軟性が失われる
このような「粘る・汚れる・流れない」血液では、いくら食事に気を使っても、栄養も酸素も届かないと著者は警告します。
◆サラサラ血液を作る5つのステップ
世古口氏は、血流を改善するための実践的な方法を5つ挙げています。
①「水」を見直せ
朝起きたらコップ1杯の常温水
1日1.5〜2リットルの水(白湯がおすすめ)を意識的に飲む
カフェイン飲料・アルコールは水とセットで
腎臓が冷えないよう、冷たい水は避ける
→血液の95%は水分。最も手軽な血液改善法は“正しい水分摂取”です。
② 末梢を動かせ:ふくらはぎと手を動かす
1日20分以上のウォーキング
足指じゃんけん・ふくらはぎマッサージ
手のグーパー体操・温熱手浴
→血流の8割は“末端”で滞る。ふくらはぎは「第二の心臓」、手は「第二の脳」とも呼ばれる重要器官。
③ 呼吸を整える:酸素は“血流のパートナー”
鼻呼吸を意識する
1分間の腹式深呼吸を1日3セット
マインドフルネスや瞑想で副交感神経を優位に
→酸素は血液の「目的地」。浅い呼吸ではせっかくの血流も活かされない。
④ 食事は「巡るもの」を意識
シナモン、生姜、にんにくなど血管拡張作用のあるスパイス
ビタミンE(アーモンド、かぼちゃ)
青魚に含まれるEPA・DHA(血小板凝集を防ぐ)
ネバネバ食材(納豆・オクラ・山芋)も血流をサポート
→“薬膳的思考”で、「流す食材」「温める食材」を日常に。
⑤ 血管を鍛える:若返りホルモン“NO”を出せ
一酸化窒素(NO)は、血管内皮から分泌される血管拡張物質。ウォーキングや有酸素運動によって生成され、血管の若返りにつながる。
階段のぼり降り、スクワットなどの「軽い負荷運動」
笑う、歌う、感動することで副交感神経を優位にするのも◎
◆「めぐる体」が自律神経もホルモンも整える
世古口氏は「血流が良くなれば、すべてが整う」と語ります。
自律神経が整う→睡眠が深くなり、ストレスにも強くなる
ホルモン分泌が安定→免疫や代謝も正常化
消化・吸収も良くなり、腸内環境も整う
脳への血流が回復→集中力・感情コントロール力がアップ
つまり、血流こそが「体のあらゆる機能のエンジン」なのです。
◆結論:「血流が良ければ、病気にならない」
血液とは、命そのもの。
だからこそ、運動・食事・水・呼吸・心の在り方のすべてを「巡る体」を意識して整えるべき。
医者や薬より、自分の血の“流れ”を信じる。
第7章 排泄こそが最強の治療:便・尿・汗の秘密とデトックス力
◆病気の本質は「出せないこと」にある
この章で著者・世古口裕司氏が繰り返し述べる主張は極めてシンプルかつ本質的です。
「健康とは、体に不要なものを、正しく“出せる”力で決まる」
体にとって最も重要な機能のひとつが「排泄」であり、現代人はこの「出す力」が圧倒的に弱っているといいます。多くの不調、肥満、アレルギー、便秘、頭痛、肌荒れ……その正体は「溜め込み体質」にあるのです。
◆デトックスの3大経路:便・尿・汗
人間の体は、3つの主要な経路で老廃物を外へ排出しています。
| 排泄手段 | 内容物 | 備考 |
| 便 | 消化後の不要物、胆汁、老廃菌、コレステロールなど | 最も重要な経路。体内毒素の75%が便から排出される |
| 尿 | 水溶性の老廃物、アンモニア、ナトリウム、薬剤など | 腎臓のフィルター機能で濾過。水分摂取と腎機能がカギ |
| 汗 | 重金属、老廃物、水分、塩分など | 肝臓・腎臓では排出できない脂溶性毒素を出せる |
著者は「便が出ない」「尿が少ない」「汗をかかない」人ほど、慢性疾患や不定愁訴を抱えやすいと指摘します。
◆便秘は“体内腐敗”を意味する
とくに「便」はデトックスの主役です。
便秘が続くと、腸内の腐敗菌が増殖し、アンモニアやフェノールなどの有害物質が腸壁から吸収され、血液に流れ込む
結果、肌荒れ・口臭・頭痛・集中力低下・免疫力低下など全身に悪影響
腸内環境の悪化は、セロトニン(幸福ホルモン)分泌の減少にも直結
「便秘は便が出ないこと」ではなく、「体内が腐っている状態」であると著者は警告します。
◆現代人が“出せない”理由とは?
食物繊維不足:精製された白米・白パン中心の食生活
水分不足:カフェインや冷たい飲み物が腸を冷やし、蠕動運動が低下
運動不足:腹圧が弱まり、排便力が低下
ストレス:交感神経優位で腸の動きが抑制
常用薬・サプリ依存:便秘薬や整腸剤の乱用で腸が怠ける
これらの生活習慣が、「排泄できない体=病気になりやすい体」をつくり上げてしまっているのです。
◆出せる体をつくる7つの習慣
著者は、排泄力を高めるために以下の7つの習慣をすすめています。
① 朝起きてすぐコップ1杯の白湯を飲む
→寝ている間に失われた水分を補い、腸を優しく目覚めさせる。白湯は胃腸の血流を促進する“天然の下剤”。
② 発酵食品と水溶性食物繊維をとる
納豆、ぬか漬け、キムチ、味噌汁
オクラ、わかめ、ごぼう、こんにゃく
→腸内細菌を整え、善玉菌を育てる。
③ スクワット&腹式呼吸
→腸の位置を整え、腹圧を上げて“出す力”をつける。朝の3分でOK。
④ 「朝トイレタイム」を習慣化
→毎朝、排便のチャンスを“意識的に”作る。時間をかけて深呼吸しながら“排泄の儀式”を持つことが大切。
⑤ 「ながらスマホ排便」をやめる
→副交感神経に切り替えるために、集中して“出す”こと。デジタル断食も排泄の一環。
⑥ 汗をかく習慣をつける
→半身浴・サウナ・ウォーキング・ホットヨガなど。汗は“第3の排泄器官”。
⑦ 薬に頼りすぎない
→便秘薬・利尿剤・抗アレルギー薬などは“出す力”を麻痺させる。自然な排泄に立ち返るべき。
◆“腸・腎・皮膚”は排泄トライアングル
世古口氏は、排泄は単独器官ではなく「腸・腎臓・皮膚」のネットワークで機能していると語ります。
腸が出せないと、腎臓と皮膚に負担がかかる
その結果、ニキビ・肌荒れ・アトピー・むくみ・疲労感に
「出すこと」こそが、美容・精神・免疫の根幹
◆まとめ:医者より先に“トイレ”へ行け
「出すこと」ができれば、「治す力」が自然に湧いてくる
病気とは、体に不要なものが“出せない”結果
最強の健康法とは、「出せる人間」になること
第8章 ホルモンと自律神経の再起動:体と心のスイッチを整える法
◆体と心のバランスを決める“2つのスイッチ”
私たちの体と心は、意識しなくてもさまざまな機能が自動で働いています。呼吸、心拍、血圧、内臓の働き……。これを司るのが「自律神経」と「ホルモン」です。
自律神経:交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)のバランス
ホルモン:脳下垂体や副腎、甲状腺、性腺などが出す命令物質
著者・世古口裕司氏は言います。
「病気とは、“スイッチ”が狂った状態にすぎない。整えれば、体は自然に回復する」
つまり、健康とはこの**“スイッチの切り替え”**を正しく行えるかどうかにかかっているのです。
◆現代人は“交感神経オン”で疲弊している
現代のストレス社会では、交感神経が常に優位な“戦闘モード”状態が続いています。
緊張、焦り、怒り、不安、スマホ通知、締切、騒音…
これらはすべて“交感神経”を刺激する要因
その結果、
副交感神経(回復モード)が働かず、寝ても疲れがとれない
血流が悪くなり、冷え・頭痛・便秘・胃痛が起こる
ホルモン分泌も乱れ、生理不順・肌荒れ・不妊・うつにつながる
◆ホルモンの乱れは「自律神経の失調」から始まる
ホルモンバランスが崩れると、多くの不調が現れます。
| ホルモン名 | 役割 | 乱れると起きる症状 |
| コルチゾール(副腎) | ストレス対応、代謝 | 慢性疲労、集中力低下、免疫低下 |
| エストロゲン(卵巣) | 女性らしさ、骨・血管・脳の保護 | 生理不順、うつ、老化促進 |
| テストステロン(精巣) | 活力、筋肉、やる気 | 無気力、筋力低下、肥満 |
| メラトニン(脳) | 睡眠促進 | 不眠、うつ |
| セロトニン(腸) | 幸福感、精神安定 | イライラ、うつ、睡眠障害 |
著者はこれらホルモンの不調を“薬で補う”よりも、根本的な自律神経の整え直しを強調します。
◆自律神経を整える“7つの生活習慣”
① 朝日を浴びる
→ 目に朝日が入ると、セロトニンが分泌 → 夜にメラトニン(睡眠ホルモン)へ変化
② 「ながら行動」をやめる
→ 食事しながらスマホ、歩きながらSNS… → 脳は常に興奮 → 交感神経が優位に
→「一点集中」が副交感神経を活性化する
③ 呼吸を整える(鼻から吸って口からゆっくり吐く)
→ 1日3分の腹式呼吸で、心拍と血圧が下がり、腸も動く
→ 自律神経の“切り替えスイッチ”として極めて効果的
④ 体を温める(特に首・足首・お腹)
→ 冷えは副交感神経を鈍らせる最大要因
→ 湯たんぽ・腹巻き・半身浴が推奨される
⑤「夜のスマホ断ち」
→ スマホのブルーライトはメラトニン分泌を抑制
→ 夜22時以降は、できればスマホをオフに
→ 安眠こそがホルモン再起動の起点
⑥ 良質なタンパク質と脂質の摂取
→ ホルモンの材料は脂質とタンパク質
→ 卵・ナッツ・青魚・アボカドなどを積極的にとる
→ 糖質過多はホルモン異常の原因
⑦ 「心の癖」に気づく
→ 完璧主義・心配性・自己否定傾向は、交感神経を過度に刺激する
→ 意識して「ゆるめる」習慣(瞑想・散歩・笑い・自然とのふれあい)を持つ
◆“脳と腸”はホルモン分泌の司令塔
脳の視床下部は、全ホルモンの司令塔
腸は“第2の脳”と呼ばれ、セロトニンの90%がここで作られる
つまり、ホルモンを整えたいなら、腸を整え、脳をリラックスさせるべきというのが著者の主張です。
◆医者に行く前に、自分の“スイッチ”を見直そう
「なんとなく疲れている」
「やる気が出ない」
「不眠や頭痛が続く」
それらは病気の前兆ではなく、スイッチの切り替えがうまくいっていないだけかもしれません。
自律神経とホルモンのスイッチを整えることで、体は本来の力を取り戻す
薬でホルモンを補う前に、生活と心の癖を見直すこと
第9章 再発しない体をつくる:“病気を防ぐ力”の根源
◆薬では「治った」ことにならない理由
私たちは、病気が治ることを「症状が消えること」と勘違いしている節があります。
咳が止まった=治った
頭痛薬で痛みが引いた=治った
血糖値が薬で下がった=治った
しかし、それらは**症状の「一時停止」**に過ぎません。
著者・世古口氏はこう強調します。
「薬を使って症状が消えたとしても、それは“治癒”ではない。
本当の治癒とは“病気になりにくい体”に戻すことだ」
この章では、**「再発しない健康体」**をつくるために必要な、本質的な力=自己治癒力と免疫力の再構築について解説します。
◆再発の原因=「回復させる時間」と「材料」がない
病気が治りきらない、あるいは繰り返す理由は明白です。
十分な休養が取れていない(時間不足)
回復に必要な栄養が足りていない(材料不足)
再発を招く生活習慣が改善されていない
たとえば、風邪を引いた直後から仕事に復帰し、無理を続けるとどうなるか?
一見、治ったように見えても、免疫は下がり、疲労は蓄積し、再発の種がくすぶり続けるのです。
◆「体内清掃システム」の再構築
病気を防ぐためには、体内の“掃除機能”が正常に働く必要があります。
リンパ系:老廃物を排出し、免疫細胞が巡回
肝臓・腎臓:毒素・薬物・老廃物を分解・排出
腸内環境:悪玉菌を抑え、善玉菌優勢に保つ
汗腺・皮膚:皮膚呼吸と発汗で毒素を出す
著者は「現代人は“入れること”ばかりに目を向け、“出す力”を軽視している」と警鐘を鳴らします。
◆“病気に強い人”がやっている7つのこと
著者が紹介する「再発しない人に共通する習慣」は次のとおりです。
①「疲れたら寝る」ではなく「疲れる前に休む」
→ 体は予兆を出している。休息は“事後”でなく“予防”に使うべき。
② 適度な“飢え”をつくる(間食断ち・16時間断食)
→ 消化を休ませる時間があると、代謝と免疫が高まる(オートファジー活性)
③ 日中はしっかり太陽を浴びる
→ ビタミンD生成 → 免疫細胞活性 → 感染症やがんの予防にも有効
④ 毎日「腸を動かす」時間を意識する
→ 腸内環境=免疫の本丸。食物繊維・水・発酵食品を意識して摂取。
⑤ 1日5分「声を出して笑う」
→ 笑いは副交感神経を優位にし、ナチュラルキラー細胞(NK細胞)を活性化する。
⑥ 体に“ありがとう”を伝える
→ 「私の免疫さん、ありがとう」と声をかける。
→ 思考と生理反応は密接につながっている(プラシーボ効果・脳内ホルモン分泌)
⑦「無理しない」が最強の予防
→ 仕事・人間関係・家庭…すべてにおいて「やりすぎない」「背負いすぎない」がコツ。
◆体の声を聞く力=“再発しない”最大の知恵
病気は「体の警報」です。
それを無視して薬で消しても、再び警報は鳴り、しかも大きくなって戻ってきます。
「早く治す」よりも「繰り返さない体」にシフトするには:
日々の“違和感”に敏感になること
小さな不調を放置せず、休養と栄養でリカバリーすること
そして「治す」から「整える」「守る」へ考え方を変えること
第10章 健康とは“生き方”である:医者に頼らない人生のすすめ
◆病気は「敵」ではなく「メッセンジャー」
現代人は「健康とは病気にならないこと」「病気はすぐ治すべきもの」と考えがちです。
しかし、著者・世古口裕司氏は、こう語ります。
「病気とは、体の叫びであり、“今の生き方を変えてほしい”というメッセージである」
つまり、病気を“取り除く対象”として見るのではなく、
「自分に何を教えてくれているか?」という視点を持つことで、人生全体の見直しにつながるのです。
◆医者いらずの生き方を実現する「7つの転換」
本章では、医者・薬に依存しない生き方にシフトするための「生き方の7転換」を提示します。
① 治療から「予防」に転換する
具合が悪くなってから病院に行くのではなく
日々の生活が最大の“診療所”であると気づく
② 我慢から「手放す」に転換する
人間関係、過剰な責任感、完璧主義…
不調の原因は“心の圧”であることも多い
③ 他人軸から「自分軸」に転換する
周囲に合わせることでストレスがたまる
自分の“好き”“快”を大切にすることが免疫力を支える
④ “頑張る”から「整える」に転換する
頑張りすぎが続くと交感神経優位となり、病気を招く
毎日を“整える”ことが、本当の意味での養生
⑤ 無理に動くから「休む勇気」に転換する
体が発する違和感を察知し、勇気を持って休む
“休む=サボる”ではなく、“回復させる仕事”と捉える
⑥ ネガティブ思考から「感謝」へ転換する
食べ物、体、天気、人間関係…
感謝を感じる頻度が多いほど、免疫と幸福度は上がる
⑦ 「健康は技術」から「健康は生き方」へ転換する
食事法・運動法・睡眠法はもちろん大切だが
それらを“義務”でやっていては逆効果
自然体で継続できる“生き方”に組み込むことが鍵
◆医者と薬を“卒業”するために
著者は「医療否定派」ではありません。
緊急時や急性疾患では医療の力が必要不可欠です。
しかし、慢性疾患・生活習慣病・ストレス性の不調に対しては、
「病院に通い続ける生き方」から「体と向き合い、自分で守る生き方」への転換が求められると語ります。
◆人生そのものが“治療法”になる
最終的に、健康は医者が与えるものではありません。
自分で選ぶ食事
自分で決める休み方
自分が心地よいと感じる人間関係
自分が笑顔になれる瞬間
これらすべてが、“治療”であり、“予防”であり、
そして“人生そのもの”が、あなたを癒やす最大の薬なのです。
◆読者へのラストメッセージ
あなたの体は、あなたの人生を“丸ごと”映し出しています。
健康になりたいのなら、体を変えるだけでなく、
生き方そのものを“調律”してください。
「健康でい続ける人」は、特別な人ではなく、
「日々、自分と向き合い、整えている人」なのです。
おわりに ― あなたの人生そのものが、最高の治療法になる
本書のすべてを通して、あなたはこう気づいたかもしれません。
「薬や手術よりも、
私自身の習慣、考え方、環境が、病気の原因であり治療でもある」と。
世古口裕司氏の言葉には、
**「医者に行かなくても、体は治そうとしている」**という強い確信が宿っていました。
今、必要なのは“治すこと”ではなく、
“整えること”です。
呼吸を意識し、食を選び、感謝し、眠りを大切にし、人と心地よくつながる――
それだけで、体は少しずつ、本来の状態に戻ろうとするのです。
医者を否定するのではありません。
「医者に頼らなくても大丈夫な自分」を目指すことが、
真の自由と安心に近づく一歩なのです。
本書を読んだあなたが、
今日から少しずつ、「医者と薬に頼らない生き方」を始められることを、心から願っています。





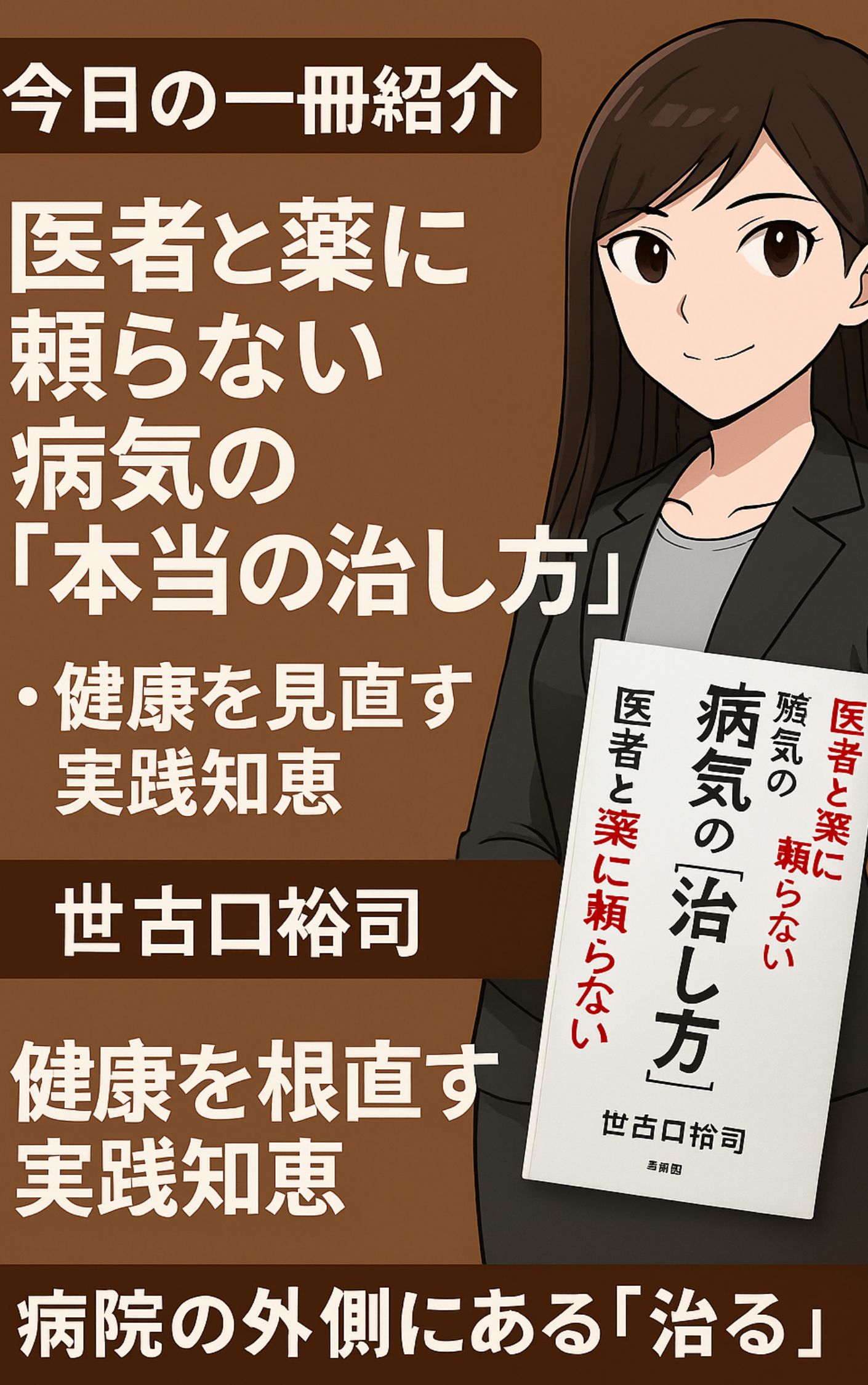

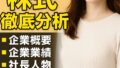
コメント