まえがき
現代人の多くが抱える不調――冷え、肩こり、頭痛、倦怠感、ストレス、そして生活習慣病。その多くは、実は「血流の滞り」から始まっています。本書は、血流こそが健康の基盤であり、改善することで心身の不調が大きく変わるという視点から、食事・運動・生活習慣・漢方までを網羅的に解説した一冊です。
著者が示すのは、特別な治療法ではなく、誰でも今日から始められる血流改善の具体策です。長年の臨床経験と最新の医学知見を組み合わせた実践法は、読む者に「自分の体を自分で整える力」を与えてくれます。
本解説版では、原書のエッセンスを10章にわたり丁寧に読み解き、さらに生活への落とし込み方や実例を加えてお届けします。あなたの5年後、10年後の健康を守るための道しるべとなることを願っています。
目次
第1章 血流こそ健康の原点
私たちの体は、およそ60兆個もの細胞でできています。そして、そのすべての細胞に酸素や栄養を送り届け、老廃物を回収するのが「血液」の役割です。血液が滞りなく巡ることで、体は機能を保ち、健康を維持することができます。
著者・堀江昭佳氏は、漢方薬剤師として多くの患者を診てきた経験から、「血流こそが健康の土台であり、あらゆる不調の根源は血の滞りにある」と結論づけています。
1. 血流とは何か
血流とは、心臓のポンプ作用によって血液が全身を循環する動きそのものを指します。血液は酸素・栄養素・ホルモンなどの生命活動に必要な物質を運び、同時に二酸化炭素や老廃物を回収します。
この循環が滞れば、細胞は栄養不足に陥り、組織の修復や再生が遅れ、免疫機能も低下します。たとえ食事で良い栄養を摂っても、それを届ける血流が滞っていれば意味がありません。
2. 漢方的な「血」の概念
西洋医学では血流を物理的な循環として捉えますが、漢方ではもう一歩踏み込み、「血(けつ)」という生命エネルギーの一部として考えます。
漢方における「血」には以下の3つの側面があります。
栄養の供給(身体を養う物質的役割)
体温の維持(温める働き)
精神の安定(心を落ち着かせる作用)
漢方の臨床経験からも、血の不足(血虚)、血の巡りの悪さ(瘀血)、血の質の悪化は、身体症状だけでなくメンタル面の不調にもつながるとされます。
3. 血流が悪くなると何が起こるのか
血流の滞りは、全身に多様な不調をもたらします。著者はこれを「冷え」「疲れ」「不眠」「生理不順」「気分の落ち込み」といった症状として多く目にしてきました。
具体的には、
手足の冷え、肩こり、腰痛
慢性的なだるさ、集中力の低下
生理痛やPMS、更年期症状の悪化
不眠や浅い眠り
抑うつや不安感の増大
などがあります。これらは別々の病気のように見えますが、根本には血流障害があるケースが多いのです。
4. 血流を改善するとなぜ体調が変わるのか
血流が改善されると、酸素と栄養の供給がスムーズになり、細胞の修復力が向上します。また、老廃物の排出が促進され、むくみや炎症が軽減します。
さらに、血流改善は自律神経を安定させ、ホルモン分泌のバランスを整える効果も期待できます。これは、脳や内分泌器官が血液の影響を直接受けるためです。
5. 「血流がすべて解決する」という考え方
著者は臨床の現場で、さまざまな不調を訴える患者に共通して「血流の滞り」があることに気づきました。
薬やサプリで部分的に症状を抑えるよりも、血流そのものを改善する方が、全体的な体調の底上げにつながることを繰り返し目の当たりにしたのです。
つまり、血流は単なる一つの健康要素ではなく、**全身の機能をつなぐ「土台」**だということです。
まとめ
血流は、生命活動の基礎となる酸素と栄養の供給・老廃物の排出を担う。
漢方では血の役割を物質的・温熱的・精神的な側面から総合的に捉える。
血流の滞りは多様な不調を引き起こすが、改善すれば全身の機能が向上する。
「血流がすべて解決する」とは、症状ごとの対処よりも根本改善を目指す考え方である。
第2章 血の質・量・巡りの三要素
血流を理解し改善するためには、「血の質」「血の量」「血の巡り」という三つの要素を切り離して考える必要があります。これは漢方の臨床経験でも強調される視点であり、この三要素のいずれか一つでも乱れると、全身のバランスが崩れ、様々な不調が現れます。著者・堀江昭佳氏は、健康の回復と維持のためには、この三つを同時に整えることが不可欠だと述べています。
1. 血の「質」――中身が健康を決める
血の質とは、血液そのものの中身の良し悪しを指します。酸素や栄養素を十分に含み、老廃物の排出もスムーズな血液は、赤く透明感があり、粘度も適切です。
しかし、食生活の乱れやストレス、喫煙、過剰なアルコール摂取などによって血の質は低下します。
質の悪化の特徴
ドロドロ血(高脂血症や血糖値の乱高下)
貧血(酸素運搬能力の低下)
栄養不足による免疫力低下
血液中の老廃物の蓄積
質の悪化は、単に血液検査の数値だけでなく、肌荒れ、慢性疲労、髪のパサつき、爪の割れやすさなど、外見にも現れます。
2. 血の「量」――足りなければ全身が機能低下
血の量は、体内を循環する血液の総量を指します。成人では体重の約8%が血液ですが、これが不足すると全身の細胞が必要な酸素や栄養を受け取れず、機能が低下します。
漢方では、この状態を**「血虚(けっきょ)」**と呼びます。
血虚のサイン
立ちくらみ、めまい
動悸、息切れ
集中力の低下、物忘れ
不眠、悪夢が多い
月経量が少ない、周期が乱れる
血の量を増やすには、鉄やたんぱく質、ビタミンB群など造血に必要な栄養をしっかり摂ることが大前提です。
3. 血の「巡り」――滞れば全てが滞る
どんなに血の質や量が良くても、それが全身に行き渡らなければ意味がありません。巡りの悪さは、血管の収縮や血液粘度の上昇、姿勢や筋肉の緊張などによって引き起こされます。
漢方では、この状態を**「瘀血(おけつ)」**と呼びます。
巡りの悪化の特徴
手足の冷え
肩こり、首こり、腰痛
顔色が暗い、唇が紫色
しこりやむくみ
生理痛や月経血の塊
巡りを改善するには、血管を拡張する温熱習慣(入浴・温かい飲み物)、軽い有酸素運動、ストレッチ、深呼吸などが効果的です。
4. 三要素は相互に影響する
質・量・巡りは独立して存在するわけではなく、互いに影響し合っています。
質が悪ければ血管内で滞りやすくなり、巡りが悪化する
量が不足すると、必要な場所に十分な血が行かず、質の低下や巡りの停滞を招く
巡りが悪ければ酸素・栄養の供給が滞り、質が悪化する
したがって、部分的に一つだけ改善しようとしても、根本的な変化は得られません。
5. 改善の第一歩
著者は、まず「巡り」を意識することを推奨しています。巡りが良くなれば、必要な栄養や酸素が各組織に届きやすくなり、血の質や量の改善にもつながるからです。温める、動かす、リラックスする──これらはすべて巡りの改善に直結します。
まとめ
血の質=栄養と老廃物のバランス
血の量=酸素と栄養を届ける力
血の巡り=それを全身に行き渡らせる流れ
三要素は互いに依存し合い、総合的な改善が必要
改善の第一歩は「巡り」を整えること
第3章 現代人の血流が悪くなる原因
現代社会は、かつてないほど便利で快適になりました。しかしその一方で、私たちの体は本来必要としていた運動や休養、食生活のバランスを失い、血流にとって厳しい環境に置かれています。著者・堀江昭佳氏は、多くの患者の症状の背景に「現代生活特有の血流障害」が潜んでいると指摘します。本章では、その主な原因を一つずつ掘り下げていきます。
1. 運動不足と長時間の座位
オフィスワークやテレワークの普及により、1日のほとんどを座って過ごす人が増えました。長時間座位は下半身の血液循環を阻害し、足に血液が滞りやすくなります。
また、筋肉は血液を押し戻すポンプの役割を果たしますが、運動不足により筋肉量が低下すると、このポンプ機能が弱まり、全身の血流が悪化します。
影響
足のむくみ
冷え性の悪化
下肢静脈瘤のリスク増大
2. ストレスと自律神経の乱れ
現代人は常に大量の情報と高いパフォーマンスを求められる環境にいます。慢性的なストレスは交感神経を優位にし、血管を収縮させます。その結果、末梢血流が低下し、冷えや筋肉のこわばりが起こります。
ストレスが続くと副腎皮質ホルモン(コルチゾール)の分泌が増え、血糖値や血圧を上昇させる一方で、血管内皮機能を低下させることも知られています。
3. 栄養の偏りと加工食品
便利で安価な加工食品や外食は、塩分・糖質・脂質が過剰になりがちです。特にトランス脂肪酸や精製糖質は血液をドロドロにし、血管内皮を傷つけます。
また、鉄・ビタミンB群・亜鉛などの造血に不可欠な栄養素が不足すると、血の量や質が低下し、巡りにも悪影響を及ぼします。
4. 冷えと環境要因
冷暖房の普及により、体温調節機能が低下している人が増えています。夏場の冷房による冷えや、冬場の暖房による急激な温度変化は、自律神経を乱し血管の収縮・拡張リズムを狂わせます。
さらに、冷たい飲み物や生野菜ばかりの食事も内臓を冷やし、血流を停滞させます。
5. 睡眠不足
睡眠中は副交感神経が優位になり、血管が拡張して修復が進みます。慢性的な睡眠不足はこの時間を削り、血管の回復を妨げます。
また、夜更かしは体内時計を乱し、ホルモン分泌や代謝のリズムを崩すため、長期的には血流障害のリスクを高めます。
6. 喫煙と過剰飲酒
タバコのニコチンは血管を急激に収縮させ、末梢の血流を悪化させます。加えて、一酸化炭素が酸素運搬能力を低下させるため、組織が慢性的な酸欠状態に陥ります。
アルコールは適量なら血管拡張効果がありますが、過剰摂取は肝臓の負担を増やし、血液中の脂質や老廃物を増やす原因になります。
7. 精神的要因
怒りや不安、悲しみといった強い感情は、瞬間的に交感神経を優位にして血管を収縮させます。これが繰り返されると血管の柔軟性が失われ、慢性的な血流障害へとつながります。
特に孤独感や慢性ストレスは炎症反応を促進し、血管老化を加速させることが近年の研究で示されています。
まとめ
血流の悪化は現代生活のあらゆる場面に潜んでいる
運動不足、ストレス、栄養不足、冷え、睡眠不足、喫煙・飲酒、精神的負担が主な原因
これらは単独で作用するだけでなく、互いに悪影響を及ぼし合い、血の質・量・巡りすべてを損なう
第4章 冷えを取る生活習慣
血流改善の第一歩は、体を「温める」ことから始まります。漢方的にも、冷えは万病のもととされ、体温の低下は血管を収縮させ、血の巡りを阻害します。現代人は冷暖房環境や飲食習慣の影響で、自覚がなくても慢性的な冷えを抱えている場合が多いのです。本章では、日常生活に取り入れられる冷え対策を具体的に解説します。
1. 漢方的「冷え」のとらえ方
漢方では冷えを単なる温度低下ではなく、「熱を生み出す力が不足している」または「熱を全身に巡らせる力が弱い」状態と見なします。
冷えには大きく分けて二種類あります。
全身性の冷え:体温が低く、手足だけでなく体幹も冷たい
末梢性の冷え:体幹は温かいが手足が冷える
どちらの場合も、血流を促す習慣が必要です。
2. 冷えを悪化させる生活習慣
冷房の効いた室内で長時間過ごす
冷たい飲み物やアイス、氷入りドリンクを日常的に摂る
生野菜や果物ばかりを大量に食べる(体を冷やす性質がある)
シャワーのみで入浴を済ませる
薄着や締め付けの強い服を好む
こうした習慣は、体表面や内臓の温度を下げ、血管を収縮させます。
3. 温めるための基本習慣
(1) 毎日の入浴
40℃前後の湯船に10〜15分つかることで、全身の血流が促進され、自律神経も副交感神経優位に切り替わります。半身浴よりも全身浴が効果的で、肩までしっかり温めるのがポイントです。
入浴時に足首やふくらはぎのマッサージを加えると、末梢循環がさらに改善されます。
(2) 温かい飲み物を選ぶ
冷たい飲み物は胃腸を冷やし、全身の代謝を下げます。常温〜温かい飲み物を基本とし、特に朝は白湯がおすすめです。生姜湯やハーブティーも体を内側から温めます。
(3) 服装の工夫
首・手首・足首は「三首」と呼ばれ、熱を逃しやすい部位です。スカーフやレッグウォーマーなどで保温すると、全身の温かさが保たれます。
4. 食事による温め効果
(1) 体を温める食材
根菜類(人参、ごぼう、れんこん)
発酵食品(味噌、納豆、漬物)
生姜、にんにく、ねぎ類
羊肉、鶏肉、青魚
これらは消化吸収の過程で熱を生み出し、血流を促します。
(2) 避けたい食材
冷たい飲食物
南国産の果物(バナナ、パイナップル、マンゴーなどは体を冷やす傾向)
過剰なカフェイン(利尿作用で体温低下を招く場合がある)
5. 運動で熱を作る
筋肉は体温の約4割を生み出す熱源です。特に太ももやふくらはぎの筋肉を鍛えることで、基礎代謝が上がり、血流改善にも直結します。
ウォーキング(1日30分)
スクワットや軽い筋トレ
ストレッチやヨガで関節と筋肉を柔らかく保つ
6. 季節ごとの冷え対策
冬:重ね着で保温し、特に腹部・腰部を冷やさない
夏:冷房対策として薄手のカーディガンや膝掛けを常備
梅雨:湿気による代謝低下に注意し、利尿作用のある食材(小豆、はと麦)で水分代謝を促す
まとめ
冷えは血流を阻害する最大の要因の一つ
入浴・温かい飲み物・三首の保温が基本
食事・運動・服装・季節ごとの工夫で内外から温める
冷えを取ることが血の質・量・巡りの改善につながる
第5章 血を増やす食事と栄養
血流を改善するためには「血を増やす」ことが欠かせません。いくら巡りを良くしても、血液そのものが不足していれば、酸素や栄養は十分に全身へ届かず、細胞の活動は低下します。漢方ではこの状態を**「血虚(けっきょ)」**と呼び、貧血や疲れやすさ、冷え、不眠、肌荒れなど多様な不調の原因と考えます。本章では、血を増やすための栄養素と食事法を詳しく解説します。
1. 血を構成する三大要素
血液は主に水分、赤血球、血漿タンパク質から成り立っています。このうち酸素を運ぶ赤血球は、鉄・たんぱく質・ビタミンB群がそろって初めて作られます。どれか一つでも不足すれば、質の良い血は作られません。
2. 鉄分――造血の主役
鉄はヘモグロビンの構成成分であり、酸素運搬の要です。鉄にはヘム鉄と非ヘム鉄があり、吸収率に大きな差があります。
ヘム鉄(吸収率15〜25%):赤身肉、レバー、カツオ、イワシ
非ヘム鉄(吸収率2〜5%):ほうれん草、小松菜、大豆製品
非ヘム鉄はビタミンCと一緒に摂ると吸収率が上がります。
3. たんぱく質――赤血球の土台
赤血球や血漿タンパク質の材料になるのがたんぱく質です。不足すると、血液量が減るだけでなく、免疫力や代謝も低下します。
動物性たんぱく質:肉、魚、卵、乳製品
植物性たんぱく質:大豆、豆腐、納豆、レンズ豆
動物性と植物性をバランスよく摂ることが望ましいとされます。
4. ビタミンB群――造血の潤滑油
特にビタミンB12と葉酸は赤血球を作る際に必須です。これらが不足すると、巨赤芽球性貧血を起こす可能性があります。
ビタミンB12:魚介類(サンマ、アジ、カキ)、卵、乳製品
葉酸:緑黄色野菜、枝豆、アスパラガス
5. 「血を作る」漢方的食材
漢方では、血虚を補うために以下のような食材が勧められます。
黒ごま、黒豆、なつめ、クコの実
鶏肉、羊肉、レバー
ほうれん草、にんじん、かぼちゃ
山芋、蓮の実
これらは体を温めながら造血を助けるとされます。
6. 血を減らす食習慣を避ける
血を増やすには、造血を阻害する習慣を減らすことも重要です。
カフェインの過剰摂取(鉄の吸収を妨げる)
過度なダイエット(栄養不足)
偏食(特定食品ばかり食べる)
過剰なアルコール(肝臓機能低下で造血阻害)
7. 食事のタイミングと調理法
鉄やビタミンは調理法や時間によって吸収率が変わります。
鉄分は酸性条件で吸収されやすい(レモン汁、酢を加える)
葉酸は熱に弱いので、生食や短時間加熱が望ましい
朝食にたんぱく質をしっかり摂ると、日中の代謝が活性化する
まとめ
血を増やすには鉄・たんぱく質・ビタミンB群の三本柱が不可欠
漢方的には黒色食材や温性食品が造血を助ける
栄養を阻害する生活習慣を見直すことも重要
調理法や組み合わせで吸収率を最大化する
第6章 血流を改善する運動と呼吸法
血流の改善には、日常生活における「体の動かし方」と「呼吸の仕方」が大きく関わっています。どれほど栄養を摂り、体を温めても、体を動かさなければ血液は全身をスムーズに巡りません。筋肉と呼吸は、血液を送り出す“第二のポンプ”として機能し、巡りを活性化させます。本章では、血流を促進するための運動と呼吸法を、漢方の視点と現代医学の両面から解説します。
1. 筋肉は「血流ポンプ」
心臓が全身に血液を送るメインポンプである一方、筋肉は補助ポンプとして血液循環に貢献します。特にふくらはぎの筋肉は「第二の心臓」と呼ばれ、歩行や屈伸運動によって足にたまった血液を心臓へ押し戻します。
筋肉低下による弊害
下半身のむくみ
足先の冷え
血圧の不安定化
代謝の低下
2. 血流を促す有酸素運動
血流改善のためには、酸素を取り込みながら体を動かす有酸素運動が効果的です。
おすすめの運動
ウォーキング:1日30分を目安に、背筋を伸ばし大股で歩く
サイクリング:膝への負担が少なく長時間継続しやすい
水中ウォーキング:水圧によるマッサージ効果と筋肉強化を同時に得られる
有酸素運動は血管を柔軟に保ち、毛細血管の発達も促進します。
3. 筋トレによる代謝向上
基礎代謝を高めるには筋肉量の維持・増加が欠かせません。特に太もも・臀部・背中など大きな筋肉を鍛えることで、安静時の血流量も増えます。
簡単な筋トレ例
スクワット(膝を痛めないよう浅めから)
ヒップリフト(仰向けでお尻を持ち上げる)
プランク(体幹を鍛え姿勢改善にも効果)
4. ストレッチと経絡刺激
漢方では、経絡(けいらく)の流れが滞ると血流も悪くなるとされます。筋肉を伸ばすストレッチは血管と経絡を同時に刺激し、巡りを整えます。
おすすめストレッチ部位
太もも前面(大腿四頭筋)
太もも裏(ハムストリングス)
肩甲骨周り(僧帽筋・広背筋)
5. 呼吸法で自律神経を整える
呼吸は血流改善に直結します。特に腹式呼吸は横隔膜の動きによって腹部の静脈を圧迫・解放し、下半身からの血液還流を助けます。また、副交感神経を優位にし、血管拡張を促します。
腹式呼吸の方法
背筋を伸ばし、肩の力を抜く
鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませる
口から細く長く息を吐き、お腹をへこませる
1日5分〜10分、朝晩行う
6. 「動」と「静」のバランス
運動と呼吸法はセットで行うことで効果が倍増します。ウォーキングなどの有酸素運動で血流を促し、その後に腹式呼吸やストレッチで自律神経を整える──この「動」と「静」の組み合わせが、持続的な血流改善につながります。
まとめ
筋肉は血流の補助ポンプとして重要
有酸素運動+筋トレで血管と筋肉を強化
ストレッチと経絡刺激で巡りを整える
腹式呼吸で自律神経を安定させ、血管拡張を促す
動と静を組み合わせた生活習慣が最も効果的
第7章 女性の血流とホルモンバランス
女性の体は、月経・妊娠・出産・更年期といったライフイベントを通じて、ホルモンバランスが大きく変化します。これらの変化は、血流と密接に関わっています。漢方医学でも、女性の健康の要を「血」に置くほど、女性にとって血流は重要なテーマです。本章では、生理周期、更年期、妊活の3つの局面を中心に、女性特有の血流変化と対策を解説します。
1. 生理周期と血流の変化
生理周期は大きく「月経期」「卵胞期」「排卵期」「黄体期」の4つに分かれ、それぞれでホルモンと血流の状態が異なります。
月経期(1〜5日目)
子宮内膜が剥がれ落ち、出血とともに血液が体外へ排出される時期。血の量が減りやすく、貧血症状や冷えが出やすい。
卵胞期(6〜13日目)
エストロゲンの分泌が増え、血流や代謝が安定する時期。肌や髪の調子も整いやすい。
排卵期(14日目前後)
血流が骨盤周辺に集中しやすく、腰回りの張りや重さを感じる人もいる。
黄体期(15〜28日目)
プロゲステロン優位になり、体が水分をため込みやすくなる。むくみや血行不良が起きやすい時期。
2. 月経不順・PMSと血流
月経不順やPMS(月経前症候群)は、ホルモン変動による自律神経の乱れと、骨盤内の血流不足が関係しています。
漢方では、これを「瘀血(おけつ)」や「気滞血瘀(きたいけつお)」と表現し、血の巡りを改善することで症状の軽減を目指します。
対策
下腹部や腰の温め(腹巻・カイロ)
骨盤回りのストレッチ
鉄・たんぱく質の補給で血を増やす
3. 更年期と血流の低下
更年期はエストロゲン分泌が急激に減少する時期で、血管の柔軟性が低下しやすくなります。その結果、のぼせ・ほてり・冷え・動悸・不眠などの更年期症状が現れます。
エストロゲンには血管拡張作用があるため、その減少は直接的に血流障害を引き起こします。
対策
有酸素運動で血管機能を維持
大豆イソフラボンなど植物性エストロゲンの摂取
深呼吸やヨガで自律神経の安定を図る
4. 妊活と血流
妊娠の成立には、卵巣や子宮への十分な血流が不可欠です。冷えや血虚、瘀血は子宮内膜の質を低下させ、着床や妊娠継続を難しくします。
著者の臨床経験でも、妊娠を望む女性に血流改善を行うと、妊娠率が高まるケースが多く報告されています。
血流改善のポイント
骨盤内の血流を促すストレッチやウォーキング
冷たい飲食物を避け、温かい食事中心にする
睡眠と休養をしっかり確保する
5. 女性の血流ケアに共通する生活習慣
毎日の入浴で全身と骨盤周辺を温める
鉄・たんぱく質・ビタミンB群を意識して摂取
適度な運動で下半身の巡りを促す
ストレスマネジメントで自律神経を安定
まとめ
女性の血流はホルモン変動の影響を強く受ける
生理周期、更年期、妊活などライフステージごとに血流ケアの方法を変える必要がある
温める・栄養を補う・巡らせるの3本柱が女性の血流改善の基本
第8章 心と血流の深い関係
血流は単に体の物理的な循環だけでなく、私たちの感情・思考・精神状態と密接に結びついています。ストレスや不安、怒り、悲しみといった感情は、直接的に血管や自律神経に影響を与え、血流を大きく左右します。著者・堀江昭佳氏も、数多くの臨床経験の中で「心の状態を整えることが血流改善につながる」と繰り返し強調しています。
1. ストレスと血流
ストレスを感じると、交感神経が優位になり、血管は収縮します。これは“戦うか逃げるか”の反応で、危険から身を守るための生理的仕組みです。しかし、現代人の多くは長期間にわたってこの反応が続いており、慢性的な血流障害の原因になっています。
ストレスによる血流低下のメカニズム
交感神経優位 → 血管収縮 → 末梢血流減少
コルチゾール増加 → 血糖値・血圧上昇
血管内皮細胞の機能低下 → 血流の柔軟性が失われる
2. 感情と自律神経
感情の変化は自律神経のバランスに直結します。
怒り → 急激な交感神経の興奮、血圧上昇
不安 → 呼吸が浅くなり酸素供給が低下
悲しみ → 代謝と循環の低下
漢方では、精神活動も「気・血・水」の流れの中に含まれると考えられ、心が乱れると血の巡りにも影響が及ぶとされています。
3. 孤独と炎症反応
近年の研究では、慢性的な孤独感が炎症性サイトカインを増加させ、血管老化や動脈硬化を促進することが分かってきました。孤独は単なる心理的問題ではなく、物理的に血管機能を衰えさせる要因です。
4. 心を整えることで血流を改善する方法
(1) 呼吸法
深くゆっくりとした腹式呼吸は副交感神経を優位にし、血管を拡張させます。特に「4秒吸って、6秒吐く」呼吸は即効性があります。
(2) マインドフルネス
今この瞬間の感覚に意識を向けるマインドフルネス瞑想は、ストレスホルモンを減らし、自律神経のバランスを整えます。
(3) 笑い
笑うことで副交感神経が優位になり、血管拡張物質である一酸化窒素(NO)の分泌が促されます。
(4) 良好な人間関係
社会的つながりは安心感を生み、自律神経とホルモンバランスを安定させます。
5. 漢方的アプローチ
漢方では、心身一如(しんしんいちにょ)という考え方があり、心の不調は体に、体の不調は心に影響するとされます。ストレスや緊張による血流障害には、気を巡らせる生薬(柴胡、香附子など)や、血の滞りを改善する生薬(丹参、桃仁など)が用いられます。
まとめ
心の状態は血流に直接影響を与える
ストレス・不安・孤独は血管収縮や炎症を引き起こす
呼吸法、瞑想、笑い、人間関係の改善は血流改善に有効
心と体を同時に整えることが、持続的な健康の鍵となる
第9章 漢方と血流改善の実践例
漢方医学は、体を「気・血・水」の3つの要素のバランスで捉え、その流れや量の異常が不調の原因になると考えます。特に血の巡りは生命活動の土台であり、改善することで多くの症状が和らぎます。本章では、著者の臨床経験や伝統的知見をもとに、症状別・体質別に血流改善の漢方的アプローチを解説します。
1. 血流の異常を示す三つのタイプ
漢方では血流の異常を大きく3つに分けます。
血虚(けっきょ)
血の量が不足している状態。貧血、めまい、動悸、冷え、乾燥肌などが特徴。
→ 改善には「血を増やす」食事や生薬(当帰、地黄、芍薬など)が使われます。
瘀血(おけつ)
血が滞り、流れが悪い状態。肩こり、頭痛、月経痛、シミ、慢性疲労など。
→ 改善には血行を促す生薬(丹参、川芎、紅花、桃仁など)が効果的。
血熱(けつねつ)
血が熱を帯び、炎症や発疹、出血傾向が見られる状態。
→ 改善には熱を冷まし血を整える生薬(牡丹皮、地黄、黄連など)が用いられます。
2. 症状別アプローチ
(1) 慢性的な冷え
原因:血虚・瘀血の併発が多い
対策:温める作用のある生薬(附子、乾姜)と血を補う生薬(当帰、熟地黄)を組み合わせる
生活習慣:入浴・足湯・ウォーキングを日課にする
(2) 生理痛・PMS
原因:瘀血と気滞(ストレスによる気の巡りの停滞)
対策:血行促進の桂枝茯苓丸、気を巡らせる香附子や柴胡を配合
生活習慣:骨盤周辺のストレッチ、下腹部を冷やさない
(3) 肩こり・頭痛
原因:瘀血、血虚、ストレスによる筋緊張
対策:川芎茶調散など血行を促す漢方を使い、同時に首・肩の筋肉をほぐす
生活習慣:デスクワーク中に1時間に1回立ち上がる習慣
(4) 不眠
原因:血虚による精神の安定不足、または血熱による興奮状態
対策:酸棗仁湯で精神を落ち着かせ、血虚には当帰や竜眼肉を加える
生活習慣:寝る前のスマホ・カフェインを避け、深呼吸や瞑想を取り入れる
(5) 肌荒れ・シミ
原因:瘀血や血熱
対策:血を巡らせる紅花、熱を冷ます牡丹皮などを組み合わせる
生活習慣:ビタミンC・Eの補給、紫外線対策
3. 体質別改善のポイント
血虚タイプ:栄養をしっかり摂る。鉄・たんぱく質・ビタミンB群を多めに。睡眠時間を確保。
瘀血タイプ:運動とストレッチで滞りを流す。長時間同じ姿勢を避ける。
血熱タイプ:辛い物・アルコールを控え、抗酸化食材(緑茶、ベリー類)を摂取。
4. 漢方と現代医療の併用
血流障害は西洋医学では生活習慣病や末梢循環不全として扱われます。漢方は根本的な体質改善を目的とし、西洋医学と併用することで効果が高まります。例えば、鉄欠乏性貧血には鉄剤+血を補う漢方、冷え性には運動療法+温補薬の併用が有効です。
5. 実際の臨床例
著者の臨床現場では、3か月以上の継続で明らかな血流改善が見られるケースが多いといいます。特に、妊活や更年期症状では、漢方+生活改善で症状が大きく軽減することが確認されています。
まとめ
漢方は血流の質・量・流れを整えるために有効
症状と体質を見極めて処方を選ぶことが重要
西洋医学との併用で効果がさらに高まる
継続は力なり。最低3か月以上の取り組みが望ましい
第10章 血流を整えて生きる未来
「血流がすべて解決する」という言葉は、決して誇張ではありません。血は酸素と栄養を全身に運び、老廃物を回収し、ホルモンや免疫機能を正常に保つ生命の根幹です。血流が整うことは、体の健康だけでなく、心の安定、人生の質の向上に直結します。本章では、これまでの内容を総括し、未来に向けて日々の生活で血流を整えるための具体的な指針を示します。
1. 血流が整った未来の自分を想像する
血流が良い状態では、以下のような変化が期待できます。
手足が温かく、冷えを感じにくい
疲れが溜まりにくく、朝スッキリ目覚められる
肌つやが良くなり、髪や爪も健康的になる
集中力や記憶力が高まり、仕事や勉強がはかどる
気分の落ち込みが減り、前向きに行動できる
これらはすべて、血流改善によって細胞が十分な酸素と栄養を受け取れるようになることで得られる恩恵です。
2. 日常生活に取り入れる血流習慣
(1) 朝のウォーミングアップ
朝起きたらまず、軽いストレッチや深呼吸を行い、血流スイッチを入れます。特に足首を回す、ふくらはぎを伸ばすなど下半身の血流促進が有効です。
(2) 食事で血を作る
鉄分:赤身肉、レバー、貝類
良質なたんぱく質:魚、卵、大豆製品
抗酸化成分:緑黄色野菜、ベリー類
水分補給:常温水やお茶をこまめに
(3) 適度な運動
ウォーキング、ヨガ、軽い筋トレなど、1日合計30分以上を目標にします。筋肉は血液を送り出すポンプとして機能するため、運動は直接的な血流改善につながります。
(4) 睡眠の質を上げる
寝る前のブルーライトを避け、部屋を暗く静かに保ちます。入浴後の体温低下がスムーズに起きるタイミングで就寝すると、副交感神経が優位になり血流が整います。
(5) ストレスマネジメント
呼吸法や瞑想を習慣化し、気持ちをリセットできる時間を1日の中に作ります。
3. 季節ごとの血流ケア
春:気温の変化による自律神経の乱れに注意。軽い運動と深呼吸で巡りを安定。
夏:冷房による冷えや水分不足に注意。常温飲料と温かい食事を心がける。
秋:乾燥で血の質が低下しやすい。オメガ3脂肪酸やビタミンEで血管を守る。
冬:血管収縮が強まり瘀血が悪化しやすい。入浴・温熱療法で徹底的に温める。
4. 未来志向の血流改善 ― 5年後・10年後の健康戦略
血流改善は即効性がある反面、継続してこそ長期的な効果が得られます。
5年後:冷え性や慢性疲労が解消し、生活習慣病リスクが低下
10年後:脳・心臓・血管の老化が遅れ、健康寿命が延びる
20年後:認知機能や筋力を保ち、介護予防につながる
5. 血流を整えるための自己チェックリスト
手足の冷えを感じないか
顔色や肌つやが良いか
睡眠後に疲れが取れているか
気分の浮き沈みが少ないか
集中力・記憶力が維持できているか
この5項目のうち3つ以上に自信が持てれば、血流はおおむね良好と考えられます。
6. 漢方と現代科学の融合
未来の血流改善は、東洋医学と西洋医学の融合によってさらに進化します。AIによる体質診断、遺伝子検査による個別化栄養指導、デジタルデバイスによる血流モニタリングなどが、漢方的アプローチと組み合わさることで、より精密な健康管理が可能になります。
まとめ
血流改善は人生の質を大きく高める
日々の小さな習慣が5年後、10年後の健康を決める
季節や年齢の変化に応じてケアを調整する
漢方と科学を組み合わせた未来志向の健康戦略が鍵
あとがき
血流を整えることは、単なる健康法ではなく、生き方そのものの質を高める行為です。毎日の食事や運動、入浴、睡眠、心の持ち方など、小さな習慣の積み重ねが、未来のあなたの血管・心臓・脳を守ります。
本解説を通じて、読者の皆様が「血流」というキーワードを常に意識し、自分の体と対話しながら日々を送れるようになれば、それは何よりの喜びです。
最後に、健康は一朝一夕には手に入りません。しかし、正しい知識と習慣は確実にあなたを変えます。本書がその第一歩となり、長く健やかな人生への架け橋となることを願っています。





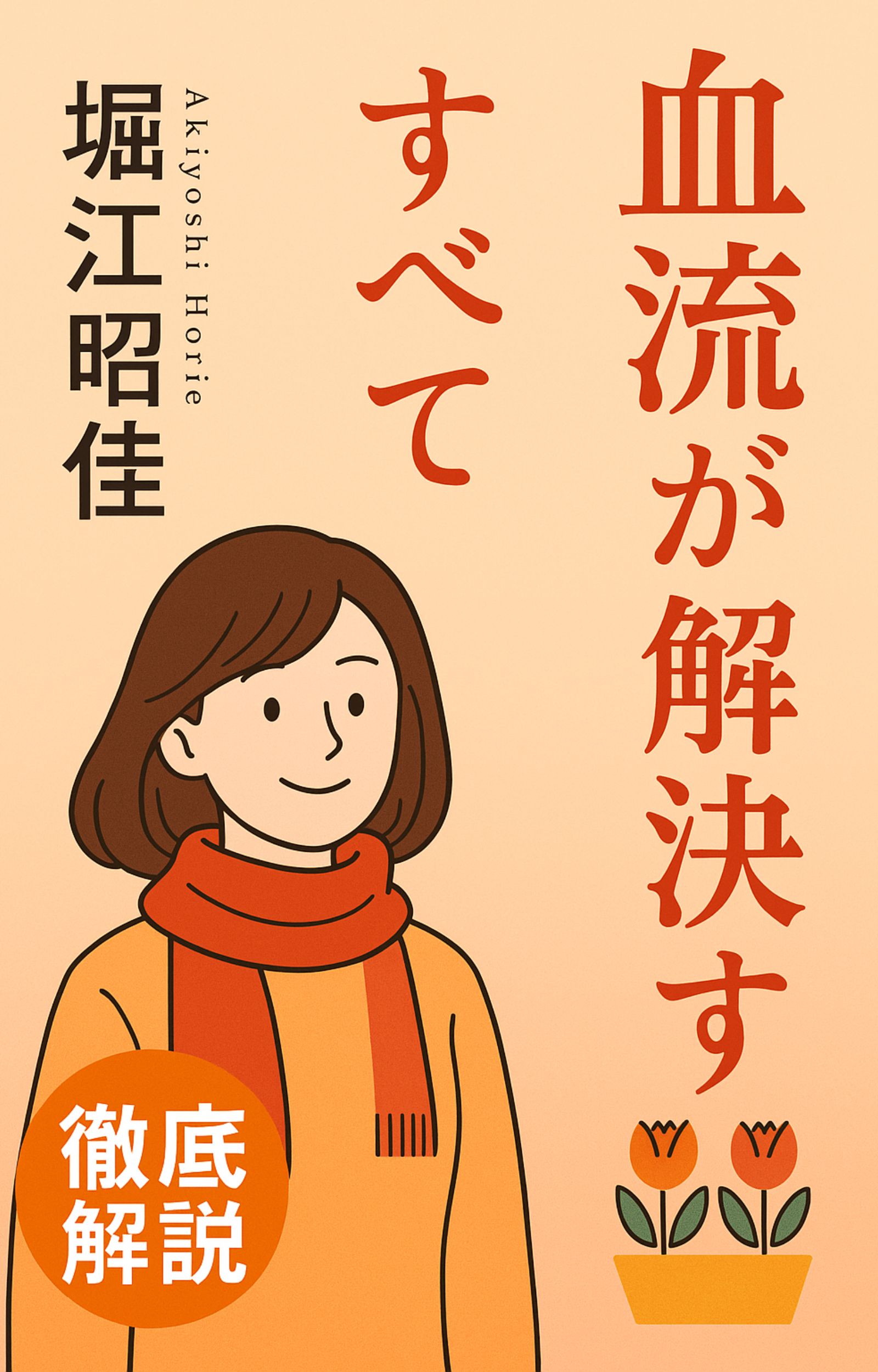


コメント